
クリストファー・コロンブスは偉人では無い。
以下の暦は全て西暦に変換しています。
日本の旧暦
中国の旧暦
ユダヤ暦
ヒジュラ暦
ソビエト連邦暦
フランス革命暦
≈は「頃」を意味しています。


|
クリストファー・コロンブスは偉人では無い。
|
|
| 年月日 | 出来事 | |||
|---|---|---|---|---|
| ≈ | 1,401 | 1 | 武寧が中山王国に帰還する。 | |
| 1,402 | 汪英紫が死去する。これにより、汪応祖が第3代南山王国国王に即位した。 | |||
| 1,402 | 11 | 14 | 後小松天皇が、落成した土御門東洞院殿の新しい内裏へ移徙する。足利義満は此れを祝い、日御座の御剣を新調して献上した。 | |
| ≈ | 1,402 | 12 | 察度の使者三五郎亹が、進貢の為、明へ向けて出港する。 | |
| 1,403 | 承察度が死去する。 | |||
| ≈ | 1,403 | 1 | 察度の使者王茂が、進貢の為、明へ向けて出港する。此の際汪応祖の使者宇座按司も同乗した。 | |
| ≈ | 1,403 | 1 | 攀安知の使者善佳古耶が、進貢の為、明へ向けて出港する。 | |
| 1,403 | 3 | 15 | 三五郎亹が明に対し、中山王国として33度目の進貢を行う。 | |
| 1,403 | 3 | 31 | 善佳古耶が明に対し、北山王国として12度目の進貢を行う。其の際、善佳古耶は冠服を請い、下賜された。 | |
| 1,403 | 4 | 5 |
以下2名が明に進貢を行う。 ①王茂(中山王国として34度目) ②使者・官生と呉宜堪弥結致(南山王国として14度目) 官生の貢物は、馬21頭と方物、呉宜堪弥結致の貢物は馬52頭・硫黄4,200kg・蘇木780kgであった。また、王は冠服を賜った。 |
|
| ≈ | 1,403 | 6 | 武寧が李氏朝鮮へ向けて出港する。途上、武蔵国六浦(現在の神奈川県横浜市金沢区)に漂着した。 | |
| ≈ | 1,403 | 6 | 三五郎亹が中山王国に帰還する。 | |
| ≈ | 1,403 | 7 |
以下の人間が帰還する。 ①王茂 ②宇座按司 ③使者・官生 ④呉宜堪弥結致 |
|
| ≈ | 1,403 | 7 | 善佳古耶が北山王国に帰還する。 | |
| ≈ | 1,404 | 1 | 武寧が中山王国に帰還する。 | |
| ≈ | 1,404 | 1 | 武寧の使者三五郎亹が、進貢の為、明へ向けて出港する。 | |
| ≈ | 1,404 | 2 | 攀安知の使者亜都結致が、進貢の為、明へ向けて出港する。 | |
| ≈ | 1,404 | 3 | 汪応祖の使者隗谷結致が、進貢の為、明へ向けて出港する。 | |
| ≈ | 1,404 | 3 | 武寧の使者が、進貢の為、明へ向けて出港する。 | |
| 1,404 | 4 | 1 | 三五郎亹が明に対し、中山王国として35度目の進貢を行う。此の際三五郎亹は、海船を賜った。 | |
| 1,404 | 4 | 25 | 亜都結致が明に対し、北山王国として13度目の進貢を行う。 | |
| 1,404 | 5 | 21 | 隗谷結致が明に対し、南山王国として15度目の進貢を行う。此の際隗谷結致は、海船を賜った。 | |
| 1,404 | 5 | 24 | 武寧の使者が明に対し、中山王国として36度目の進貢を行う。 | |
| ≈ | 1,404 | 6 | 三五郎亹が中山王国に帰還する。 | |
| ≈ | 1,404 | 7 | 亜都結致が北山王国に帰還する。 | |
| ≈ | 1,404 | 9 | 武寧の使者が中山王国に帰還する。 | |
| ≈ | 1,404 | 9 | 武寧の使者が、進貢の為、明へ向けて出港する。此の際汪応祖の使者も同乗した。 | |
| ≈ | 1,404 | 9 | 隗谷結致が南山王国に帰還する。 | |
| 1,404 | 11 | 29 |
以下2名が明に進貢を行う。 ①武寧の使者(中山王国として37度目) ②汪応祖の使者(南山王国として16度目) |
|
| 1,405 | 明王朝が、琉球からの使節に対応する為、泉州に市舶提挙司付属の「来遠駅」を設立する。 | |||
| ≈ | 1,405 | 2 |
以下2名が帰還する。 ①武寧の使者 ②汪応祖の使者 |
|
| ≈ | 1,405 | 2 | 武寧の使者三五郎亹が、進貢の為、明へ向けて出港する。 | |
| ≈ | 1,405 | 3 | 武寧の使者養埠結致が、進貢の為、明へ向けて出港する。 | |
| ≈ | 1,405 | 3 | 攀安知の使者赤佳結致が、進貢の為、明へ向けて出港する。 | |
| ≈ | 1,405 | 3 | 汪応祖の使者タキが、進貢の為、明へ向けて出港する。 | |
| 1,405 | 4 | 8 | 三五郎亹が明に対し、中山王国として38度目の進貢を行う。 | |
| 1,405 | 4 | 29 | 赤佳結致が明に対し、北山王国として14度目の進貢を行う。 | |
| 1,405 | 5 | 10 | 養埠結致が明に対し、中山王国として39度目の進貢を行う。 | |
| 1,405 | 5 | 16 | タキが明に対し、南山王国として18度目の進貢を行う。又、李傑が国子監に留学した。 | |
| ≈ | 1,405 | 7 | 三五郎亹が中山王国に帰還する。 | |
| ≈ | 1,405 | 8 | 養埠結致が中山王国に帰還する。 | |
| ≈ | 1,405 | 8 | 赤佳結致が北山王国に帰還する。 | |
| ≈ | 1,405 | 8 | タキが南山王国に帰還する。 | |
| ≈ | 1,405 | 8 | 養埠結致が南山王国に帰還する。 | |
| ≈ | 1,405 | 9 | 武寧の使者新川大親が暹羅へ向けて出港する。那覇にやって来た暹羅船に従って向かった。 | |
| ≈ | 1,405 | 11 | 武寧の使者新垣大親が、進貢の為、明へ向けて出港する。 | |
| ≈ | 1,405 | 11 | 攀安知の使者亜都結致が、進貢の為、明へ向けて出港する。 | |
| ≈ | 1,405 | 11 | 汪応祖の使者タキが、進貢の為、明へ向けて出港する。 | |
| 1,406 | 1 | 16 | 新垣大親が明に対し、中山王国として40度目の進貢を行う。 | |
| 1,406 | 1 | 16 | 亜都結致が明に対し、北山王国として15度目の進貢を行う。 | |
| 1,406 | 1 | 16 | タキが明に対し、南山王国として19度目の進貢を行う。 | |
| ≈ | 1,406 | 2 | 武寧の使者三五郎亹が、進貢の為、明へ向けて出港する。此の際汪応祖の使者も同乗した。 | |
| 1,406 | 3 | 21 |
以下2名が明に進貢を行う。 ①三五郎亹(中山王国として41度目) ②汪応祖の使者(南山王国として20度目) |
|
| ≈ | 1,406 | 6 | 新垣大親が中山王国に帰還する。 | |
| ≈ | 1,406 | 6 | 亜都結致が北山王国に帰還する。 | |
| ≈ | 1,406 | 6 | タキが南山王国に帰還する。 | |
| ≈ | 1,406 | 7 | 新川大親が中山王国に帰還する。 | |
| ≈ | 1,406 | 8 |
以下2名が帰還する。 ①三五郎亹 ②汪応祖の使者 |
|
| ≈ | 1,407 | 2 | 武寧の使者タキが、進貢の為、明へ向けて出港する。 | |
| ≈ | 1,407 | 2 | 尚思紹王の使者三五郎亹が、進貢の為、明へ向けて出港する。 | |
| 1,407 | 4 | 8 | タキが明に対し、南山王国として21度目の進貢を行う。 | |
| 1,407 | 5 | 18 | 三五郎亹が、中山王国として42度目の進貢を行う。此の際三五郎亹は、武寧の訃報を伝え、尚思紹王を武寧の世子として、第3代明皇帝永楽帝に対し冊封を請うた。 | |
| ≈ | 1,407 | 7 | タキが南山王国に帰還する。 | |
| ≈ | 1,407 | 8 | 三五郎亹が中山王国に帰還する。 | |
| ≈ | 1,408 | 2 | 尚思紹王の使者大グスク大親が、進貢の為、明へ向けて出港する。 | |
| ≈ | 1,408 | 2 | 汪応祖の使者曵達姑耶が、進貢の為、明へ向けて出港する。 | |
| 1,408 | 4 | 22 | 大グスク大親が明に対し、中山王国として43度目の進貢を行う。 | |
| 1,408 | 4 | 22 | 曵達姑耶が明に対し、南山王国として22度目の進貢を行う。其の後李傑が、帰国の為、南山王国行きの船に同乗した。 | |
| ≈ | 1,408 | 7 | 大グスク大親が中山王国に帰還する。 | |
| ≈ | 1,408 | 7 |
以下2名が南山王国に帰還する。 ①曵達姑耶 ②李傑 |
|
| ≈ | 1,409 | 2 | 尚思紹王の使者三五郎亹が、進貢の為、明へ向けて出港する。 | |
| ≈ | 1,409 | 3 | 汪応祖の使者大グスク大親が、進貢の為、明へ向けて出港する。 | |
| 1,409 | 5 | 25 | 三五郎亹が明に対し、中山王国として44度目の進貢を行う。此の際三五郎亹は永楽帝の居る北京まで行き、海船を賜った。 | |
| ≈ | 1,409 | 6 | 尚思紹王の使者新川大親が李氏朝鮮へ向けて出港する。武寧の側室であった朝鮮人を送還した。 | |
| 1,409 | 7 | 11 | 大グスク大親が、永楽帝の居る北京へ出向き、明に対し、南山王国として23度目の進貢を行う。又、李傑が再度国子監に留学した。 | |
| ≈ | 1,409 | 8 | 三五郎亹が中山王国に帰還する。 | |
| ≈ | 1,409 | 10 | 大グスク大親が南山王国に帰還する。 | |
| ≈ | 1,410 | 1 | 新川大親が中山王国に帰還する。 | |
| ≈ | 1,410 | 2 | 尚思紹王の使者中グスク大親が、進貢の為、明へ向けて出港する。 | |
| ≈ | 1,410 | 4 | 尚思紹王の使者新川大親が、進貢の為、明へ向けて出港する。 | |
| 1,410 | 4 | 9 | 中グスク大親が明に対し、中山王国として45度目の進貢を行う。 | |
| ≈ | 1,410 | 6 | 尚思紹王の使者本部大親が李氏朝鮮へ向けて出港する。 | |
| ≈ | 1,410 | 6 | 尚思紹王の使者慈空禅師が日本へ向けて出港する。 | |
| ≈ | 1,410 | 7 | 中グスク大親が中山王国に帰還する。 | |
| 1,410 | 7 | 31 | 新川大親が明に対し、中山王国として46度目の進貢を行う。此の際新川大親は永楽帝の居る北京まで行った。 | |
| ≈ | 1,410 | 10 | 新川大親が中山王国に帰還する。 | |
| ≈ | 1,410 | 11 | 尚思紹王の使者三五郎亹が、進貢の為、明へ向けて出港する。 | |
| 1,411 | 大友親著の四男大友親繁が生誕する。 | |||
| ≈ | 1,411 | 1 | 慈空禅師が中山王国に帰還する。 | |
| ≈ | 1,411 | 1 | 本部大親が中山王国に帰還する。 | |
| 1,411 | 1 | 18 |
三五郎亹が明に対し、中山王国として47度目の進貢を行う。又、以下2名が国子監に留学した。 ①ファイテ ②ジルーク |
|
| ≈ | 1,411 | 2 |
以下2名の尚思紹王の使者が、進貢の為、明へ向けて出港する。 ①程復 ②具志頭大親 |
|
| ≈ | 1,411 | 4 | 三五郎亹が中山王国に帰還する。 | |
| ≈ | 1,411 | 4 | 尚思紹王の使者本部大親が、進貢の為、明へ向けて出港する。 | |
| 1,411 | 4 | 25 |
以下2名が明に対し、中山王国として48度目の進貢を行う。 ①程復 ②具志頭大親 程は其の儘帰国した。又、王茂が中山王国の国相に就任した。 |
|
| ≈ | 1,411 | 6 | 尚思紹王の使者慈空禅師が日本へ向けて出港する。 | |
| ≈ | 1,411 | 6 | 尚思紹王の使者新川大親が李氏朝鮮へ向けて出港する。勝連按司の船で向かった。 | |
| ≈ | 1,411 | 7 | 具志頭大親が中山王国に帰還する。 | |
| 1,411 | 7 | 17 | 本部大親が明に対し、中山王国として49度目の進貢を行う。 | |
| ≈ | 1,411 | 10 | 本部大親が中山王国に帰還する。 | |
| ≈ | 1,411 | 10 | 尚思紹王の使者三五郎亹が、進貢の為、明へ向けて出港する。 | |
| ≈ | 1,411 | 12 | 尚思紹王の使者タブチが、進貢の為、明へ向けて出港する。 | |
| ≈ | 1,412 | 1 | 汪応祖の使者大グスク大親が、進貢の為、明へ向けて出港する。 | |
| ≈ | 1,412 | 1 | 慈空禅師が中山王国に帰還する。 | |
| ≈ | 1,412 | 1 | 新川大親が中山王国に帰還する。 | |
| 1,412 | 1 | 7 | 三五郎亹が明に対し、中山王国として50度目の進貢を行う。 | |
| 1,412 | 1 | 30 | タブチが明に対し、中山王国として51度目の進貢を行う。 | |
| ≈ | 1,412 | 2 | 三五郎亹が中山王国に帰還する。 | |
| ≈ | 1,412 | 3 | 尚思紹王の使者具志頭大親が、進貢の為、明へ向けて出港する。 | |
| ≈ | 1,412 | 4 | タブチが中山王国に帰還する。 | |
| 1,412 | 4 | 1 | 大グスク大親が明に対し、南山王国として24度目の進貢を行う。此の際大グスク大親は、海船を賜った。 | |
| 1,412 | 5 | 26 | 具志頭大親が明に対し、中山王国として52度目の進貢を行う。 | |
| ≈ | 1,412 | 6 | 大グスク大親が南山王国に帰還する。 | |
| ≈ | 1,412 | 6 | 尚思紹王の使者慈空禅師が日本へ向けて出港する。 | |
| ≈ | 1,412 | 6 | 尚思紹王の使者本部大親が李氏朝鮮へ向けて出港する。勝連按司の船で向かった。 | |
| ≈ | 1,412 | 8 | 具志頭大親が中山王国に帰還する。 | |
| ≈ | 1,412 | 11 | 尚思紹王の使者島尻大親が、進貢の為、明へ向けて出港する。 | |
| ≈ | 1,412 | 12 | 尚思紹王の使者タブチが、進貢の為、明へ向けて出港する。 | |
| ≈ | 1,413 | 1 | 慈空禅師が中山王国に帰還する。 | |
| ≈ | 1,413 | 1 | 本部大親が中山王国に帰還する。 | |
| ≈ | 1,413 | 2 | 汪応祖の使者呉是佳結制が、進貢の為、明へ向けて出港する。 | |
| 1,413 | 2 | 16 | 島尻大親が明に対し、中山王国として53度目の進貢を行う。 | |
| ≈ | 1,413 | 3 | 尚思紹王の使者三五郎亹が、進貢の為、明へ向けて出港する。 | |
| 1,413 | 3 | 4 | タブチが明に対し、中山王国として54度目の進貢を行う。又、3名の官生が国子監に留学した。 | |
| ≈ | 1,413 | 5 | 汪応祖の使者李仲が、進貢の為、明へ向けて出港する。 | |
| ≈ | 1,413 | 5 | 島尻大親が中山王国に帰還する。 | |
| ≈ | 1,413 | 5 | タブチが中山王国に帰還する。 | |
| 1,413 | 5 | 20 | 呉是佳結制が、永楽帝の居る北京へ出向き、明に対し、南山王国として25度目の進貢を行う。此の際呉是佳結制は、永楽銭を賜った。 | |
| 1,413 | 5 | 20 | 三五郎亹が、永楽帝の居る北京へ出向き、明に対し、中山王国として55度目の進貢を行う。此の際三五郎亹は、永楽銭を賜った。 | |
| ≈ | 1,413 | 6 | 尚思紹王の使者慈空禅師が日本へ向けて出港する。 | |
| ≈ | 1,413 | 6 | 尚思紹王の使者本部大親が李氏朝鮮へ向けて出港する。勝連按司の船で向かった。 | |
| ≈ | 1,413 | 8 | 呉是佳結制が南山王国に帰還する。 | |
| ≈ | 1,413 | 8 | 三五郎亹が中山王国に帰還する。 | |
| 1,413 | 9 | 12 | 李仲が、永楽帝の居る北京へ出向き、明に対し、南山王国として26度目の進貢を行う。李仲は病を患い、李傑が福州まで送った。 | |
| ≈ | 1,413 | 10 | 尚思紹王の使者南風原大親が、進貢の為、明へ向けて出港する。 | |
| ≈ | 1,413 | 12 | 慈空禅師が中山王国に帰還する。 | |
| ≈ | 1,413 | 12 | 本部大親が中山王国に帰還する。 | |
| ≈ | 1,413 | 12 | 李仲が南山王国に帰還する。 | |
| 1,414 | 1 | 20 | 南風原大親が、永楽帝の居る北京へ出向き、明に対し、中山王国として56度目の進貢を行う。 | |
| ≈ | 1,414 | 6 | 尚思紹王の使者慈空禅師が日本へ向けて出港する。 | |
| ≈ | 1,414 | 6 | 尚思紹王の使者本部大親が李氏朝鮮へ向けて出港する。勝連按司の船で向かった。 | |
| ≈ | 1,414 | 6 | 南風原大親が中山王国に帰還する。 | |
| ≈ | 1,414 | 7 | 尚思紹王の使者三五郎亹が、進貢の為、明へ向けて出港する。 | |
| 1,414 | 10 | 18 | 三五郎亹が、永楽帝の居る北京へ出向き、明に対し、中山王国として57度目の進貢を行う。 | |
| ≈ | 1,415 | 1 | 他魯毎の使者郭是佳結制が、進貢の為、明へ向けて出港する。 | |
| ≈ | 1,415 | 1 | 三五郎亹が中山王国に帰還する。 | |
| 1,415 | 1 | 6 | 第4代室町幕府征夷大将軍足利義持が、中山王国へ向けて書簡を記す。慈空禅師が此れを受け取った。 | |
| ≈ | 1,415 | 2 | 慈空禅師が中山王国に帰還する。 | |
| ≈ | 1,415 | 2 | 本部大親が中山王国に帰還する。 | |
| ≈ | 1,415 | 2 | 尚思紹王の使者南風原大親が、進貢の為、明へ向けて出港する。此の際攀安知の使者リュウインも同乗した。 | |
| 1,415 | 4 | 28 | 郭是佳結制が、永楽帝の居る北京へ出向き、明に対し、南山王国として27度目の進貢を行う。此の際、汪応祖が崩御した事を報告し、冊封を請うた。 | |
| 1,415 | 5 | 27 |
以下2名が、永楽帝の居る北京へ出向き、明に進貢を行う。 ①南風原大親(中山王国として58度目) ②リュウイン(北山王国として16度目) リュウインは海船を賜った。 |
|
| ≈ | 1,415 | 6 | 尚思紹王の使者慈空禅師が日本へ向けて出港する。 | |
| ≈ | 1,415 | 6 | 尚思紹王の使者本部大親が李氏朝鮮へ向けて出港する。勝連按司の船で向かった。 | |
| ≈ | 1,415 | 6 | 尚巴志の使者末吉大親が、進貢の為、明へ向けて出港する。 | |
| ≈ | 1,415 | 7 | 郭是佳結制が南山王国に帰還する。 | |
| 1,415 | 7 | 6 | ヤン・フスが火刑に処せられる。 | |
| 1,415 | 8 | 21 | 朝、ポルトガル王国アヴィス朝の王ジョアン1世が、マリーン朝のセウタ(現在のモロッコに隣接するスペインの自治都市)への奇襲襲撃の為、息子のエンリケ王子と200隻の船で運ばれた45,000名の部隊を率いて、サン・アマロ海岸に上陸した。セウタの守備隊を油断を突いて攻撃し、日暮れまでに町は占領された。 | |
| 1,415 | 9 | 28 | 末吉大親が、永楽帝の居る北京へ出向き、明に対し、中山王国として59度目の進貢を行う。 | |
| ≈ | 1,415 | 10 |
以下2名が帰還する。 ①南風原大親 ②リュウイン |
|
| ≈ | 1,415 | 11 | 尚思紹王の使者三五郎亹が、進貢の為、明へ向けて出港する。其の際、冊封使の為の船を送って行った。 | |
| ≈ | 1,416 | 1 | 末吉大親が中山王国に帰還する。 | |
| ≈ | 1,416 | 2 | 慈空禅師が中山王国に帰還する。 | |
| ≈ | 1,416 | 2 | 本部大親が中山王国に帰還する。 | |
| ≈ | 1,416 | 2 | 他魯毎の使者郭義才が、進貢の為、明へ向けて出港する。 | |
| ≈ | 1,416 | 2 | 尚思紹王の使者韓完義が、進貢の為、明へ向けて出港する。 | |
| 1,416 | 2 | 25 | 三五郎亹が、永楽帝の居る北京へ出向き、明に対し、中山王国として60度目の進貢を行う。此の際三五郎亹は、海船を賜った。 | |
| 1,416 | 5 | 6 | 郭義才が、明に対し、南山王国として28度目の進貢を行う。此の際郭義才は、冊封に対し謝意を示した。 | |
| 1,416 | 5 | 6 | 韓完義が、明に対し、中山王国として61度目の進貢を行う。 | |
| ≈ | 1,416 | 6 | 三五郎亹が中山王国に帰還する。 | |
| 1,416 | 7 | 25 | 仙洞御所が炎上する。紫宸殿も危険な状態に陥った。第101代天皇称光天皇は、自ら日御座の御剣を帯び、紫宸殿の防火を指揮した。其れを見て感動した周囲の人々が、屋根に上り火の粉を防ぎ、紫宸殿は類焼を免れた。 | |
| ≈ | 1,416 | 10 | 郭義才が南山王国に帰還する。 | |
| ≈ | 1,416 | 10 | 韓完義が中山王国に帰還する。 | |
| ≈ | 1,421 | 河野通元の嫡男河野通春が生誕する。 | ||
| 1,431 | 大宮長興が左大史に任命される。しかし、官務の地位は壬生家が握り、大宮は任命されなかった。 | |||
| 1,435 | 壬生晨照が左大史に任命される。加えて、官務に任ぜられた。 | |||
| 1,439 | 3 | 3 |
以下2名の間に、足利義視が生誕する。 ①足利義教 ②義教の側室小宰相局 義視は、義教の拾男に当たる。 |
|
| 1,439 | 3 | 9 | 室町幕府が、第10代室町幕府伊予国守護で河野氏宗家当主の河野教通に、足利持氏征伐の為の美濃国での待機を命じる。 | |
| 1,439 | 4 | 5 | 足利義視が、正親町三条実雅の養君となる。 | |
| ≈ | 1,441 | 8 | 14 | 河野教通が、室町幕府の命を受けて、嘉吉の乱での赤松家征伐に於いて遅参した事を理由に、予州家当主河野通春の征伐を開始する。 |
| ≈ | 1,442 | 4 |
以下にて合戦が発生する。 ①千手城(現在の福岡県嘉麻市千手) ②馬見城(現在の福岡県嘉麻市馬見) 平賀頼宗も大内教弘に付いて戦闘に参加し、大内教幸と対峙した。教幸は、教弘の跡目相続に不満を持ち、大友持直・少弐氏に与していた。 |
|
| 1,443 | ハングル文字が発明される。 | |||
| 1,443 | 足利義視が出家する。 | |||
| 1,443 | 上杉持朝の参男上杉定正が生誕する。 | |||
| ≈ | 1,443 | 1 |
第15代管領畠山持国が、以下3名の落所を早急に訪ねて治罰を与えよという命を大友一族の志賀親賀・志賀親昌に下す。 ①少弐教頼 ②大友持直 ③大内教幸 |
|
| 1,443 | 10 | 16 |
後南朝に与する一党が、内裏を襲撃し、三種の神器の内以下を奪い、比叡山に逃れる。 ①天叢雲剣 ②八尺瓊勾玉 |
|
| 1,444 |
氏継系であった大友親繁が、親世系であった第14代大友家当主大友親隆の娘を正室として迎える事を条件に、第9代室町幕府豊後国守護職に補任され、第15代大友家当主となる。此れにより、西暦1,368年以降続いた大友家の両統迭立に終止符が打たれた。又同年、以下2名の間に大友政親が産まれた。 ①親繁 ②親隆の娘 |
|||
| ≈ | 1,444 | 5 | 室町幕府が、安芸国の小早川煕平等に対し、河野教通の援助を命じる。 | |
| ≈ | 1,445 | 3 | 大宮長興が官務に任命される。室町幕府に訴えた結果であった。 | |
| ≈ | 1,445 | 12 |
壬生晨照が官務に任命される。大宮長興から官務の地位を奪い返した。大宮は、以下に家司として仕え、室町幕府との関係を維持する事で壬生家に対抗しようとした。 ①近衛家 ②一条家 |
|
| 1,446 | 7 | 6 |
豊前国守護代杉武勝が、光岡城(現在の大分県宇佐市赤尾)周辺の5ヶ村に於いて、以下の人間が合戦を行なって敵を退けたという主旨の推挙状を出す。 ①大内教幸 ②宇佐郡上田氏・時永氏・野上氏 ③下毛郡秣氏・森山氏 |
|
| ≈ | 1,449 | 2 | 河野通春が、細川勝元の支援を受け、第11代室町幕府伊予国守護に就任する。 | |
| ≈ | 1,449 | 7 | 河野教通方の村上吉資が、佐礼城(現在の愛媛県今治市玉川町別所)を攻略する。 | |
| 1,449 | 7 | 4 | 河野教通が、村上吉資の佐礼城での戦功を賞する。 | |
| ≈ | 1,449 | 11 | 大宮長興が官務に任命される。壬生晨照から官務の地位を奪還した。 | |
| 1,450 | 1 | 13 | 大宮長興が、大宮家の文庫を造営する事を朝廷に申し入れ、朝廷から室町幕府に文庫造営を命じて貰う様訴える。 | |
| 1,450 | 6 | 30 | 大宮長興が「私の文庫の修繕や宿所を整備する為の費用として、昨年公家が請け負っていた徴収金を武家から出す様にとの命令が有った。そして、其の管理を第17代管領畠山持国に委ねる旨の御教書が出された。播磨国と丹波国に就いては、守護職が請け負い執り仕切る様にとの指示が有り、播磨国の費用として本日100疋が届いた。此れを担当するのは飯尾之種と飯尾之清の両名である。今回は初回なので、先ず130貫文が私の所に直接送られる事となり、本日到着した。此れは喜ばしい事だ」という主旨の発言をする。 | |
| 1,450 | 8 | 20 | 足利義政が、吉川経信に対し、伊予国へ渡り河野教通を支援する様命じる。 | |
| 1,450 | 9 | 14 | 此の時点で、文庫の修理及び宿所の上層部の移住の為の費用として、諸国の段銭を目安に徴収する事が命じられる予定であった。大宮長興だけでなく壬生晨照からも官文庫修繕が出ており、足利義政自身が畠山持国に管理を委ねた。しかし、使者が尾張国へまだ下向していなかった。 | |
| 1,450 | 9 | 24 | 室町幕府が、小早川盛景に、伊予国へ渡り教通を支援する様命じる。又足利義政は、河野教通を第12代室町幕府伊予国守護として再任させた。 | |
| 1,450 | 11 | 25 | 官文庫の修繕費用として、段銭500貫文が尾張国から届けられる。 | |
| 1,450 | 11 | 25 | 官文庫の修繕費用として、段銭500貫文が尾張国から届けられる。 | |
| 1,451 | 日明貿易の一環で、第11次遣明船10隻が出発する。6号船は、大友親繁が仕立てた。 | |||
| 1,451 |
村上吉資を含む以下の三家が、予州家方に寝返る。 ①因島村上家 ②来島村上家 ③能島村上家 此れを受けて河野教通率いる軍は、来島村上家の本拠地である来島城(現在の愛媛県今治市来島)を攻撃し、落城させた。 |
|||
| 1,451 | 5 | 11 |
室町幕府が、以下2名に対し、伊予国へ渡り河野教通を支援する様督促する。 ①杉原伯耆守 ②小早川盛景 |
|
| ≈ | 1,451 | 7 |
河野教通が、以下の支援により、河野通春に呼応した城郭20ヶ所余を奪取する。 ①小早川盛景 ②重見通実 ③森山氏 ④竹原盛景 ⑤益田兼堯 ⑥吉川三郎 ⑦周布次郎 小早川・重見・森山氏・竹原は連携して、通春方の抵抗勢力を制圧した。又、益田は吉田(現在の愛媛県宇和島市)で、吉川・周布は鐘挊尾・味酒(現在の愛媛県松山市)にて戦功を挙げた。教通は、小早川の尽力に対して謝意を表し、其の功績を室町幕府に報告した。重見は、宇和郡の大野氏と喜多郡の森山氏の連合体制が出来上がった旨を、小早川等に伝えた。 |
|
| 1,451 | 7 | 24 | 室町幕府が、小早川盛景の部下の戦功を賞する。 | |
| 1,451 | 8 | 15 | 室町幕府が、益田兼堯の吉田での戦功を賞する。 | |
| ≈ | 1,451 | 8 | 小早川煕平が、伊予国三島七島内下島(現在の広島県呉市の大崎下島)を、自身の嫡男小早川敬平に譲る。 | |
| 1,451 | 9 | 14 |
重見通実が、以下2名に対し、河野通春征伐の為の合力を依頼する。 ①杉原伯耆守 ②小早川盛景 |
|
| 1,451 | 9 | 20 |
室町幕府が、以下3名の鐘挊尾・味酒での戦功を賞する。 ①益田兼堯 ②吉川三郎 ③周布次郎 |
|
| 1,452 | ボローニャでユダヤ人判別の印の着用義務が課せられる。 | |||
| 1,452 | 畠山持富が死去する。 | |||
| 1,452 | 1 | 17 |
室町幕府が、以下2名に対し、河野教通の支援の為の伊予国への発向を命じる。 ①吉川経信 ②出羽祐房 |
|
| ≈ | 1,452 | 11 | 河野通春方の森山氏が、森山城(現在の愛媛県伊予市大平)にて挙兵する。室町幕府は、吉川経信に、伊予国へ発向し、河野教通を支援する形で森山氏を征伐する様命じた。 | |
| ≈ | 1,452 | 11 |
以下2名が、森山城・天神森城(現在の愛媛県上浮穴郡久万高原町西明神)にて、森山氏を破る。 ①吉川経信 ②益田兼堯 |
|
| 1,452 | 11 | 20 | 河野通春が、浄寂寺(現在の愛媛県今治市五十嵐)に対する、諸給人の干渉及び段銭等の課役を停止する。 | |
| 1,452 | 12 | 7 |
室町幕府が、以下2名に対し、森山城・天神森城(現在の愛媛県上浮穴郡久万高原町西明神)での戦功を賞する。 ①吉川経信 ②益田兼堯 |
|
| 1,453 | 大内教弘が当主を務める大内氏が、日明貿易に参加する。以降細川家と競合した。 | |||
| 1,453 | 5 | 16 | 西園寺公広が、歯長寺(現在の愛媛県西予市宇和町伊賀上)住持昌宗に、永長郷(現在の愛媛県西予市宇和町永長)成俊名等の旧領を返付する。 | |
| 1,453 | 5 | 27 | 細川勝之が、安芸国の小泉興平に対し、越智郡大島(現在の愛媛県今治市)の地頭職等を安堵する。 | |
| 1,453 | 5 | 29 | 東ローマ帝国の首都コンスタンティノープル(現在のイスタンブール)が第7代オスマン帝国スルタンのメフメト2世によって陥落され、東ローマ帝国が滅亡する。 | |
| ≈ | 1,453 | 6 | 細川勝元が、足利義政の意向を聞かず、河野通春を第13代室町幕府伊予国守護として改補する。其の後河野は、京都から伊予国へ帰国したが、其の際、村上吉資が河野を援助した。細川の此の行動は、足利との対立を生み、細川は管領職を辞任しようとした。しかし、足利の慰留により、思い留まった。 | |
| 1,453 | 6 | 21 | 細川勝元が、村上吉資に対し、河野通春の伊予国への帰国の際に援助した事を賞する御教書を発する。 | |
| 1,455 | 10 | 13 |
以下2名の間に陶弘護が生誕する。 ①第7代陶家当主陶弘房 ②仁保盛郷の娘 |
|
| 1,456 |
村上治部進が、東寺から、弓削島荘(現在の愛媛県上島町)の所務請負の話を持ち掛けられる。此の時点で弓削島荘は、以下の4家が支配していた。 ①安芸国小泉家 ②讃岐国山路家 ③能島村上家の2つの家系 村上は、所務請負を引き受けるに当たり、条件として、細川勝元の折紙を要求した。小泉家や山路家が、細川の家人である為である。但村上は、能島村上家に対しては、細川の折紙を要求している事は口外しない様釘を刺した。 |
|||
| 1,456 | 2 | 5 | 室町幕府が、河野通春の伊予国守護職を罷免し、細川勝元を第14代室町幕府伊予国守護に任命する。此れにより細川は、土佐国守護職との兼任となった。 | |
| 1,456 | 6 | 10 |
村上治部進が、弓削島荘の状況に就いての書簡を東寺地蔵堂に提出する。以下2点等が報告された。 ①弓削島荘は以下の4家が支配している。 ❶小泉家 ❷山路家 ❸能島村上家の2つの家系 ②①の内、小泉家と山路家は細川勝元に奉公する面々である。 |
|
| ≈ | 1,456 | 6 | 10 | |
| 1,456 | 10 | 15 | 細川勝元が、村上治部進に、有名無実となっていた弓削島荘の知行を命じる御内書を発給する。又細川は、村上に弓削島荘の年貢を送る様命じた。 | |
| 1,456 | 10 | 20 | 東寺公文所が、村上治部進に、細川勝元の御内書を送る。東寺公文所は、村上に対し、此の御内書に従って弓削島所務を厳密に行う様伝えた。 | |
| ≈ | 1,456 | 12 | 大内教弘が、門松や祇園会に筥崎松を伐採・使用する事を禁止する。 | |
| 1,457 | 河野教通が、自身の弟河野通秋を養子とし、家督を譲る。 | |||
| 1,457 | 12 | 18 | 嘉吉の乱で没落した赤松氏の遺臣が、再興を目指して後南朝から八尺瓊勾玉を奪い返す。後南朝に好意を持つと見せ掛け、巧みに接近し内情を探った後、夜襲を仕掛けて奪い取った。 | |
| ≈ | 1,459 | 10 |
畠山政久が死去する。後継者は、以下3名の支持により、畠山政長となった。 ①遊佐長直 ②神保長誠 ③成身院光宣 遊佐・神保・成身院は、政長に従順し仕えた。 |
|
| 1,460 | 1 | 11 | 河野通春が、足利義持の年忌法要の費用40貫文を負担する。 | |
| 1,460 | 7 | 10 | ゲットー(ユダヤ人隔離居住区)をフランクフルト・アム・マイン(現在のドイツのヘッセン州)に建設される事が決定される。 | |
| 1,460 | 12 | 21 | 室町幕府が、小早川煕平に対し、弓削島荘の状況を報告する様命じる。 | |
| 1,461 | フランシスコ会修道士のバルナバ・ダ・テルニがペルージャでモンテ・ディ・ピエタという公営の質屋を設立した。貧民に対する慈善事業として、比較的低い利子で貸出を行った。 | |||
| ≈ | 1,461 | 1 | 河野教通が、室町幕府に対し、古代以来の先祖の勲功を列挙し、最後に近年の河野通春が細川勝元によって伊予国守護に据えられ、河野家の家督を継いだ不慮の儀を嘆き、伊予国守護職と御恩地の返還を要求する主旨の申状を提出する。 | |
| 1,461 | 6 | 26 | 室町幕府が、小早川煕平に対し、越智郡大島の1/4の地頭職を返す。 | |
| ≈ | 1,461 | 9 | 大友親繁が、河野教通の要求を退け、豊後国臼杵荘(現在の大分県)の領知を認める様、室町幕府に訴える。 | |
| ≈ | 1,462 | 6 |
細川成之率いる軍が、河野通春征伐の為、渡海して東予から進軍する。同時に、南予の宇都宮安綱も北上した。圧倒的な兵力差を前に、河野は一旦湯築城(現在の愛媛県松山市道後公園)を捨て、以下の山間部や島嶼部に退却した。
①高縄山(現在の愛媛県松山市猿川) ②港山城(現在の愛媛県松山市港山) ③忽那諸島 ④来島(現在の愛媛県今治市来島小島) |
|
| 1,462 | 6 | 29 | 東寺公文浄総が、村上治部進の所務の様子を東寺の僧侶の永尊に知らせる。 | |
| ≈ | 1,462 | 11 | 河野教通率いる軍が、桜三里(現在の愛媛県東温市河之内周辺)付近にて、細川成之の軍勢に合流する。包囲網を敷かれ窮地に立たされた河野通春は、海賊衆に細川率いる軍の補給路を断たせ、難を逃れた。 | |
| 1,463 | 此の年、細川成之の被官達が伊予国に駐留し続けるも、河野通春に同情したり、細川の介入を嫌って河野方に寝返る地元の国人衆が続出した。 | |||
| 1,463 | 7 | 10 | 東寺雑掌が、村上治部進の弓削島荘所務職を認めていない小泉家や山路家を含む海賊が共謀し、押妨を行っていた為、此れを不当な所業であると非難し、室町幕府に押妨を止めさせ、弓削島荘等の所務職の確保を要請する。 | |
| 1,463 | 9 | 15 | 弓削島荘にて、定光寺観音堂(現在の愛媛県越智郡上島町弓削土生)が創建される。 | |
| 1,464 | 富樫泰高が隠居し、富樫成春の嫡男で泰高の大甥の富樫政親が家督を継ぐ。此れにより政親は、第15代加賀国守護(南半国守護)に就任した。 | |||
| 1,464 | 8 | 25 | 河野通秋が、忽那通賢に対し、忽那島(現在の愛媛県松山市野忽那)の東分検断職を安堵する。 | |
| 1,464 | 10 | 30 | 大内教弘が、善応寺(現在の愛媛県松山市善応寺甲)に禁制を掲げる。 | |
| 1,464 | 12 | 11 | 室町幕府が、相国寺の僧承勲を遣わせ、大内教弘に、河野通春征伐を命じる。 | |
| 1,464 | 12 | 23 | 足利義視が、実子の居ない足利義政に請われて還俗し、義政の後継者となる事が決定される。 | |
| 1,464 | 12 | 30 | 足利義視が還俗し、正親町三条実雅の今出川の屋敷に移住する。 | |
| 1,465 | 壬生晨照が官務に就任し、大宮長興から官務の地位を奪い返す。 | |||
| 1,465 | 3 | 13 |
以下2名が、土居家分の地頭職を善応寺に寄進する。 ①河野通春 ②河野通生 |
|
| 1,465 | 4 | 10 | 足利義視が、日野重子の旧邸である高倉殿を「今出川殿」と改め、移住する。 | |
| 1,465 | 5 | 13 | 室町幕府が、細川勝元等が河野通春征伐を申し出た事に関し、協議する。 | |
| ≈ | 1,465 | 7 |
室町幕府が、細川勝元の申し出を受け入れ、以下を始めとする近国の諸将に、河野通春征伐を命じる。 ①細川賢氏 ②細川成之 又此の頃、大内教弘率いる軍が伊予国に入り、河野を支援した。 |
|
| 1,465 | 8 | 17 |
足利義視が、以下2名の勧めにより、日野良子を正室に迎える。 ①足利義政 ②日野富子 |
|
| 1,465 | 9 | 15 | 細川勝元が、伊予国の在地領主である大野氏に、河野通春征伐を命じる。 | |
| 1,465 | 9 | 23 | 大内教弘が、興居島(現在の愛媛県松山市)にて病没する。 | |
| ≈ | 1,465 | 10 | 細川勝元方の兵が、伊予国に進軍し、河野通春率いる軍と交戦する。大内政弘方の兵も、河野の軍に加わっていた。河野は、大内教弘の援軍を受けて、細川方の兵を退けた。 | |
| 1,465 | 10 | 17 | 細川勝元が、河野通春征伐に関し、毛利豊元に支援を求める。 | |
| 1,465 | 10 | 29 | 細川勝元が、毛利豊元に、伊予国への出兵を促す。 | |
| 1,465 | 12 | 11 |
以下2名の間に足利義尚が生誕する。 ①足利義政 ②日野富子 義政は、足利義視を無理矢理還俗させて自身の猶子とし、次期征夷大将軍として据えて、細川勝元を執事として政務から離れる積もりであったが、義尚の誕生により、義尚を征夷大将軍にさせようとする富子と対立した。富子は、自身の兄日野勝光と結託し、幕政へ関与し始めた。 |
|
| 1,465 | 12 | 24 | 足利義政が、小早川元平に越智郡大島の1/4の地頭職等を安堵する。 | |
| ≈ | 1,466 | 1 | 伊勢貞親が、斯波義廉の守護職を罷免させるべく策動していた。 | |
| 1,466 | 3 | 21 | 三国湊(現在の福井県坂井市三国町山王付近)が内膳司領とされた事に関し、興福寺学侶・衆徒が訴える。 | |
| 1,466 | 5 | 14 | 此の時点で、後土御門天皇即位の際に壬生晴富に下賜される予定であった1村が、まだ壬生に下賜されていなかった。壬生は、今回仰せつけられなければ、窮困してどうしようもないと嘆いた。 | |
| 1,466 | 5 | 24 | 河野通生が、忽那通光に、忽那島の東分検断職を安堵する。 | |
| ≈ | 1,466 | 6 | 古市胤栄が、斯波義廉から所領を与えられる。 | |
| 1,466 | 10 | 15 | 第8代室町幕府征夷大将軍足利義政の独裁を支えていた幕府政所執事伊勢貞親が、足利義視を処刑すべきだと義政に進言する。此れは諸大名の猛反発を招き、伊勢は京を追われ、近江国、次いで伊勢国へ逃れた。対する義視は、山名持豊の屋敷に逃れ、細川勝元に無実を訴えた。 | |
| 1,466 | 12 | 9 | 河野教通が、忽那通光の恵良城(現在の愛媛県松山市上難波)に於ける戦功を賞する。 | |
| ≈ | 1,467 | 一条兼良の文庫である桃華坊文庫には、105kgもの文書が収められていた。 | ||
| 1,467 | 1 | 30 | 畠山義就が、自身の陣営に加わった山名宗全の支援の下、5,000名を率いて上洛する。其の後、大智院派の管領する千本地蔵院に滞在した。そして、相国寺(現在の京都府京都市上京区今出川通烏丸東入相国寺門前町)に布陣した。畠山は、第8代室町幕府征夷大将軍足利義政に圧力を掛けた。 | |
| 1,467 | 2 | 5 | 畠山政長が椀飯を務める。 | |
| 1,467 | 2 | 6 | 足利義政が、春日万里小路(現在の京都府京都市中京区坂本町・舟屋町付近)に所在する畠山政長の屋敷への御成を取り止め、花の御所(現在の京都府京都市上京区築山南半町付近)に畠山義就を招く。義就が足利に圧力を掛けた結果であった。山名宗全の支持を失った政長は、畠山家の家督を事実上奪われた。 | |
| 1,467 | 2 | 9 | 足利義政が、畠山政長の管領職を罷免し、春日万里小路の屋敷を畠山義就に明け渡す様命じる。政長は此れを拒否し、神保長誠等と共に自身の屋敷の防衛を強化した。同日足利は、山名宗全の屋敷の酒宴に出席し、義就が饗応した。足利は、義就・山名を支持する姿勢を示した。 | |
| 1,467 | 2 | 12 | 斯波義廉が第20代管領に就任する。 | |
| 1,467 | 2 | 12 | 室町幕府が、評定始を行う。 | |
| 1,467 | 2 | 15 | 山名宗全が椀飯を務める。 | |
| 1,467 | 2 | 19 |
以下2名が御所巻を画策する。 ①細川勝元 ②畠山政長 花の御所を包囲して威圧し、足利義政に畠山義就征伐の命令を出させる事を意図した。しかし、其の計画を細川の正室春林寺殿が山名宗全に漏らした為、以下が先に花の御所を制圧した。 ①山名 ②畠山義就 ③斯波義廉 そして、内裏から以下2名を迎え入れ、花の御所に避難させる事に成功した。 ①後花園上皇 ②第103代天皇後土御門天皇 |
|
| 1,467 | 2 | 21 | 足利義政が、畠山家の争いは畠山家同士で決着する様、畠山政長方・畠山義就方の双方に命じる。加えて、細川勝元に政長の援助の中止を命じた。細川は、義就による山名宗全の援助の中止を条件に承諾した。其の後細川は、武士の風上にも置けないとして批判された。山名達は、足利に対し政長・細川の追放を訴え、畠山家の争いは畠山家同士で決着する様命じられているにも拘らず、義就に加勢した。 | |
| 1,467 | 2 | 21 | 深夜、畠山政長が、春日万里小路の自身の屋敷を焼き払い、神保長誠の助言により、自身の一族や成身院光宣を含む2,000名の兵を率い、上御霊神社(現在の京都府京都市上京区上御霊前通烏丸東入上御霊竪町)に布陣する。 | |
| 1,467 | 2 | 22 |
早朝、畠山義就が兵3,000名余を率い、畠山政長の布陣する上御霊神社を襲撃する。以下3名も加勢した。 ①朝倉孝景 ②山名宗全 ③山名政豊(宗全の命により加勢) 細川勝元は此の段階では動かず、静観した。政長は持ち堪えられず、丸一日の合戦の末、上御霊神社の拝殿に放火し、細川の屋敷に退却した。足利義視は義就を支援し、細川は面目を失った。神保長誠は、其の後奮戦し、上杉定正に其の武勇を激賞された。 |
|
| 1,467 | 2 | 25 |
朝倉孝景が、在洛する以下2名を襲撃し、追放する。 ①斯波持種 ②持種の息子斯波義孝 |
|
| 1,467 | 3 | 2 | 政所内談始が行われる。 | |
| 1,467 | 3 | 28 | 足利義政への伺事が行われる。 | |
| 1,467 | 3 | 29 | 足利義視が、畠山政長・畠山義就両陣営に対し和睦を呼び掛ける。しかし失敗に終わった。 | |
| ≈ | 1,467 | 4 | 細川勝元が、土岐政康を第23代室町幕府伊勢国守護一色義直の統治する伊勢国へ派遣する。 | |
| 1,467 | 4 | 7 | 節句であった此の日、山名宗全を始めとする諸大名が花の御所に参賀する。しかし、細川勝元は欠席した。諸大名は、細川が戦をする積もりなのだと悟った。 | |
| ≈ | 1,467 | 5 | 細川勝元方の兵が、山名宗全方の年貢米を略奪する事件を相次いで起こす。更に細川方の兵は、宇治川や淀川等の各地の橋を焼き、四門を固めた。 | |
| ≈ | 1,467 | 5 |
山名方の分国から京進される年貢を、細川方が以下の国で没収する。 ①丹波国 ②丹後国 |
|
| ≈ | 1,467 | 5 | 少弐教頼が、対馬の宗氏勢力等を動員し、大内政弘領である筑前国に侵攻する。 | |
| ≈ | 1,467 | 5 |
箱崎津(現在の福岡県福岡市東区箱崎)寄住の以下2名が、朝鮮人漂流民を送還する為に朝鮮に使いを出す。 ①藤原安直 ②藤原直吉 |
|
| 1,467 | 5 | 30 | 大内政弘が、自身の味方の武士が箱崎津に到着した事を記す。此の頃の遣明船は大量の朝貢品・貿易品を調達する必要が有り、箱崎には重要貿易品であった硫黄が保管されていた。 | |
| ≈ | 1,467 | 6 | 細川勝元が、斯波義敏を第17代室町幕府越前国守護斯波義廉が統治する越前国へ派遣する。義敏は、義廉方を圧迫した。 | |
| ≈ | 1,467 | 6 | 細川勝元が、赤松政則の家臣宇野政秀を播磨国へ派遣する。赤松は、赤松家の旧領であった播磨国・備前国・美作国に侵攻させた。旧領だった事もあり、旧臣・牢人・寺社・百姓・土民が協力し、数日で旧領を奪回した。 | |
| ≈ | 1,467 | 6 |
細川勝元が、諸大名に上洛を要請する。畠山政長等が参集した。斯うして、細川の屋敷と花の御所を中心とした京都北部から東に布陣した細川方と、堀川西岸に建てられた山名宗全の屋敷と京都中央に位置する斯波義廉の屋敷を拠点とする山名方の構図がはっきりし、前者が東軍、後者が西軍と呼称された。其々以下の陣容であった。 ①東軍 ❶細川 ❷足利義視 ❸政長 ❹斯波義敏 ❺武田信繁の弐男武田信賢 ❻成身院光宣 ❼細川勝久 ❽京極持清 ❾赤松政則 ❿富樫政親 ②西軍 ❶山名宗全 ❷足利義尚 ❸畠山義就 ❹斯波義廉 ❺一色義直 ❻朝倉孝景 ❼甲斐敏光 ❽六角高頼 ❾土岐成頼 |
|
| ≈ | 1,467 | 6 | 一色義直が、武田信賢との確執及び若狭国・三河国を復旧する目的から西軍に与した為、丹後国守護職・伊勢国守護職を罷免される。 | |
| ≈ | 1,467 | 6 | 山名宗全が、大内政弘に出陣を要請する。 | |
| 1,467 | 6 | 4 |
領地を巡って相論を起こしていた以下2名が、担当奉行を通じて足利義政に証文等を提出する。 ①訴人:壬生晨照(担当奉行:諏訪忠郷) ②論人:大宮長興(担当奉行:飯尾貞有) |
|
| 1,467 | 6 | 5 | 前日の諏訪忠郷の提出した証文に理が有ると考えた飯尾貞有が、余酔と称し、花の御所での証文提出を欠席する。 | |
| 1,467 | 6 | 8 | 飯尾貞有が、足利義政に大宮長興の証文を提出する。しかし足利は、飯尾の対応を不快とし、壬生晨照の支証に分が有るとして、壬生方の勝訴の裁許を下した。 | |
| 1,467 | 6 | 10 | 2日前の裁許により、足利義政による御判御教書の発給が決定される。此の当時、斯波義廉が西軍に属していた為、御判御教書の発給に難渋し、前年から発給されていなかった。管領を介さず、御判奉行伊勢貞藤に直接下される事となった。 | |
| 1,467 | 6 | 11 |
大内政弘が、周防国・長門国を始めとする8ヶ国の数万の兵を率い、山口を出発する。以下2名も此の中に居た。 ①河野通春 ②陶弘房 弘房は、家の事は陶弘護に任せていた。大内の本隊は海路で、以下を経由して瀬戸内海を東上した。 ①野上(現在の山口県周南市) ②柳井(現在の山口県) ③屋代島(現在の山口県大島郡周防大島町) ④室津(現在の兵庫県たつの市) |
|
| 1,467 | 6 | 14 | 足利義政による御判御教書が発給される。広慶院が日野富子に口添えを依頼し、日野が諏方忠郷に言い付け、発給に至った。 | |
| 1,467 | 6 | 21 | 山名宗全が評定を開き、五辻通大宮東(現在の京都府京都市上京区観世町)に本陣を置く。そして軍勢を招集した。 | |
| 1,467 | 6 | 22 | 若狭国小浜の一色義直の勢力を駆逐していた武田信賢が上洛する。 | |
| 1,467 | 6 | 22 | 越前国の斯波義敏が攻め入ったとの報告を受け、斯波義廉が困惑する。 | |
| 1,467 | 6 | 27 | 夜明け前、花の御所の隣の一色義直の屋敷を襲撃する事を意図し、武田信賢が花の御所と山名宗全の屋敷の中間に位置する実相院(現在の京都府京都市上京区実相院町)を、成身院光宣が実相院に近接し一色の屋敷に隣接する土倉正実坊を其々占拠する。そして夜明け頃、武田・成身院等が、足利義政を味方に付ける事を意図し、一色の屋敷を襲撃し占拠した。一色は直前に脱出したものの屋敷は焼き払われた。此れが成功し、細川勝元は、戦火から保護するという名目で花の御所を占拠して足利義政を保護し、自身の屋敷に本陣を置いた。斯うして東軍は、西軍征伐の大義名分を得た。西軍は、実相院・正実坊の奪還を試みたが、東軍の反撃により失敗し、山名の屋敷付近まで退却した。 | |
| 1,467 | 6 | 27 |
東軍と西軍が、一条大宮(現在の京都府京都市上京区下石橋南半町)にて市街戦を繰り広げる。そんな中、西軍は山名宗全の屋敷近くの細川勝久の屋敷に目を付け、斯波義廉が、朝倉孝景・甲斐敏光を引き連れて細川の屋敷へ向かった。此れに対し東軍は、京極持清が細川の救援に向かい、一条通を西進して斯波率いる軍を襲撃した。しかし、朝倉の反撃に遭って敗走した。其の後赤松政則が、一条通を南下し、正親町通(現在の京都府京都市上京区の中立売通)を進んで迂回して斯波率いる軍を襲撃した。疲弊していた斯波達は退却した。自邸で抵抗していた細川は、此れを焼き払って退却し、第8代室町幕府阿波国守護細川成之の屋敷に逃げ込んだ。戦闘は翌日の18時迄続いた。最終的に以下や民家等が焼失した。 ①行願寺(現在の京都府京都市中京区寺町通竹屋町上ル行願寺門前町) ②知恩寺(現在の京都府京都市左京区田中門前町) |
|
| 1,467 | 6 | 27 |
山名宗全が、分国の兵を招集し、以下が呼応する。 ①垣屋氏 ②田結庄氏 ③八木氏 |
|
| 1,467 | 6 | 28 |
此の日から翌日に掛けて、以下の人間等の屋敷が炎上する。 ①細川勝久(屋敷は現在の京都府京都市下京区富小路通四条下る徳正寺町の徳正寺に所在) ②細川教春 ③第8代室町幕府淡路国守護細川成春 |
|
| 1,467 | 6 | 29 | 足利義政が両軍に対し、停戦して和睦する様命じる。此れにより両者痛み分けとなったものの、足利と花の御所を押さえた東軍が優位となった状態で停戦となった。 | |
| ≈ | 1,467 | 7 | 伊勢貞親が、足利義政に呼び戻され、伊勢国から上洛する。此れにより足利義視は孤立した。 | |
| ≈ | 1,467 | 7 | 足利義視が、牙旗を下され東軍の主将となる。足利は、東軍から山名家の縁者を追放し、東軍と通じた奉行衆を殺害した。 | |
| ≈ | 1,467 | 7 | 古市胤栄が上洛する。西軍に属した。 | |
| 1,467 | 7 | 4 | 足利義政が、細川勝元に足利将軍旗を与える。 | |
| 1,467 | 7 | 8 | 祇園会が中止となる。 | |
| 1,467 | 7 | 12 | 飯尾為数が、西軍に通じたとして、足利義視に暗殺される。又同日、両軍の間で戦闘が発生し、上京の多くが焼失した。 | |
| 1,467 | 7 | 14 | 武田氏被官白井備中守が討死する。 | |
| 1,467 | 7 | 14 | 斯波義廉が、東軍への降参条件として、朝倉孝景の首級を要求する。 | |
| 1,467 | 7 | 15 | 武田信賢率いる軍が、二条通(現在の京都府京都市中京区)に下る途上、朝倉孝景勢の待ち伏せに遭い、約80名が討ち取られる。 | |
| 1,467 | 7 | 15 |
後花園上皇が、以下の内容の書簡を伏見宮貞常親王に送り、出家の意思を伝える。 此度の戦は、時の流れとはいえ、只々驚いています。出家は私の本望ではありましたが、在位中は其れを忍んでいました。後土御門天皇の御代の始めの儀式を執り行う事が出来ました。今となると、俗世への執心等無い所に、此の様な大乱が起こり、いよいよ世俗との関わりを断とうと思いまして、出家の本意を遂げようという心境です。後土御門天皇の始めに此の様な事が起こってしまい、只々恥入っております。出家の意思が万が一漏れた場合、武家が止めるでしょう。そうなっては口惜しい事です。無上菩提の妨げにならない様、呉々も内密に進めて下さい。 |
|
| 1,467 | 7 | 23 | 西軍が金閣寺に布陣する。 | |
| 1,467 | 8 | 2 | 武田信賢率いる軍が、斯波義廉の屋敷を襲撃する。しかし退却した。 | |
| 1,467 | 8 | 5 |
後花園上皇が、以下2名を室町幕府に遣わせ、停戦を要請する。 ①伏見宮貞常親王 ②第85代関白一条兼良 しかし、細川勝元は無視した。 |
|
| 1,467 | 8 | 8 |
後花園上皇が、以下2名を室町幕府に遣わせ、再度停戦を要請する。 ①足利満詮の息子義賢 ②正親町三条実雅 |
|
| 1,467 | 8 | 10 | 武田信賢率いる軍が、斯波義廉の屋敷を襲撃する。しかし数名が朝倉孝景勢に討たれた。 | |
| 1,467 | 8 | 19 |
大内政弘率いる軍が、20,000〜30,000名の軍勢で播磨国兵庫津(現在の兵庫県神戸市兵庫区)に入る。此の内2,000〜3,000名は河野通春が率いていた。細川勝元は、以下2名に花の御所への動座を求めた。 ①後花園上皇 ②後土御門天皇 |
|
| ≈ | 1,467 | 9 | 細川勝元等が、伊勢貞藤が西軍に与したとして室町幕府から追放する。 | |
| 1,467 | 9 | 5 | 大内政弘が、尼崎にて、若衆が敵対した為、焼き討ちにして現地住民を殺害する。 | |
| 1,467 | 9 | 8 |
大内政弘が、河野水軍・村上水軍・三島水軍等の瀬戸内水軍を率い、大物浦の以下の場所にて、上陸を阻止しようとする細川勝元・赤松政則の軍と交戦し、撃破する。 ①難波(現在の兵庫県尼崎市西本町付近) ②水堂(現在の兵庫県尼崎市立花町付近) 此の戦闘により、河野通春等は戦功を挙げた。其の後大内率いる軍は、尼崎を焼き払い、10,000名の兵と2,000隻の船団と共に上洛し、東寺に布陣した。そして後に焼失した梶井門跡(現在の京都府京都市北区紫野下築山町付近)に移り本陣とした。其の後大内達は、兵站基地や大輪田泊(現在の兵庫県神戸市兵庫区)で激しい攻防を展開し、軈て戦線は、摂津国・丹波国・近江国の周辺諸国へと移っていった。通春と河野教通の兄河野通生は、摂津国へ向かった。 |
|
| 1,467 | 9 | 8 | 夜、足利義視が出発する。足利義政が伊勢貞親を呼び戻した事が切っ掛けであった。此の行動に失望した義政は、後継者を足利義尚とする事を検討し始めた。 | |
| 1,467 | 9 | 20 | 西軍が下京に火を放つ。 | |
| 1,467 | 9 | 20 | 大内政弘率いる軍が、東寺に布陣する。 | |
| 1,467 | 9 | 20 | 陶弘護が、龍文寺(現在の山口県周南市長穂門前)にて、第3世龍文寺住職器之為璠より受衣し、法名を「孝勲」、号を「忠建」と称す。 | |
| 1,467 | 9 | 20 |
河野教通が、忽那通光に、恵良城での勲功の賞として、以下2ヶ所の所領を与える。 ①出作(現在の愛媛県伊予郡松前町) ②鹿子 |
|
| 1,467 | 9 | 21 | 足利義視が、伊勢国国司木造教親の陣所の中山殿に入る。木造は足利に「北畠教具を頼りなさい」と助言した。足利は、軍事力・経済力を保持していながら、幕政には不干渉で中立の立場を取り、和歌等の貴族的文化を持っていた北畠に惹かれ、伊勢国への逃亡を決意した。其の後足利は、木造に警護され、武者小路通(現在の京都府京都市上京区)を東へ向かい、蛸薬師通(現在の京都府京都市中京区)を経由して一条通(現在の京都府京都市右京区)へ向かった。釘貫門は、東軍の富樫政親の兵が守っていたが、木造は「三条公敦殿は病気で東山に居り、足利殿が見舞いに参るのである。開門せよ」という主旨の発言をした。しかし富樫は不審がって開けず「鍵が無い」と答えた為、木造は、予てから準備していた合鍵で開門した。そして足利は、近江国坂本(現在の滋賀県大津市坂本・坂本本町・下阪本)に入り、石川次郎の館にて、お忍びで来ていた日野富子と暇乞いをし、北条早雲を伴って伊賀国を経由し、伊勢国に入った。 | |
| 1,467 | 9 | 21 | 大内政弘が上洛する。此れにより、畠山義就を始めとする西軍は勢い付いた。 | |
| 1,467 | 9 | 29 | 武田信賢率いる軍が、等持院(現在の京都府京都市北区等持院北町)に布陣する畠山義就勢に矢を射掛ける。しかし反撃に遭い、退却するも途中で討たれ、三宝院(現在の京都府京都市伏見区醍醐東大路町)に駆け込んだ。畠山は追撃し、三宝院を攻めた。武田信繁の四男武田元綱が奮戦したものの、東軍は敗れ、畠山によって三宝院に火を放たれ、落とされた。斯うして東軍は、京都の東北部の隅に封じ込められた形となり、追い込まれた。 | |
| 1,467 | 10 | 4 |
北畠教具が、足利義視を保護する為に長谷寺(現在の奈良県桜井市初瀬)を出発する。そして以下2名を迎え、伊勢国丹生(現在の三重県多気郡多気町)に屋敷を造り、逗留させた。 ①足利 ②北条早雲 此の際武田信賢は、足利義稙を守り、西軍に送り届けた。 |
|
| 1,467 | 10 | 4 | 足利義政が、畠山義就に停戦勧告を行う。しかし畠山は耳を貸さなかった。 | |
| 1,467 | 10 | 11 |
畠山義就率いる軍が、土御門内裏(現在の京都府京都市上京区元浄花院町付近)を占拠する。西暦1,467年9月29日から同日迄の戦いで、以下を含む公家の屋敷37戸、 ①近衛殿 ②鷹司殿 ③日野殿 ④花山院殿 ⑤広橋殿 ⑥西園寺殿 及び、以下を含む大名の屋敷や奉行衆の宿所80戸が焼失した。 ①吉良氏 ②大館氏 ③細川教春 ④飯尾之種 此れにより、下京の大半は西軍が制圧した形となった。 |
|
| 1,467 | 10 | 11 | 山名宗全率いる軍が、細川勝元の屋敷を襲撃する。 | |
| 1,467 | 10 | 12 |
以下2名が上洛する。 ①細川勝元の家臣秋庭元明 ②赤松政則の家臣浦上則宗 秋庭・浦上は、細川の命により大内政弘率いる軍と摂津国で交戦したものの撤退し、大内の後を追っての上洛であった。しかし、此の時点で下京の大半が西軍に占拠されていた為、東寺を経由して東に迂回した。 |
|
| 1,467 | 10 | 14 | 武田信賢率いる軍が、畠山義就勢と交戦する。武田側は24名の首が取られた。 | |
| 1,467 | 10 | 14 |
以下2名が南禅寺(現在の京都府京都市左京区南禅寺福地町)に布陣する。しかし此れが西軍に察知された。 ①秋庭元明 ②浦上則宗 |
|
| 1,467 | 10 | 16 |
早朝、東軍本体と連絡が取れずに孤立していた以下2名の布陣していた南禅寺山(現在の京都府京都市左京区南禅寺南禅寺山町付近)に、大内政弘率いる軍が攻撃を開始する。 ①秋庭元明 ②浦上則宗 此の戦いにより、以下が灰燼に帰した。 ①南禅寺 ②青蓮院(現在の京都府京都市東山区粟田口三条坊町) 秋庭・浦上の陣は、俄仕立てで防御も不十分であったが、摂津国での雪辱に燃え、大石等を投げ落として防戦し、大内率いる軍を退けた。次に、山名宗全率いる軍が日ノ岡(現在の京都府京都市山科区)から攻め上ったが、大石等を投げ落とされ、退けられた。三番手として、遊佐氏・誉田氏が山科から攻め上った。しかし東軍が木々の間や岩陰から矢の雨を浴びせ、此れを退けた。次に、四番手として甲斐氏・朝倉孝景が如意ヶ嶽から下って攻め込んだが、谷が深く充分な戦闘が行えない中、石礫を浴びて退却した。 |
|
| 1,467 | 10 | 18 | 後花園上皇が、花の御所にて出家する。其の後室町幕府は、後花園上皇に対し、西軍征伐の綸旨の発給を求めるも、後花園上皇は断固として拒否した。 | |
| 1,467 | 10 | 29 | 武田信賢が、勝定院(現在の京都府京都市下京区七条御所ノ内本町)の陣所を畠山義就率いる軍に攻められ、退却する。 | |
| 1,467 | 10 | 29 |
南禅寺山を攻めていた西軍が、攻撃を止めて洛中に戻る。以下2名は其の隙に北へ迂回して、吉田山(現在の京都府京都市左京区吉田神楽岡町)・上御霊神社を経由して東軍本陣と合流した。 ①秋庭元明 ②浦上則宗 以下2名は、其々の家臣と再会出来た事を喜んだものの、東軍の戦況は厳しく、花の御所や其れに隣接する相国寺・細川勝元の屋敷等の上京の拠点に押し込められた。 ①細川勝元 ②赤松政則 |
|
| 1,467 | 10 | 30 |
以下の人間が率いる西軍30,000名程度の軍勢が、朝倉孝景等と合流し、烏丸小路(現在の京都府京都市の烏丸通)・東洞院通・高倉通を経由して、相国寺及び其の周辺を襲撃する。 ①畠山義就 ②畠山義統 ③大内政弘 ④一色義直 ⑤土岐成頼 ⑥六角高頼 対する東軍は、相国寺にて立て籠もって、以下の人間が率いる3,000騎が迎え撃った。 ①細川勝元の猶子細川勝之 ②細川勝元の重臣安富元綱 ③武田信繁の参男武田国信 三条坊門殿は、以下2名が500騎余で守備していた。 ①伊勢国の住人関民部少輔 ②備前国の住人松田次郎左衛門尉 しかし、西軍の猛攻の前に直ぐに敗れ、松田は討たれ、関は相国寺に退却した。軈て、西軍に内通した相国寺の僧が、相国寺に火を放つと、高倉殿を守備していた武田信賢と、足利義政邸である烏丸殿を守備していた京極持清は、西軍が相国寺を攻め落としたと思い込み、出雲路(現在の京都府京都市北区出雲路立テ本町)に退却した。火の手を見た西軍は、一斉に相国寺に突入した。相国寺を破られたら隣は花の御所という後が無い東軍は、総力を挙げて白兵戦を展開した。以下3名は、配下500名と馬廻だけで総門を固め、石橋から攻め入る大軍を迎え撃って7度退けたが、東門から西軍が再度攻め込んだ為、東門へ向かい、其処で配下の兵と共に戦死した。 ①勝之 ②元綱 ③元綱の弟安富盛継 次に、大内・土岐が総門を攻め立てた。しかし、浦上則宗等の奮戦により、大内の花の御所侵入は阻止された。其処で、大内率いる軍は、相国寺仏殿の焼け跡から攻め込んだが、以下2名等が防戦し、西軍の侵入を阻止した。 ①国信 ②赤松政則 しかし東軍は、相国寺を放棄せざるを得なくなった。其の後、時雨が降り、火や煙が少し収まった頃、朝倉・大内が相国寺に陣取り、攻め口が無く戦闘に参加出来なかった一色・六角も此れに続き、相国寺一帯は30,000名の西軍の軍勢に押さえられた。西軍は、討ち取った首級を8輌もの車に載せ、意気揚々と自陣に帰還した。一方足利義政は、日野富子に避難を勧められるも聞かず、いつも通り酒宴に興じていた。 |
|
| 1,467 | 10 | 30 | 後花園上皇が、両軍和睦の為、天下静謐の祈りを神仏に捧げよという主旨の院宣を寺社に発給する。更に後花園上皇は、両軍に勅使を派遣し、和平せよと命じた。しかし細川勝元は、天下静謐とは山名宗全を討つ事であるとし、自軍を鼓舞した。 | |
| 1,467 | 10 | 31 | 畠山政長が、東軍の危機的状況を打開すべく、4,000名の兵を率い、花の御所の四足門から出撃する。四足門に面した室町通を上り、東へ向かい、相国寺の塔頭の1つである普廣院の焼け跡から西軍に突撃した。細川勝元からの援軍を東からの横槍として投入し、西軍は混乱状態に陥り、6,000名が討たれ、撤退した。特に、一色義直の兵が、相国寺内の蓮池の側で多数の戦死者を出した。西軍は、此れ以上攻めるとなると、花の御所が戦場となる事から、諸将が躊躇い、戦意が低かった事が敗因であった。斯うして畠山は相国寺を掌握したが、其の後朝倉孝景率いる軍が相国寺を奪還した。西軍は相国寺を占拠したものの東軍を攻め切れず、決着の付かない儘戦闘は終了した。前日と併せて、相国寺での戦いは双方に甚大な被害を齎した。 | |
| 1,467 | 11 | 13 | 六角高頼が、馬淵(現在の滋賀県近江八幡市)にて六角政堯と交戦する。 | |
| 1,467 | 12 | 31 |
朝廷が、西軍に与した以下の公家等の官爵剥奪を決定する。 ①正親町三条公治 ②葉室教忠 ③教忠の息子葉室光忠 ④阿野季遠 ⑤清水谷実久 此の公家達は、日野家と対立していた三条家の一族や縁者が多く含まれていた。 |
|
| 1,468 | 野田泰忠が、京都から出て行く西軍を攻撃する為、上植野城(現在の京都府向日市上植野町北小路)に布陣する。 | |||
| 1,468 | 小早川弘景が沼田荘高山城(現在の広島県三原市高坂町)を攻撃する。 | |||
| ≈ | 1,468 | 1 | 播磨国を統治していた宇野政秀が、諸役免除等の文書を発給する。 | |
| ≈ | 1,468 | 1 |
此の時点で、九州の諸国は以下の状態であった。 ①豊前国:大内氏が支配(大友氏が申し請うていた) ②筑前国:少弐氏が支配(大友氏が狙っていた) ③筑後国:菊池氏が支配(大友氏が狙っていた) ④肥前国西部:平戸氏が支配 ⑤肥前国東部:千葉氏が支配 |
|
| ≈ | 1,468 | 1 |
河野教通等が、以下2ヶ所に禁制を掲げる。 ①三島神社(現在の愛媛県今治市大三島町宮浦の大山祇神社) ②善応寺 |
|
| 1,468 | 1 | 8 | 京極持清が、六角高頼方の高野瀬城(現在の滋賀県犬上郡豊郷町高野瀬)を落城させる。 | |
| 1,468 | 1 | 17 | 河野通春が、摂津国を進発するに当たり、東寺に祈祷を依頼する。 | |
| 1,468 | 1 | 24 |
以下が放火により焼失する。 ①建仁寺塔頭 ②八坂神社の多宝塔・大門 |
|
| ≈ | 1,468 | 2 | 大内政弘が、分国からの援軍を得て摂津国一帯を荒らし、西軍摂津国守護として、摂津国欠郡(住吉郡(現在の大阪府大阪市)・東生郡(現在の大阪府大阪市))を拠点として、軍事的占領を行う。 | |
| ≈ | 1,468 | 4 | 初代古河公方足利成氏と西軍諸将の間で攻守同盟が締結される。足利義視が此れを承認した。 | |
| ≈ | 1,468 | 4 | 細川勝元に金品によって勧誘され、東軍に属していた、侍所所司代多賀高忠配下の目付の骨皮道賢が、300名余の足軽を率い、下京の焼き討ち作戦の為出陣する。稲荷山(現在の京都府京都市伏見区稲荷山官有地)の伏見稲荷大社(現在の京都府京都市伏見区深草藪之内町)に布陣した。稲荷山の在る京都南部は貧困街であった。 | |
| 1,468 | 4 | 9 |
烏丸通・北大路通(現在の京都府京都市北区小山上総町付近)にて、大内政弘と、東軍の以下2名が交戦する。 ①毛利豊元 ②小早川煕平 |
|
| 1,468 | 4 | 10 | 骨皮道賢率いる軍が、七条を放火する。 | |
| 1,468 | 4 | 13 |
朝倉孝景率いる軍が、以下2名が布陣する醍醐(現在の京都府京都市伏見区醍醐東大路町付近)・山科を襲撃する。 ①赤松政則 ②武田信賢 赤松・武田は退却した。 |
|
| 1,468 | 4 | 13 |
以下の人間が率いる30,000名の軍が、骨皮道賢の布陣していた稲荷山を包囲し、襲撃する。 ①山名宗全 ②斯波義廉 ③朝倉孝景 ④畠山義就 ⑤大内政弘 多勢に無勢で、敗北を悟った骨皮は、女装して板輿に乗り、逃走を図った。しかし見破られ、朝倉が骨皮を斬首し、稲荷山に火を放った。骨皮の首級は三条河原(現在の京都府京都市中京区大橋町)に梟首され、以下の落首が張り出された。 昨日まで稲荷廻し道賢を今日骨皮と成すぞかはゆき (昨日まで稲荷山で威張り散らして暴れ廻っていた道賢が、今日は骨と皮になって殺されてしまった。折角女装までして可愛かったのに、お気の毒様) かはゆきは「哀れ」「可愛い」の2つの意味が掛かっている。 |
|
| ≈ | 1,468 | 4 | 17 |
京極持清の嫡男京極勝秀が、六角高頼の居城である観音寺城(現在の滋賀県近江八幡市安土町石寺)を襲撃する。此の時以下2名は京都に居り、代わりに留守居役の家老伊庭行隆が迎撃した。 ①六角 ②六角の陣代山内政綱 |
| 1,468 | 4 | 23 | 伊庭行隆が、観音寺城を開城する。 | |
| ≈ | 1,468 | 4 | 23 | 京極勝秀が甲賀郡に侵攻し、六角高頼方の小佐治為重を攻撃する。 |
| 1,468 | 5 | 2 | 丹波国宮田荘(現在の兵庫県丹波篠山市)に就いて、此れ迄通り知行を認めるとの足利義政の御内書が下される。此れは、依頼を受けた女中で摂津満親の娘の春日局による訴訟が以前から行われていた為である。 | |
| 1,468 | 5 | 18 | 六角高頼方の山内政綱が、六角政尭が築城させた長光寺城(現在の滋賀県近江八幡市長光寺町)を落城させる。 | |
| 1,468 | 6 | 3 |
松田貞頼を始めとする15名が、布施貞基に対し、以下の内容の意見状が御前沙汰にて発給される。 近年、御判神領に就いて、本来の領主が訴訟を起こし、返還されるべきかどうかが争われています。訴状を精査したところ、道理に基づいて判断するならば、仮令神領であっても、元々一般の者に返還された前例が有るのかどうかが問題となります。もし其の様な前例が有るのであれば、証文の内容に従い、正しく裁定すべきです。 |
|
| 1,468 | 6 | 12 | 斯波義敏の軍勢が、朝倉孝景勢を越前国から追い出す。 | |
| 1,468 | 6 | 24 |
大沢重胤が以下の主旨の内容を記す。 私は公用で京都に居り、各地に散在する田地に就いて、義賢を通じて公方に申し上げるべき事である。此れを心得ておく様にとの旨を、新兵衛督局に対し、山科言国の書簡によって申し伝えた。近頃は大小の案件を問わず特に問題は無いが、もし何か申し上げるべき事が有れば、速やかに言上する様にとの事である。広橋綱光・飯尾之種・飯尾為信が申し上げた。 |
|
| ≈ | 1,468 | 7 | 六角高頼に代わり、六角政堯が第19代室町幕府近江国守護に就任する。 | |
| 1,468 | 7 | 6 | 京極勝秀が病死する。 | |
| ≈ | 1,468 | 7 | 23 | 武田信賢勢が、吉田神社(現在の京都府京都市左京区吉田神楽岡町)に兵を展開する。 |
| 1,468 | 7 | 23 |
西軍が以下等に火を放つ。 ①吉田神社 ②浄蓮華院(現在の京都府京都市伏見区深草鞍ケ谷) ③吉田村(現在の京都府京都市左京区) |
|
| 1,468 | 8 | 21 | 西軍が、青蓮院・民家を焼失させる。 | |
| 1,468 | 8 | 22 |
西軍が以下を焼失させる。 ①聖護院(現在の京都府京都市左京区聖護院中町) ②法勝寺(現在の京都府京都市左京区岡崎法勝寺町) |
|
| 1,468 | 8 | 23 | 若狭武田氏被官逸見繁経率いる軍が、東山に出陣する。 | |
| 1,468 | 8 | 24 | 西軍が清閑寺(現在の京都府京都市東山区清閑寺歌ノ中山町)を破壊する。 | |
| 1,468 | 8 | 30 | 光明峯寺(現在の京都府京都市東山区今熊野南谷町)が焼失する。 | |
| 1,468 | 8 | 31 | 逸見繁経率いる軍が、山科郷・勧修寺(現在の京都府京都市山科区勧修寺仁王堂町)から深草(現在の京都府京都市伏見区)に掛けてを襲撃する。 | |
| ≈ | 1,468 | 9 | 丹後国の西軍が嵯峨に布陣する。 | |
| 1,468 | 9 | 10 | 西軍が上御霊神社を焼失させる。 | |
| 1,468 | 9 | 12 |
東軍が以下を焼失させる。 ①泉涌寺(現在の京都府京都市東山区泉涌寺山内町) ②妙法院(現在の京都府京都市東山区妙法院前側町) |
|
| 1,468 | 9 | 19 | 伊勢貞親が朝倉孝景に対し、東軍に勧誘する書簡を送る。此の書簡を読んだ朝倉は、目を疑った。以降足利義政は、細川勝元と共に、西軍勢力の切り崩し工作を行なった。 | |
| 1,468 | 9 | 20 | 東軍が仁和寺を焼失させる。 | |
| 1,468 | 9 | 23 |
西軍が大覚寺(現在の京都府京都市右京区嵯峨大沢町)と民家を焼失させる。又同日、以下の寺も焼失した。 ①天龍寺(現在の京都府京都市右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町) ②臨川寺(現在の京都府京都市右京区嵯峨天龍寺造路町) ③宝幢寺(現在の京都府京都市左京区上高野釜土町) |
|
| ≈ | 1,468 | 10 | 丹波国の東軍が、丹後国に侵入し、西軍を破る。 | |
| 1,468 | 10 | 8 | 足利義視が、足利義政の説得により帰洛する。しかし北条早雲は其の儘伊勢国に留まり、其の後、招聘を受けていた自身の妹北川殿の夫である今川義忠の下へ行った。其の後義視は、義政に対し、西軍との講和を望んでいた日野富子の兄日野勝光の排斥を訴えた。しかし義政は聞き入れず、細川勝元も、義視の訴えに懸念を示した。 | |
| 1,468 | 10 | 18 | 六角高頼の重臣で陣代の山内政綱が、弓削(現在の滋賀県蒲生郡竜王町)にて、細川勝元方の三井信高を討ち取る。 | |
| ≈ | 1,468 | 11 | 足利義政が、伊勢貞親を幕政に復帰させる。此れにより、義政と足利義視は対立した。 | |
| ≈ | 1,468 | 11 |
細川勝元が、大内政弘の分国及び与力の知行の在所を打ち取り次第、注進によって充て行う旨のお触れを出す。大友親繁・大友政親父子は、以下の国に侵攻を開始した。 ①豊前国 ②筑前国 ③肥前国 又足利義政は親繁に、以下の国にも侵入する様命じた。 ①長門国 ②周防国 |
|
| 1,468 | 11 | 6 | 野田泰忠率いる山城国西岡(現在の京都府乙訓郡大山崎町)の被官衆が、寺戸城(現在の京都府向日市寺戸町古城)に布陣し、鶏冠井城(現在の京都府向日市鶏冠井町御屋敷)を攻撃する。 | |
| 1,468 | 11 | 28 |
斯波義敏が越前国を略掌握し、斯波義廉が苦境に立たされる中、東軍の働き掛けにより、朝倉孝景が、自身の嫡男朝倉氏景と配下の兵を京都に残し、以下の自身の弟3名と共に、越前国へ下向する。 ①朝倉経景 ②朝倉景冬 ③朝倉光玖 此れは義敏に反撃する為と周囲は理解していた。 |
|
| ≈ | 1,468 | 12 |
河野通春が、河野教通に以下の主旨の書簡を送る。 応仁の乱は延々と続くと思いますが、西軍へご同心頂けるのでしょうか。先年大内方からも依頼が有った筈ですが、其の後お返事を頂いておりません。足利義政殿・足利義視殿の双方が将軍となられた今、其の命令には変わりはありません。此度の摂津国の合戦により、私は守護に補任されましたが、家名を上げる上では、私と教通殿の何方がなっても同じだと思います。 |
|
| 1,468 | 12 | 13 |
弓削にて、信濃守が討死し、三沢彦四郎に太刀一振が与えられる。此の戦いに於いて、六角高頼方の山内政綱に敗れた以下2名は、軍備を整えた。 ①京極持清 ②六角政堯 此の戦いで以下が全焼した。 ①瑞光寺(現在の滋賀県蒲生郡竜王町弓削) ②七堂伽藍 |
|
| 1,468 | 12 | 14 | 山内政綱が近江国に帰国する。そして、観音寺城の防備を固めた。 | |
| 1,468 | 12 | 18 |
以下2名が、六角高頼方の守山城(現在の滋賀県守山市守山)を落城させる。 ①京極持清 ②六角政堯 |
|
| ≈ | 1,468 | 12 | 六角政堯方が、垣見(現在の滋賀県東近江市)にて、六角高頼方を破る。 | |
| 1,468 | 12 | 21 |
以下2名率いる軍が観音寺城へ侵攻する。 ①京極持清 ②六角政堯 山内政綱は持ち堪える事が出来ず、火を放って敗走した。 |
|
| 1,468 | 12 | 23 | 足利義視に仕えていた有馬元家が、足利義政の命を受けた赤松政則によって殺害される。 | |
| 1,468 | 12 | 26 | 有馬元家が殺害された事で身の危険を感じた足利義視が、延暦寺へ向けて逃走する。 | |
| 1,469 | 大友親繁が、第12代室町幕府筑後国守護に就任する。豊後国守護職との兼任となった。 | |||
| 1,465 | ||||
| ≈ | 1,469 | 1 | 後花園上皇が、足利義視征伐の為、東軍に治罰の院宣を発給する。此れを受けて足利義政は、自軍に足利義視征伐を命じた。 | |
| ≈ | 1,469 | 1 | 足利義政が、御料所である丹後国与謝郡(現在の京都府与謝郡伊根町・与謝野町、現在の京都府宮津市・京丹後市・福知山市)の分郡守護に摂津之親を任じる。此れにより摂津は、第19代室町幕府丹後国守護に就任した。又、間人(現在の京都府京丹後市丹後町)の門四郎家国が、李氏朝鮮に派遣された。 | |
| 1,469 | 1 | 5 | 西軍が、比叡山に使いを出して足利義視を迎え入れる。 | |
| 1,469 | 1 | 6 | 陶弘房が、京都の陣営にて死去する。大内政弘は京都にて従軍していた為、此の隙に豊前国・筑後国の賊徒等が蜂起した。其の後陶弘護は、大内政弘の命で加冠し、大内から「弘」の字を貰い元服した。斯うして弘護は、第8代陶家当主に就任した。 | |
| 1,469 | 1 | 7 | 延暦寺に立ち寄っていた足利義視が、山名宗全の屋敷に入る。此れにより足利は、西軍に寝返った。勢い付いた西軍は、足利を将軍とする「西幕府」を形成した。 | |
| 1,469 | 1 | 24 | 数日前に朝倉孝景が斯波義敏に降参したとの報が京都に齎される。 | |
| ≈ | 1,469 | 1 | 27 | 足利成氏が、足利義政の代官長尾景人の守備する下野国足利荘(現在の栃木県足利市)への攻撃を開始する。成氏は、足利義視が西軍に参加するのを待ち、攻撃の機会を窺っていた。 |
| 1,469 | 1 | 31 | 西軍が山科を襲撃する。武田信賢は、山科郷民と協力して此れを退けた。 | |
| 1,469 | 3 | 12 | 足利義政が、越前国人深町久清に対し、朝倉孝景に従い斯波義廉を討つ様命じる。足利は深町の知行の安堵を約束した。 | |
| ≈ | 1,469 | 5 | 大内政弘の要請により、足利義視の内書が鎮西・四国の諸大名に多数送付される。 | |
| ≈ | 1,469 | 5 | 武田信賢が、足利義政から丹後国を与えられ、第20代室町幕府丹後国守護に就任する。同時に、摂津之親の後任として、細川政国が、丹後国与謝郡の分郡守護に任じられた。 | |
| 1,469 | 5 | 4 | 山名是豊の息子の山名頼忠が、九日城(現在の兵庫県豊岡市九日市上町)を攻める。 | |
| 1,469 | 5 | 12 |
逸見真正が、以下の人間を丹後国に討ち入らせる。 ①粟屋賢家 ②温品氏 ③青江氏 此れを受けて細川政国も、天竺賢実率いる軍を丹後国へ差し向けた。細川勢は優位に戦いを進め、一色氏の勢力を宮津湾や府中(現在の京都府宮津市)に追い込むが、丹後国守護代延永直信率いる軍が、必死の防戦に努めた。 |
|
| 1,469 | 5 | 30 | 谷ヶ堂(現在の京都府京都市西京区松室地家山)を本拠とする、野田泰忠率いる西岡被官衆が、西軍の鶏冠井政益率いる軍が籠城していた鶏冠井城を襲撃する。 | |
| ≈ | 1,469 | 6 |
六角高頼が、観音寺城奪還の為出陣する。此れを受けて室町幕府は、六角政堯の近江国守護職を罷免し、京極持清を第20代室町幕府近江国守護に据えた。此れに激昂した高頼は、観音寺城を奪還し、修復して籠城した。京極持清は、以下2名を観音寺城に派遣した。 ①多賀高忠 ②政堯 対する高頼は、以下3名を観音寺城と其の支城及び砦に配置し、東軍を撃退した。 ①山内政綱 ②伊庭貞隆 ③伊庭行隆 |
|
| ≈ | 1,469 | 6 | 観音寺城に派遣された多賀高忠に代わり、武田信賢に京都の東口の確保が命じられる。武田は、瓜生山(現在の京都府京都市左京区一乗寺松原町)に北白川城を築かせた。 | |
| 1,469 | 6 | 2 |
西軍が、松尾(現在の京都府京都市西京区松尾谷松尾山町付近)の谷の城を落とす。又同日、以下と民家が焼失した。 ①西芳寺(現在の京都府京都市西京区松尾神ケ谷町) ②峰ヶ堂(現在の京都府京都市西京区御陵峰ケ堂) |
|
| 1,469 | 6 | 2 | 畠山義就率いる軍が、谷ヶ堂を攻め落とす。西岡被官衆は丹波国へ逃亡した。 | |
| 1,469 | 6 | 13 | 西幕府が御教書を発する。其処には河野通春の名前が有った。 | |
| 1,469 | 6 | 30 | 朝倉孝景が、深町久清に加勢を依頼する。朝倉は深町に、知行の安堵を約束した。 | |
| 1,469 | 7 | 24 |
西軍が以下に攻め込む。 ①摂津国 ②丹波国 |
|
| 1,469 | 7 | 28 |
以下2名が、丸岡城(現在の京都府亀岡市余部町古城)の防備に当たる。 ①野田泰忠 ②細川勝元方の安富又次郎 |
|
| 1,469 | 8 | 9 | 伊勢貞親が朝倉孝景に対し「『貴方の側に参じて忠誠を尽くすべき』とのご意向を述べられ、実に立派な事でございます。では、御内書を書いて下さい」という主旨の書簡を送る。 | |
| 1,469 | 8 | 17 |
東軍が以下の寺を焼失させる。 ①清水寺 ②六道珍皇寺(現在の京都府京都市東山区小松町) ③建仁寺(現在の京都府京都市東山区大和大路通四条下る小松町) |
|
| 1,469 | 8 | 18 |
東軍が籠城していた安照寺城(現在の大阪府高槻市真上町)が西軍に落とされる。此れにより、野田泰忠の下に、以下2名の抱えている忍頂寺城(現在の大阪府茨木市)が苦戦しているとの報告が入った。 ①薬師寺長忠 ②四宮長能 |
|
| ≈ | 1,469 | 9 |
延永直信率いる軍が、山名宗全の命で但馬国から駆け付けた以下2名率いる援軍と共に、普甲寺(現在の京都府宮津市小田)に布陣する。 ①垣屋宗忠の息子垣屋平右衛門尉 ②垣屋出雲守 そして、細川勝元方の天竺賢実等と交戦し、天竺を討った。 |
|
| 1,469 | 9 | 1 | 京極持清方が、六角高頼方の押立城(現在の滋賀県東近江市下里町)を落城させる。 | |
| 1,469 | 9 | 2 | 大内政弘率いる軍が、東軍に帰順した池田氏の居城である池田城(現在の大阪府池田市城山町)を落城させる。 | |
| ≈ | 1,469 | 9 | 6 | 京極持清方が、六角高頼方の梁瀬城(現在の滋賀県東近江市五個荘簗瀬町)を落城させる。 |
| 1,469 | 9 | 8 |
武田信賢勢の以下2名が、丹後国へ攻め入る。 ①逸見繁経 ②粟屋元隆 しかし、一色氏被官で丹後国守護代の延永直信が此れを退けた。 |
|
| 1,469 | 9 | 23 | 京極持清方の多賀高忠が、六角高頼方の山内政綱の守備する金剛寺城(現在の滋賀県近江八幡市)を攻め、落城させる。近江国甲賀郡佐治荘(現在の滋賀県甲賀市甲賀町小佐治付近)の佐治城を本拠とする佐治氏は、山内に付いて活躍したものの、部下の戦死者を多数出し、佐治為重の息子も戦死した。 | |
| 1,469 | 9 | 25 | 多賀高忠が、慈恩寺城(現在の滋賀県近江八幡市)に於いて、六角高頼方を破る。 | |
| 1,469 | 10 | 1 | 多賀高忠が、観音寺城下石寺に於いて、六角高頼方を破る。多賀高忠率いる軍は、観音寺城を落城させ、其の後東軍は、六角高頼を追撃した。多賀は足利義政から感状を受け取った。 | |
| 1,469 | 11 | 18 | 興福寺の新供衆が、三国湊の件に関し、朝倉孝景に書簡を送る。 | |
| 1,469 | 11 | 19 |
池田城に居た大内政弘率いる軍が、以下2名の率いる大軍を前に、兵庫の確保に失敗する。 ①山名是豊 ②宇野政秀 |
|
| 1,469 | 11 | 25 | 大内政弘率いる軍が池田城を出発する。此の頃野田泰忠は丹波国に居た。 | |
| 1,469 | 12 | 24 |
南朝皇胤の末裔を称する兄弟が、以下2ヶ所で蜂起する。 ①吉野(西陣南帝(兄)が蜂起) ②熊野(西陣南帝の弟が蜂起) |
|
| 1,470 | 河野教通が、第9代李氏朝鮮国王成宗に使者を遣わせ、土貢を献上する。 | |||
| 1,470 | 陶弘護が、周防国守護代に就任する。 | |||
| 1,470 | 1 | 10 | 伊勢貞親が朝倉孝景に対し「朝倉殿の注進の旨を足利義政殿に披露した所、京都での情報と大きく違っている。先ずは戦功を以って態度を示して下さい」という主旨の書簡を送る。足利は、御内書や国拝領御判を受け取っておきながら合戦を行わない朝倉を信用していなかった。此の時越前国の内外は、西軍が大勢を占めていた。朝倉は、合戦を仕掛けて敗北すれば、東軍の情勢が悪化する為、表向きは西軍に従いながらも、越前国坂北郡(現在の福井県あわら市・坂井市三国町・丸岡町地区)の深町氏等の有力国人や大寺社を味方に勧誘する等して、合戦の準備を進めた。 | |
| 1,470 | 1 | 14 |
野田泰忠率いる軍が、山名是豊に合流する。其の後は、以下等を転戦した。 ①神呪寺(現在の兵庫県西宮市甲山町) ②山田荘(現在の大阪府吹田市) ③三宅館(現在の大阪府吹田市) |
|
| ≈ | 1,470 | 2 | 1 | 野田泰忠が、西軍が山崎(現在の京都府乙訓郡大山崎町字大山崎)に出陣するとの報告を受け、山名是豊率いる軍と共に三宅氏の陣営を出発し、山崎へ向かう。其の後は山崎城(現在の京都府乙訓郡大山崎町字大山崎)に砦を構えた。 |
| 1,470 | 2 | 15 | 山崎城にて合戦が行われる。 | |
| ≈ | 1,470 | 3 | 畠山義就が勝龍寺(現在の京都府長岡京市勝竜寺)に入り、陣城とする。 | |
| ≈ | 1,470 | 3 |
大内教幸が、大内政弘の留守中に周防国を奪取する事を意図し、長門国赤間関(現在の山口県下関市赤間町)にて、以下の人間と共に挙兵する。 ①内藤武盛 ②仁保盛安 ③吉見信頼 ④周布和兼 大内は、百計を巡らせて陶弘護も誘ったものの、陶は応じなかった。 |
|
| ≈ | 1,470 | 3 |
足利義政が、大内教幸を大内家当主として認め、以下2名に対し、備後国・安芸国・周防国の討伐を命じられた大内の援助を命じる。 ①大友親繁 ②益田兼堯 |
|
| 1,470 | 3 | 7 |
以下に出陣していた西軍が、山崎にて東軍と交戦する。 ①勝龍寺(現在の京都府長岡京市勝竜寺) ②植野(現在の京都府乙訓郡大山崎町下植野付近) |
|
| 1,470 | 3 | 11 |
以下の人間が連署で、京都に居る吉見信頼に書簡を送る。 ①内藤弘矩の兄内藤武盛 ②豊田元秀 ③杉重隆 ④杉弘重 ⑤二保武安 ⑥間田弘縄 ⑦陶弘護 以下の主旨の内容であった。 足利義政に忠節を致せという細川勝元殿の書簡を頂きましたが、大内教幸殿は老齢である為、大内殿の息子加嘉丸を奉公させるという事で大内殿に一味同心したので、細川殿に此れを取り次ぎ、速やかに公方の私信と室町幕府の安堵状を下される様にして頂きたい。 |
|
| 1,470 | 3 | 14 | 多賀高忠が、観音寺城馬場に於いて、六角高頼方を破る。 | |
| ≈ | 1,470 | 4 | 此の頃、今八幡宮(現在の山口県山口市上宇野令)の神主は、国が傾こうとしている事を憂い、毎日夜に神殿にて密かに祈りを捧げていた。或る日、此の神主は京都にて、大内政弘に 摩利支天像の掛け軸を、陶弘護に太刀を渡した。 | |
| ≈ | 1,470 | 4 | 1 | 小倉宮の血を引く西陣南帝が、紀伊国有田郡(現在の和歌山県)にて挙兵する。 |
| 1,470 | 4 | 9 | 西陣南帝が紀伊国海草郡藤白(現在の和歌山県海南市)に入る。郡の者の大半が西陣南帝に味方した。 | |
| 1,470 | 4 | 11 |
第186世興福寺別当経覚が、大友親繁に、長野宗雄を以下2ヶ所の代官職に任命させる。 ①田川郡糸田荘(現在の福岡県) ②田川郡田原荘(現在の福岡県田川郡川崎町) 長野は此の頃、大内氏と不和になり、大友氏の被官となって、糸田荘・田原荘で合わせて以下を納めさせられた。 ①進納500貫文 ②補任料50貫文 ③奉行分25貫文 |
|
| ≈ | 1,470 | 4 | 30 | 西陣南帝が大和国に入る。 |
| ≈ | 1,470 | 5 | 後花園上皇の、後南朝の残党征伐の治罰の綸旨が発せられる。 | |
| 1,470 | 5 | 14 |
勝龍寺城の搦手北の門で東軍と西軍が交戦する。安富又次郎が、お供を連れて以下2ヶ所を焼き払った。 ①馬場(現在の京都府長岡京市) ②古市(現在の京都府長岡京市神足麦生付近) |
|
| 1,470 | 5 | 16 |
山名是豊率いる軍が勝龍寺城に出陣する。其の後、野田泰忠率いる西岡被官衆は、東軍の布陣する以下3ヶ所に火を放った。 ①上里館(現在の京都府京都市西京区の上里地区) ②石見城(現在の京都府京都市西京区大原野石見町) ③井内館(現在の京都府京都府長岡京市井ノ内地区) そして、向日河原(小畑川の河原)で合戦が行われた。 |
|
| 1,470 | 5 | 26 | 大内政弘の家臣で筑前国守護代の仁保盛安の息子仁保十郎が、大内政弘の陣営を出て東軍に寝返る。 | |
| 1,470 | 6 | 3 | 山城国淀(現在の京都府京都市伏見区淀本町)にて東軍と西軍が交戦する。 | |
| ≈ | 1,470 | 6 | 10 |
山名宗全を始めとする西軍諸将が西陣南帝を天皇に擁立し、京都御所に迎え入れようとしているとの風聞が立ち始める。山名は、以下3名を味方に付けている東軍の権威に対抗する為に、西陣南帝の天皇擁立を画策していた。 ①後土御門天皇 ②後花園上皇 ③足利義政 しかし、後南朝と所領が重なっていた畠山義就は、西陣南帝の天皇擁立に反対した。 |
| 1,470 | 6 | 18 | 仁保家の総領仁保弘有が、安芸国西条(現在の広島県東広島市西条地区)衆を率いて、大内武治と共に大内政弘に背いて東軍に寝返る。 | |
| 1,470 | 6 | 19 | 摂津国茨木にて東軍と西軍が交戦する。 | |
| ≈ | 1,470 | 7 |
此の頃から2ヶ月程、多賀高忠が築城させた如意ヶ嶽城(現在の京都府京都市左京区鹿ケ谷菖蒲谷町)を拠点に、以下2名や被官が山科や勧修寺へ出陣し、西軍と戦う。 ①武田国信 ②多賀高忠 |
|
| 1,470 | 7 | 10 | 仁保十郎が、奈良を経由して西下する。 | |
| 1,470 | 7 | 12 | 西軍が賀茂御祖神社(現在の京都府京都市左京区下鴨泉川町)を焼失させる。又同日、東軍は八坂神社を焼失させた。 | |
| 1,470 | 7 | 23 | 畠山義就が、足利義視を始めとする西軍諸将の説得により、西陣南帝の天皇擁立を了承する。 | |
| 1,470 | 8 | 15 | 勧修寺に立て籠もり防衛線を敷いていた逸見繁経率いる軍が、西軍の襲撃を受ける。結果、逸見を始めとする200名が討たれ、勧修寺は燃やされた。 | |
| 1,470 | 8 | 16 | 西軍が、醍醐寺(現在の京都府京都市伏見区醍醐東大路町)の東軍を破り、醍醐寺・民家を焼失させる。 | |
| 1,470 | 9 | 1 |
陶弘護が、以下2名に対し、大内政弘に与して本意を達するべく計略を巡らし、疎意の無い事を誓う誓書を送る。 ①益田兼堯 ②兼堯の嫡男益田貞兼 |
|
| 1,470 | 9 | 14 | 山科家が、広橋綱光を通じて丹波国宮田荘の当知行安堵を室町幕府に申請する。 | |
| 1,470 | 9 | 15 | 朝倉孝景が、坂井郡河口荘本庄郷(現在の福井県あわら市)・大口郷(現在の福井県あわら市)の済物を押領する。 | |
| ≈ | 1,470 | 10 | 武田信賢率いる軍が、如意ヶ嶽城に集結する。体制の立て直しを行った。しかし此の頃から両軍で、寝返りが横行し始めた。 | |
| 1,470 | 11 | 8 | 少将殿御局が、長坂口(現在の京都府京都市北区鷹峯千束町・鷹峯一ノ坂・鷹峯長坂・鷹峯堂ノ庭町)の関所の件に於ける山科家からの依頼状を紛失した為、第17代室町幕府武家伝奏広橋綱光に女房奉書を再提出する。 | |
| 1,470 | 11 | 22 |
山科言国が申し上げた長坂口の関所の件に就いて、女中を通じて少将殿御局に取り次ぎ、足利義政に伺いを立てた所、足利から、奉行に命じて奉書をを作成させる様にとの沙汰が有った。此れにより、山科家に当知行安堵の奉行人奉書が発給される事となったが、同日、広橋綱光が、飯尾為信に対し以下の主旨の書簡を送る。 ①広橋頼光殿が此の様な書簡を下され、大沢重胤が持参して奉書を整えました。 ②山科言国が申し上げた長坂口の関所の管理に就いて、従来の知行に従い、奉書を作成する様に殿御沙汰が有りました。 此の件に就いては、少将殿御局を通じて申し上げた所、御渡しされたので、ご承知おき下さい。 |
|
| 1,470 | 12 | 12 | 大内教幸が、安芸国へ向けて出発する。 | |
| 1,471 | 1 | 13 | 陶弘護率いる軍が、鞍掛山(現在の山口県岩国市玖珂町)にて、大内教幸率いる軍を破る。大内は残党を引き連れ、大内家の家臣吉見信頼を頼って津和野(現在の島根県鹿足郡津和野町田二穂)へ敗走した。大内は、備後国の東軍に援助を命ぜられ、廿日市に兵を派遣し、自らも周防国・安芸国の国境まで進軍していた。 | |
| 1,471 | 1 | 14 | 山名是豊が、備後国へ帰国する為の条件として、山崎城の守衛を命じられる。 | |
| 1,471 | 1 | 19 | 陶弘護率いる軍が、江良城(現在の山口県萩市吉部上)にて、大内教幸の残党を破る。教幸は其の後も、吉見信頼の助けを借りて兵を集め、長門国阿武郡を攻撃したが、大内政弘の母の命により砦を築いていた陶弘護が此れを防いだ。教幸率いる軍は潰走した。 | |
| ≈ | 1,471 | 2 | 武田元綱が、毛利豊元の誘いに乗り、大内政弘に与し、西軍に寝返る。此の頃若狭武田氏が分郡守護を努める安芸国は、大内を始めとする西軍に押されていた。 | |
| ≈ | 1,471 | 3 | 粟生(現在の京都府長岡京市)にて東軍と西軍が交戦する。山名是豊も東軍として参戦した。 | |
| 1,471 | 3 | 20 | 細川勝元方から、朝倉孝景が斯波義廉の命に背いて東軍に参仕し、朝倉氏景も、越前国へ下向し、斯波義敏の被官となった旨が第21世興福寺大乗院(現在の奈良県奈良市高畑町)門主政覚に伝えられる。 | |
| ≈ | 1,471 | 4 | 仁保十郎が、東福寺(現在の京都府京都市東山区本町)の東軍の陣中に加わる。其の後仁保は西下し、大内家の領国を経由し大内教幸と合流した。 | |
| 1,471 | 4 | 13 | 山名頼忠が、円山川東岸に布陣し、奈佐太郎の支援を受けて、九日城に居た西軍の垣屋宗忠を攻撃する。垣屋は、山名宗全の孫亀石丸を養育しつつ、居留守役として在城していた。垣屋平右衛門尉が宵田城(現在の兵庫県豊岡市日高町久斗)から駆け付け、奈佐等を富辺羅山(現在の兵庫県豊岡市戸牧)に追い崩した。其の敗報を聞いた山名は敗走した。最終的に奈佐氏は滅びた。 | |
| 1,471 | 4 | 21 |
垣屋宗忠が、普甲寺にて以下と交戦する。 ①武田氏 ②天竺氏 |
|
| 1,471 | 4 | 23 |
九日城の河向かいに布陣していた山名頼忠が、九日城を攻める。山名に味方した奈佐太郎は、富辺羅山に布陣し、一色信長を支援した以下2名を挟み撃ちにした。 ①垣屋平右衛門尉 ②垣屋出雲守 垣屋氏は、富辺羅山を集中的に攻め、此れを破った為、山名は退却した。平右衛門尉と出雲守は反撃に転じ、山名を普甲寺に押し返し、以下を破った。 ①武田信賢 ②天竺賢実 此の普甲寺の戦は乱戦となり、出雲守は、戦線が勝っていたにも拘らず、負けたと思い戦線を離脱して九日城に退却し、物笑いとなった。九日城には、山名宗全が、家臣であった宗忠と共に、孫の亀王丸を養育しながら住んだ。 |
|
| 1,471 | 6 | 9 |
以下の書簡が朝倉孝景宛に送付される。 ①足利義政が此度の条々は全て承知し、朝倉氏景の東軍帰属も明白となった為、重ねての御内書が発給された旨を伝える細川勝元の書簡 ②足利義政による、朝倉を第18代室町幕府越前国守護に補任する旨の書かれた御内書・管領副状 |
|
| 1,471 | 6 | 20 | 武田信賢が病死する。 | |
| 1,471 | 6 | 26 | 夜、朝倉氏景が、細川成之の屋敷に馳せ参じる。 | |
| 1,471 | 6 | 27 | 朝倉氏景が、征夷大将軍直臣の待遇で足利義政に謁見する。朝倉は、御剣を拝領した。 | |
| ≈ | 1,471 | 7 | 粟生にて東軍と西軍が交戦する。山名是豊も東軍として参戦した。 | |
| 1,471 | 7 | 11 | 朝倉氏景が越前国に入る。若狭国を経由したが、越前国下向の手配は全て赤松氏被官中村三郎が行った。 | |
| ≈ | 1,471 | 8 | 京都で天然痘が流行する。此れにより両軍の士気は大きく下がった。 | |
| ≈ | 1,471 | 8 | 斯波義廉が、朝倉孝景を一乗谷(現在の福井県福井市城戸ノ内町)付近にて攻撃する。朝倉は富樫政親に支援を求めたが、富樫にとって朝倉は旧敵であった事から拒否された。此れに怒った朝倉は、第14代加賀国守護(北半国)赤松政則経由で、富樫成春の弐男富樫幸千代の擁立を画策した。 | |
| 1,471 | 8 | 9 | 勝龍寺城にて東軍と西軍が交戦する。山名是豊も東軍として参戦した。 | |
| 1,471 | 9 | 10 | 西軍諸将の要請を受けた西陣南帝が、北野天満宮松梅院に入る。そして、西陣南帝は天皇として擁立された。山名宗全は、自身の妹の居る西陣(現在の京都府京都市上京区薬師町付近)近くに所在する比丘尼寺の安山院を行在所とし、西陣南帝を迎えた。四条氏が、西陣南帝に奉仕した。 | |
| 1,471 | 11 | 16 | 山科言国が申し上げた諸々の件に就いて、女中を通じて少将殿御局に取り次ぎ、更に飯尾為信経由で伺いを立てた所、足利義政から、奉書を作成する様にとの沙汰が発せられる。 | |
| 1,471 | 12 | 13 | 陶弘護が、再度益田貞兼に誓書を送り、大内政弘方として同盟を結ぶ。 | |
| ≈ | 1,472 | 西陣南帝の天皇擁立に賛成していた足利義視が、反対に回る。足利は、朝倉孝景の寝返りによって東軍が勢いを取り戻しつつあった事から、態度を変えた。 | ||
| 1,472 | 神保家の家老格である氷見の鞍川氏が、能登畠山家に影響され、畠山義就方に呼応する動きを見せる。此れを受けて神保長誠は、300名余の率いて越中国へ帰国し、此れを鎮定した。同年神保は、射水郡・婦負郡の守護代に就任した。又神保は、越中国射水郡倉垣荘(現在の富山県射水市・富山市)等の寺社本所領を押領し、勢力の拡大に努めた。 | |||
| ≈ | 1,472 | 1 | 吉見信頼率いる軍が嘉年城(現在の山口県山口市阿東嘉年下)に進軍する。吉見は、大内教幸に長門国西部の諸城を攻略させる形で攻撃を開始し、陶弘護が此れを迎撃した。 | |
| 1,472 | 1 | 17 |
陶弘護が、以下の内容の京都の大内政弘宛の戦況報告の書簡を送る。 ①吉見・三隅・周布・小笠原諸氏による嘉年城包囲 ②益田貞兼が高津城(現在の島根県益田市高津町上市)等の諸城を攻略 ③自身の軍による嘉年城攻略 |
|
| 1,472 | 2 | 5 |
陶弘護率いる軍が、長門国阿武郡(現在の山口県阿武郡阿武町)にて、大内教幸率いる軍を破る。大内は豊前国へ敗走し、馬ヶ岳(現在の福岡県行橋市大谷)に入った。仁保盛安も厳島神領に逃れ、以下へ加勢する計画を立てた。 ①玖珂郡山代(現在の山口県岩国市錦町・本郷町・美和町周辺) ②佐波郡得地(現在の山口県山口市徳地地区) |
|
| 1,472 | 2 | 11 |
陶弘護が益田貞兼に、近況を伝える以下の主旨の内容を含む書簡を送る。 ①大内教幸は西暦1,472年3月4日に没落し、仁保盛安は安芸国の厳島神社の神領地である宮内村(現在の広島県廿日市市)に逃れたが容れられず、安芸武田家の分領の伴(現在の広島県広島市安佐南区)に退く積もりで、現在国衆と申し合わせて、計略の最中である。 ②仁保から吉見信頼へ宛てた書簡を途中で奪い取ったが、其の書中に玖珂郡山代・佐波郡得地へ加勢する事が書かれている。よって、益田殿の一層の奔走を祈る。 ③吉見信頼の分領並びに庄内郷(現在の山口県防府市牟礼)・黒谷郷(現在の山口県山口市徳地深谷付近)方面への発向計画はどうなっているのか。当方で得た情報によれば、吉見勢は山代及び地福(現在の山口県山口市阿東町大字地福上・大字地福下)方面への進出を企んでいる為、此れを牽制する為にも、背後から吉見領への進攻を急いで貰いたい。 |
|
| 1,472 | 2 | 23 |
以下2名による和睦交渉が開始される。 ①細川勝元 ②山名宗全 此の時点で東軍は、大義名分や戦況に於いて優位に立っていた。西軍の降伏で話が進んでいたが、以下3名が反対し、不調に終わった。 ①東軍 ❶赤松政則 ②西軍 ❶畠山義就 ❷大内政弘 |
|
| ≈ | 1,472 | 6 | 細川勝元が、細川勝之や家臣と共に髷を落とし、隠居の姿勢を見せ、自身の嫡男である細川政元に家督を継がせる意向を示す。政元の母は山名宗全の養女で山名熙貴の娘の春林寺殿であり、山名家の血を引く政元に家督を継がせる事で、和睦を進める狙いが有った。 | |
| ≈ | 1,472 | 6 | 山名宗全が切腹を試みるが、未遂に終わる。 | |
| 1,472 | 6 | 16 |
関目彦右衛門尉宛の室町幕府奉行人連署奉書に、以下の主旨の内容が記される。 津田隆光が、借りた物に就いて室町幕府に提訴した。以前、論人である関目は、支状を提出した儘在国しているという。余りにも勝手な振る舞いであり、言語道断である。不日政所に参る様に。 |
|
| ≈ | 1,472 | 9 | 山名宗全が、家督を山名政豊に譲り、隠居する。 | |
| 1,472 | 12 | 24 |
津田隆光宛の室町幕府奉行人連署奉書に、以下の主旨の内容が記される。 関目彦右衛門尉は、西暦1,466年の徳政令を破棄する奉書を得ていたが、借状には此の旨が掲載されていなかった為に、関目の主張を退ける。津田は質券の地である近江国富田荘(現在の滋賀県長浜市)の内の知行分を以って本利一倍分を勘定する様に。 |
|
| 1,473 | ボローニャでモンテ・ディ・ピエタが設立される。 | |||
| 1,473 | ボローニャでモンテ・ディ・ピエタが廃業する。 | |||
| 1,473 | 大友親繁が隠居し、自身の嫡男大友政親に家督を譲る。此れにより、大友家の両統迭立の廃止はより強固なものとなった。政親は、足利義政から偏諱を賜り、第16代大友家当主に就任した。 | |||
| 1,473 | 1 | 1 | 小早川煕平が死去する。此れを受けて足利義視は、煕平の所領を小早川弘景に与える御内書を発した。 | |
| 1,473 | 4 | 15 | 山名宗全が病死する。其の後西陣南帝は、西軍諸将によって追放された。和睦交渉は、山名政豊が引き継いだ。 | |
| 1,473 | 5 | 9 |
以下2名が和睦交渉を行う。 ①細川勝元 ②山名政豊 しかし、畠山義就が承知せず不調に終わった。 |
|
| 1,473 | 5 | 19 | 足利義視が、一条兼良に進退を相談する書簡を送る。 | |
| 1,473 | 6 | 6 | 細川勝元が死去する。和睦交渉は細川政元が引き継いだ。 | |
| 1,473 | 6 | 8 | 足利義政が、細川勝元の死去を受けて、吉川元経等に忠節を求める。 | |
| 1,473 | 10 | 21 | 小早川弘景が、高山城へ向けて出発する。 | |
| 1,473 | 10 | 21 | 京極政経が、第24代室町幕府近江国守護に就任する。 | |
| 1,473 | 11 | 22 | 東軍の沼田小早川方の浦平五が、高山城にて討死する。 | |
| 1,473 | 11 | 26 | 小早川元平が、室町幕府の命により、西軍に与する者を成敗し、領内に陣取る近国の兵を退散させる。 | |
| 1,473 | 12 | 11 | 河野教通が、東幕府からの伊予国守護職の補任状を受け取る。此れにより河野は、第17代室町幕府伊予国守護に就任した。 | |
| 1,473 | 12 | 13 | 第10代扇谷上杉家当主上杉政真が、五十子(現在の埼玉県本庄市)にて戦死する。政真には子供が居なかった為、太田道灌や重臣達が評議した結果、政真の叔父である上杉定正を扇谷上杉家当主に迎える事になった。此れにより定正は、第11代扇谷上杉家当主に就任した。 | |
| 1,474 | ボローニャで奢侈条例の一部として、ユダヤ人の衣装に関する規制が設けられる。 | |||
| 1,474 | 大内政弘が、陶弘護の功績を称え、尾張権守に任じる。 | |||
| 1,474 | 1 | 7 | 足利義政が征夷大将軍職を足利義尚に譲り、義尚が第9代室町幕府征夷大将軍に補任される。 | |
| ≈ | 1,474 | 2 |
以下2名が和睦交渉を行う。 ①細川政元 ②山名政豊 しかし、此処でも以下3名は反対し、不調に終わった。 ①東軍 ❶赤松政則 ②西軍 ❶畠山義就 ❷大内政弘 |
|
| ≈ | 1,474 | 2 | 朝倉孝景が、日野川(現在の福井県)の合戦で、斯波義廉の家臣である増沢祐徳を破る。更に、杣山城(現在の福井県南条郡南越前町社谷)に籠城していた越前国守護代甲斐敏光も撃破した。其の後杣山城は、河合宗清の居城となり、朝倉の支配下となった。 | |
| 1,474 | 2 | 12 | 政所内評定始が再開される。 | |
| 1,474 | 2 | 12 | 足利義視が、小早川弘景に小早川煕平の遺産を委ねる。 | |
| 1,474 | 3 | 4 | 一休宗純が、後土御門天皇の勅命により住持となる。 | |
| 1,474 | 3 | 20 |
足利義政が、花の御所を足利義尚に譲り、小川殿(現在の京都府京都市上京区寺之内通堀川東入ル百々町)に移る。以下2名は花の御所に残った。 ①日野富子 ②足利義尚 第180世興福寺別当尋尊は「政務は日野殿が取り仕切り、足利殿は酒に溺れ、諸大名は犬笠懸に興じ、まるで天下泰平の世の様だ」と評した。 |
|
| 1,474 | 3 | 28 | 足利義尚が内裏に参内する。 | |
| 1,474 | 3 | 29 | 足利義尚が内裏に参内する。 | |
| 1,474 | 3 | 29 | 畠山義就が、東寺の僧坊に風呂銭を課す。 | |
| ≈ | 1,474 | 4 | 野田泰忠が、軍忠を注進し、細川政国の確認を得る。 | |
| 1,474 | 4 | 18 |
足利義視が、以下の国の国人に対し、高山城攻めの合力を命じる。 ①備後国 ②安芸国 |
|
| 1,474 | 4 | 19 |
以下2名が単独で和睦する。 ①細川政元 ②山名政豊 仲介を務めたのは武田国信であった。武田に突き付けられた和睦の条件の1つとして、一色義直と戦って奪った丹後国の所領を返還し、丹後国守護職を一色義春へ返付する、というものが有った。又同日、細川家と山名家を隔てる空堀には橋が架けられ、東陣(現在の京都府京都市上京区上小川町付近)から山名の陣を通って北野天満宮に参詣する者や、西軍の勢力下であった下京から東陣へ物を売る商人等が往来を始めた。 |
|
| 1,474 | 5 | 1 | 一色義直が、船岡山(現在の京都府京都市北区紫野北舟岡町)の陣営を撤収させる。 | |
| 1,474 | 5 | 1 | 山名政豊が、自身の長男の山名常豊を連れて、足利義尚に謁見する。政豊の東幕府への帰参が認められた。 | |
| 1,474 | 5 | 9 | 山名政豊勢と畠山義就勢の足軽同士が交戦する。御構外の山名占拠の堀川以西が東軍支配下となり、人・物の往来が緩和された。 | |
| 1,474 | 5 | 16 | 和泉国上半国守護家の細川政有が、足利義政から偏諱を受ける。 | |
| 1,474 | 5 | 31 |
甲斐敏光率いる軍が、坂井郡や甲斐国に逃れた牢人と合流し、九頭竜川(現在の福井県)を超えて、岡保(現在の福井県福井市河水町)に進軍し、朝倉孝景率いる軍を攻撃、戦闘が開始される。以下で激戦が繰り広げられた。 ①殿下(現在の福井県福井市) ②桶田(現在の福井県福井市河増町) 朝倉氏景が敵を多数討ち取った。 |
|
| ≈ | 1,474 | 6 | 15 | 足利義政が、一色義春を引見する。 |
| ≈ | 1,474 | 6 | 15 | 此の頃、甲斐敏光勢と朝倉孝景勢の戦闘が、波着寺(現在の福井県福井市成願寺町)周辺に移る。 |
| 1,474 | 6 | 21 |
足利義視が、一色氏の知行していた領国を其々の忠誠に応じて以下の通り分配する決定を下す。 ①三河国:讃州細川家 ②伊勢国・丹後国:一色義春 ③若狭国:武田国信 此れにより、一色は第22代室町幕府丹後国守護に就任した。又、同年足利義政は、第26代室町幕府伊勢国守護北畠政郷に、伊勢国半国を一色に返付する様命じたが、北畠は此れを拒否した。 |
|
| 1,474 | 6 | 29 |
一色義春に丹後国守護職が返付された事に抵抗する以下2名の家臣が、一色勢と丹後国で交戦する。 ①武田国信 ②細川政国 此の時点で、武田・細川は丹後国を掌握していた。 |
|
| 1,474 | 6 | 29 | 朝倉孝景が、西軍方の富樫成春の弐男富樫幸千代と連携し、波着寺周辺にて甲斐敏光率いる軍と激戦を繰り広げる。波着寺周辺には、半助谷と呼ばれる場所が在り、其処には甲斐と親しい武将の館が在った。此処で敗れれば本拠地に攻め込まれかねない状況であった朝倉は、必死の防戦で、甲斐氏・千福中書増沢・甲斐法花院舎弟を悉く討ち、勝利した。平泉寺(現在の福井県勝山市平泉寺町平泉寺)の衆も多くが損害を受けた。 | |
| 1,474 | 6 | 29 | 甲斐敏光方が多く討たれた事を知った真盛が、卒塔婆を大畔縄手(現在の福井県福井市岡西谷町付近)に建設する。岡ノ西光寺(現在の福井県福井市次郎丸町)にて百万遍の回向を行なった。 | |
| ≈ | 1,474 | 7 |
斎藤妙椿が、数千騎を率いて越前国に入り、以下の間を調定の末和解させる。 ①朝倉孝景 ②甲斐敏光 此の頃、西軍諸将が和睦しようとしたが、斎藤の反対により実現しなかった。 |
|
| 1,474 | 8 | 5 | 上京中御門方の西軍の足軽が、同じ西軍の大内政弘勢と交戦する。 | |
| 1,474 | 8 | 8 |
山名政豊を始めとする西軍諸将が、足利義尚に出仕し謁見する。西軍は、足利義視の征夷大将軍擁立の姿勢を一変させ、其の方針転換を名実共に対外的に示した。此の姿勢に以下の人間が反発した。 ①畠山義就 ②土岐成頼 ③大内政弘 |
|
| 1,474 | 8 | 13 |
山名政豊勢が以下を放火する。 ①二条大宮 ②岩神神社(現在の京都府京都市右京区京北熊田町雨ヶ岳) ③猪熊通・堀川通の在家3〜4町分 |
|
| 1,474 | 8 | 14 |
畠山政長勢が以下を放火する。 ①三条坊門小路 ②猪熊通 ③堀川通 ④油小路通 |
|
| 1,474 | 8 | 19 | 大内政弘が、本能寺(現在の京都府京都市中京区下本能寺前町)から猪熊通・堀川通・油小路通周辺に布陣する。又、畠山義就は、二条大宮から三条大宮(現在の京都府京都市中京区)に掛けて布陣した。 | |
| 1,474 | 8 | 24 |
西軍の足軽が以下を放火する。 ①三条坊門小路 ②油小路通西面 一方東軍は、河野教通と通じた中川家を始めとする勢力が、土岐成頼の屋敷を攻め落とし、周囲も含めて放火した。 |
|
| 1,474 | 8 | 25 |
東軍が以下を放火する。 ①下京土岐第 ②妙行寺 ③法華寺(現在の京都府京都市下京区西新屋敷中之町) |
|
| 1,474 | 8 | 30 |
以下等が、大内政弘に呼応して京都に入る。 ①大和国添上郡古市(現在の奈良県奈良市古市町)を拠点とする古市氏 ②大和国高市郡越智荘(現在の奈良県高市郡高取町付近)を拠点とする越智氏 |
|
| 1,474 | 9 | 7 | 西軍が北野千本に放火する。 | |
| 1,474 | 9 | 7 |
花の御所から、以下2名に五劔が下される。 ①山名政豊 ②細川政元 |
|
| ≈ | 1,474 | 10 |
丹後国の一色義春勢が以下2名の家臣を破り、旧領回復に成功する。 ①武田国信 ②細川政国 武田は援軍を丹後国に送る事が出来ず、主将の逸見真正は自害した。此の敗北を受けて武田は出家した。 |
|
| 1,474 | 11 | 23 | 未明、富樫政親が、籠城していた蓮台寺城(現在の石川県小松市蓮代寺町)主富樫幸千代を攻め、陥落させる。此の際第8世本願寺宗主蓮如が、見返りとして保護して貰う事を意図して政親方として介入した。しかし政親は、本願寺門徒の勢いを恐れ、弾圧を始めた。幸千代は京都へ敗走し、加賀国守護職の奪回工作を行なった。 | |
| 1,474 | 12 | 10 | 大友親繁の京都郡奉行2名が、佐田河内守に京都郡吉田荘(現在の福岡県行橋市上稗田付近)内の70町を譲る。 | |
| 1,474 | 12 | 21 | 足利義政が、改めて大内政弘を左京大夫に任じ、懐柔に乗り出す。 | |
| 1,475 | 此の年、京都で洪水・暴風雨等の自然災害が頻発する。 | |||
| ≈ | 1,475 | 1 | 25 | 高山城が、小早川弘景率いる西軍の攻撃により、落城寸前となる。此れを受けて足利義政は、領主の小早川元平を急ぎ帰国させた。又足利は、再度毛利豊元を呼び寄せた。小早川敬平も京都から戻って来た。足利は御教書を発し、近隣の豪族に敬平を助ける様命じた。此れによって東軍は盛り返した。 |
| 1,475 | 2 | 6 | 応仁の乱の勃発以降休止されていた朝廷儀式が再開される。 | |
| 1,475 | 2 | 18 | 室町幕府が、再度毛利豊元を招く。 | |
| 1,475 | 4 | 7 | 両軍が備後国で交戦する。毛利豊元は、自身の家臣である国司有純を遣わせ、情勢を報告させた。 | |
| 1,475 | 4 | 10 |
両軍が以下にて交戦する。 ①沼田荘真良(現在の広島県三原市高坂町) ②沼田荘本郷(現在の広島県三原市) |
|
| ≈ | 1,475 | 4 | 26 | 此の時点で西軍は、高山城の包囲を続けていた。 |
| 1,475 | 5 | 3 | 室町幕府が、重ねて山名是豊に小早川元平への合力を命じる。 | |
| 1,475 | 5 | 6 |
細川政国が、室町幕府の命により、以下の国の被官等に、小早川元平への合力を命じる。 ①備前国 ②備中国 |
|
| 1,475 | 5 | 9 | 両軍が、高山城の麓で交戦する。 | |
| 1,475 | 5 | 15 |
小早川元平が、西軍が提示した高山城の包囲を解く条件である、以下の割譲案を呑む。 ①沼田荘熊井田本郷(現在の広島県三原市沼田西町松江) ②沼田荘安直本郷(現在の広島県三原市沼田西町納所・小原・松江・惣定一帯) ③沼田荘梨子羽郷(現在の広島県三原市本郷地区) |
|
| 1,475 | 5 | 23 |
西軍が、以下の調停により、高山城の包囲を解き始める。 ①宮元信 ②宮盛忠 又、庄元資以下の東軍も撤退した。 |
|
| 1,475 | 5 | 26 | 西軍が高山城から撤退する。 | |
| 1,475 | 9 | 6 | 六角高頼に山門領を押領された延暦寺の衆徒が、室町幕府に六角征伐を願い出る。 | |
| ≈ | 1,475 | 10 |
出雲国に落ち延びていた以下2名が、出雲国の国人衆を率いて上洛する。 ①京極政経 ②多賀高忠 東軍に付いていた京極は、第19代室町幕府出雲国守護に補任され、六角氏から近江国を奪還する様命じられた。 |
|
| 1,475 | 11 | 26 |
六角高頼が、佐々木荘(現在の滋賀県近江八幡市安土町地区)にて以下を破る。 ①京極政経 ②延暦寺山門衆徒 |
|
| 1,475 | 11 | 26 | 仁保盛安の息子で少弐政資の被官の仁保弘名が、津隈荘(現在の福岡県行橋市上津熊・中津熊・下津熊)40町を下毛郡(現在の大分県中津市)の池永彦次郎へ打ち渡す。 | |
| 1,476 | 足利義政が、一色氏の三河国の旧領を改めて一色義春に与える。しかし、第11代室町幕府三河国守護細川成之は、此れを拒み、国領を渡さなかった。 | |||
| ≈ | 1,476 | 1 |
吉見信頼が、元山城(現在の山口県山口市阿東徳佐下)を攻撃する。しかし吉見は、陶弘護に敗れ、以下の所領を奪われた。 ①吉賀(現在の島根県鹿足郡) ②長野(現在の島根県益田市) ③北九州 其の所領は、益田貞兼や大内家の家臣に当てられた。吉見は其の後も、長門国へ軍勢を送る等して威嚇したが、合戦には至らなかった。陶の正室は益田兼堯の娘であったが、益田家と吉見家は犬猿の仲であった。 |
|
| 1,476 | 4 | 21 |
佐田忠景を始めとする宇佐郡(現在の大分県豊後高田市・宇佐市)衆が、周防国から豊前国へ渡る。其の後瀧池山に布陣し、以下の城に籠城する大友親繁・少弐政資等の征伐を開始した。 ①馬ヶ岳城(現在の福岡県行橋市大谷・西谷) ②岩石城(現在の福岡県田川郡赤村添田町添田) 此の時、豊前国守護代の杉弘勝が京都に居た為、大内政弘は、宇佐郡衆の中から大将を出す様佐田忠景に求め、佐田は此れに応じた。 |
|
| ≈ | 1,476 | 5 | 畠山政長が、河内国を確保する事を意図し、遊佐長直を派遣する。 | |
| ≈ | 1,476 | 6 |
少弐政尚が、旧領を回復すべく、以下の人間を始めとする4,000名の兵を率い、豊前国に入る。 ①宗職盛 ②宗国久 そして、馬ヶ岳城・岩石城等の古城に籠城した。陶弘護が兵3,000名を率いて覗山城(現在の福岡県行橋市稲童)を築いて対陣して合戦となり、大内方が60名、少弐方が6名の戦死者を出したが、勝負は付かなかった。 |
|
| 1,476 | 6 | 20 | 佐田忠景が、余(現在の大分県宇佐市院内町上余)の合戦を始めとする宇佐郡の戦いで敵を多数討ち取ったとして、大内政弘から感状を得る。 | |
| 1,476 | 7 | 4 | 大内政弘は、宇佐郡衆に感状を与える。 | |
| 1,476 | 8 | 12 | 大内政弘が門司彦九郎に、西暦1,476年6月20日に覗山城の合戦で負傷した事を労う軍忠状を送る。 | |
| 1,476 | 9 |
以下2名が、三河国に出陣し、三河国守護代東条国氏を自害に追い込む。 ①一色義直 ②一色義春 |
||
| ≈ | 1,476 | 9 |
室町幕府が、以下2名に対し、内藤藤左衛門尉・仁保盛安が豊前国にて合戦しているのを止めさせ、和睦する様命じる。 ①大友政親 ②大内教幸 |
|
| 1,476 | 9 | 7 | 室町幕府が、大内教幸に対し、豊前国での停戦を命じる。 | |
| 1,476 | 10 | 1 | 足利義政が、大内政弘に和睦を求める書簡を送る。其の後大内は、日野富子の仲介の下、足利義視と共に東軍との和睦交渉に当たった。大内の手元に留め置かれていた、室町幕府の遣明船の唐荷引き渡しが大内赦免の条件であった。 | |
| 1,476 | 11 | 29 | 花の御所が炎上する。 | |
| 1,477 |
足利義政が、大友政親の家督継承を正式に認め、大友を以下2ヶ国の守護に任じる。 ①豊後国 ②筑後国 |
|||
| 1,477 | 薬師寺長盛の嫡男薬師寺元一が生誕する。 | |||
| 1,477 | 1 | 5 | 足利義視が足利義政に対し、他意の無い事を伝える書簡を送る。斯うして、義視は義政に恭順を誓った。義政は、義視の罪を不問に付す、という主旨の返答をし、日野富子の仲介によって両軍は和睦した。 | |
| 1,477 | 3 | 29 |
以下2名の間に大内義興が生誕する。 ①大内政弘 ②賀茂神社の社家である鳥居大路氏の娘で畠山義統の養女の今小路 |
|
| 1,477 | 5 | 9 | 室町幕府が、大友政親等に対し、大内政弘が先年の下知状を持って、大内教幸が周防国・長門国へ渡海するので協力せよとのお触れを出しているので、此れを止めて上洛させよとの命を下す。 | |
| 1,477 | 5 | 31 | 河野通春が、東軍に内通していた大内政弘の仲介によって東軍に下り、足利義尚の安堵を取り付ける。 | |
| ≈ | 1,477 | 6 | 室町幕府が、伊勢国北半国守護職を一色義春に与える。同職は北畠政郷が補任されていたが、罷免しない儘一色に与えられた為、現地の代官同士が揉め、一色は奪還を意図し現地入りし、合戦に発展した。結果、北畠が勝利した。周囲は、北畠が畠山義就に味方するのではないかと警戒したが、杞憂に終わり、北畠は、伊勢国北半国守護職に再任された。 | |
| 1,477 | 6 | 13 | 足利義視が、大内政弘経由で日野富子へ和睦の仲介料を支払う。 | |
| ≈ | 1,477 | 8 | 足利義視が、自身の娘を日野富子の下に送り、猶子にして貰う。 | |
| ≈ | 1,477 | 10 | 東条国氏の後継者の東条修理亮が、自身の京都の屋敷を一色義直に攻められ、一族郎党300名と共に、大和国へ逃亡する。 | |
| 1,477 | 10 | 27 |
畠山義就が、河内国へ向けて京都を出発する。1ヶ月前くらいから畠山が京都を離れる噂は立っており、畠山は、以下の大和国人等と打ち合わせを行なっていた。 ①越智氏 ②古市氏 |
|
| 1,477 | 10 | 29 |
畠山義就が、以下を含む250騎・具足を装着した2,000名余を率い山城国から河内国牧(現在の大阪府枚方市牧野地区)に入る。 ①甲斐庄氏19騎 ②誉田氏42騎 其の後畠山は、河内国守護所で、河内国守護代遊佐長直の籠城する若江城(現在の大阪府東大阪市若江北町)を攻撃した。以下も河内国に入り、畠山に加勢した。 ①越智氏 ②古市氏 畠山率いる軍は、天王寺に移り、堺の占領を目指したが、和田助直によって阻まれ、河内国に引き返した。 |
|
| ≈ | 1,477 | 11 | 高田為長が河内国・大和国の畠山政長方と共に、妻の実家である飯高城を攻撃する。境界争いが発端であった。古市氏の後詰めが遅く、飯高城主毛利吉信は自害し、高田は勝利した。 | |
| 1,477 | 11 | 2 | 畠山義就率いる軍が、東軍の守備していた客坊城(現在の大阪府東大阪市客坊町の市杵嶋姫神社)を襲撃する。結果、畠山勢が客坊城を落城させた。 | |
| ≈ | 1,477 | 11 | 2 |
室町幕府が、畠山義就追討の綸旨を奏請する。結果、後土御門天皇から畠山政長や以下に対し、綸旨が発せられた。 ①興福寺 ②多武峰(現在の奈良県桜井市) ③高野山 ④粉河寺(現在の和歌山県紀の川市粉河) ⑤根来寺(現在の和歌山県岩出市根来) |
| 1,477 | 11 | 6 | 畠山義就率いる軍が八尾城(現在の大阪府八尾市本町)に入城する。 | |
| 1,477 | 11 | 12 |
畠山義就率いる軍が、畠山政長方の以下の人間が守備する誉田城(現在の大阪府羽曳野市誉田)を攻撃する。 ①誉田城主和田美作守 ②恩智氏 ③丹下氏 ④越智氏 ⑤古市氏 筒井順尊・箸尾為国や大和国箸尾(現在の奈良県北葛城郡広陵町)・宇智(現在の奈良県五條市)の国人である以下の人間は、政長方に付き、西軍と戦った。 ①杉野氏 ②宇野氏 ③坂部氏 ④野原氏 そして、越智氏・古市氏が、筒井・箸尾を破り、南都を占拠した。筒井・箸尾・箸尾の大和国人は追撃を躱し、福住(現在の奈良県天理市)に逃亡した。西軍は、以下を含む30名余を自害に追い込み、200名余を没落させて、誉田城を落城させた。 ①和田 ②杉野氏 ③宇野氏 ④坂部氏 ⑤野原氏 和田を始めとする37名の首級は、京都に居る政長の下に送られた。筒井順尊は教興寺(現在の大阪府八尾市教興寺)から大和国へ追い返された。又、以下の人間が越智氏に付いた。 ①十市氏 ②龍田氏 ③片岡氏 |
|
| 1,477 | 11 | 13 |
嶽山城(現在の大阪府富田林市龍泉)が、畠山義就方の大和国の吐田氏によって陥落する。又、往生院城(現在の大阪府東大阪市六万寺町)も落城し、焼失した。西軍の勢力拡大により、以下の人間と土地等が没落した。 ①宝来祐尊 ②筒井順尊(自焼没落) ③筒井の後継人成身院順宣(自焼没落) ④安楽坊順憲 ⑤萩別所氏 ⑥小林 ⑦辻子 ⑧木津 ⑨金剛寺(現在の大阪府河内長野市天野町) ⑩曽部 ⑪北院 ⑫小南(現在の奈良県大和郡山市) ⑬今市新 ⑭六条 ⑮堀 嶽山城は、西暦1,471年に畠山政長方に占領されていたが、義就が奪回した形となった。 |
|
| 1,477 | 11 | 14 |
畠山義就率いる軍が、若江城を落城させる。遊佐長直は、天王寺から船を出し、大和川を渡って撤退した。島氏も、平群谷(現在の奈良県生駒郡平群町)の居館に自ら火を放ち、逃亡した。此れにより畠山は以下を略手中に収めた。 ①河内国 ②大和国 |
|
| 1,477 | 11 | 18 | 大内政弘が、畠山義就に呼応し、木津城(現在の京都府木津川市城山台)を攻撃する。東軍は敗れ、木津氏は自ら木津城に火を放った。 | |
| ≈ | 1,477 | 12 |
室町幕府が、大内政弘の以下4ヶ国の守護職を承認する。 ①周防国 ②長門国 ③豊前国 ④筑前国 此れは大内が、足利義政に遣明船の唐荷を納めた為、赦免された事によるものであった。又朝廷も、大内の官位を昇叙させた。此れ等は日野富子の仲裁によるものであった。 |
|
| ≈ | 1,477 | 12 | 河野通春が、陣所を引き払って伊予国へ帰国する。 | |
| ≈ | 1,477 | 12 | 日野富子が、大内政弘の帰国によって戦う意味が無くなった畠山義就に1,000貫文を貸し付け、撤退を促す。畠山は此れに応じ、河内国へ向けて京都を出発した。 | |
| ≈ | 1,477 | 12 |
壬生晴富が以下の主旨の内容を記す。 西暦1,471年12月頃、足利義政殿に命じられて文庫の屋根を葺き替えたが、既に数年が経ち、大きく損傷し、度重なる雨により壁が雪崩て、其の状態は言葉にならない程酷いものである。戦乱後も平穏無事であったが、今後は湿損するであろう。 |
|
| ≈ | 1,477 | 12 |
足利義視・足利義稙が、以下2名の庇護の下、川手城(現在の岐阜県岐阜市正法寺町)へ下向する。 ①土岐成頼 ②斎藤妙椿 |
|
| 1,477 | 12 | 16 | 西軍の諸将が一斉に下国する。大内政弘は、陣所を引き払って伊予国へ向かった。足利義視も、自身の嫡男の足利義稙を伴い、美濃国の土岐成頼の下に亡命し、承隆寺(現在の岐阜県岐阜市茜部寺屋敷)に滞在した。 | |
| 1,477 | 12 | 25 | 室町幕府が、天下静謐の祝宴を開催する。足利義政は、京都の東軍諸将と共に、応仁の乱の終結を祝った。しかし、河内国・大和国の大半は畠山義就が押さえており、火種が燻っていた。 | |
| 1,478 | 第212代ローマ教皇シクストゥス4世の許可により、カスティーリャ地方(現在のスペイン中心部)以外で、スペインに於いて異端審問所が設置される。 | |||
| 1,478 | 陶弘護が、筑前国守護代に就任する。周防国守護代職と兼務する事となった。 | |||
| ≈ | 1,478 | 1 | 一条兼良が京都に戻る。其の後一条は、足利義尚に政道や和歌等を教えた。足利は、翌年頃から盛んに歌会を主催した。 | |
| 1,478 | 1 | 18 |
大友政親が以下の内容を記す。 当方の調停により合戦は止んだが、少弐方が仁保盛安を殺害した為、国中が正体無き成り行きとなった。内藤氏に与した族は遺恨を止めたが、九州大乱の元になりかねない。 |
|
| 1,478 | 1 | 26 | 大内政弘が周防国へ帰国する。其の際陶弘護は、柳井津(現在の山口県柳井市)にて大内を出迎え、富田保(現在の山口県周南市富田)の自身の屋敷で持て成した。大内は「国が平穏無事であったのは其方のお蔭である」と感謝し、大内と陶は義兄弟の契りを交わした。陶は、夜は大内政弘の寝所で控え、昼は饗応した。 | |
| ≈ | 1,478 | 3 | 一色義遠が、文書で三河国を放棄する。又、尾張国知多郡も東軍に没収された為、義遠は、一色政具等と共に槇島城(現在の京都府宇治市槇島町薗場付近)に入った。 | |
| ≈ | 1,478 | 4 | 吉見信頼が大内政弘に謝罪し、和睦を求める。大内は此れを認めた。大内は、陶弘護に筑前国を任せ、陶は忠節を尽くした。 | |
| 1,478 | 8 | 8 | 足利義政が、足利義視を赦免する。しかし義視は、美濃国に留まり続けた。 | |
| 1,478 | 9 | 23 |
大内政弘が、大内義豊に以下等を預け、知行させる。 ①豊前国宇佐郡 ②豊前国京都郡二塚(現在の福岡県行橋市) |
|
| ≈ | 1,478 | 10 |
大内政弘が、以下の国へ遠征を行う。 ①豊前国 ②筑前国 陶弘護は先駆けとして戦った。 |
|
| 1,478 | 10 | 20 |
大内政弘率いる軍が、太宰府にて少弐政資率いる軍を破る。少弐達は散り散りとなった。此れを受けて、以下を始めとする人間が、大内の下に祝言を述べる為にやって来た。 ①城井俊明 ②周防国分寺住持 ③馬ヶ岳城城督右田弘量 ④佐田忠景 ⑤仲間盛秀 ⑥彦山座主頼有 ⑦頼有の息子帥律師 |
|
| 1,478 | 10 | 28 | 此の日から3日間、陶弘護が、頼有の計略により捕らえられた仁保弘名の首級を、博多土井町(現在の福岡県福岡市博多区店屋町)の称名寺の門前に梟首する。 | |
| 1,478 | 10 | 31 |
大内政弘が、西暦1,469年8月頃以来、周防国・長門国へ亡命していた以下の国の被官に対し、兵糧料として周防国・長門国の寺社領を半済としていたものを、米銭・借物の返済を免除する徳政令を出す。 ①豊前国 ②筑前国 |
|
| 1,478 | 11 | 4 | 大内政弘が、西暦1,469年以降周防灘を渡って長門国へ逃れていた筑後国の被官・国人に対し、米銭借物の返済を免除する徳政令を出す。 | |
| 1,478 | 11 | 11 | 箱崎の民衆が、大内政弘が足利家に対する貢納として、博多と同じく筥崎地下にも1,000貫文を賦課し、進納すべき旨の請文を、博多に居た大内政弘に提出する。 | |
| 1,478 | 12 | 8 | 西陣南帝が、京都から東海を経由して、甲斐国の小石沢(現在の山梨県笛吹市石和町小石和)の観音寺に入る。 | |
| 1,478 | 12 | 26 | 大友親繁に与えられていた豊前国守護職が、大内教幸に与えられる。しかし少弐氏が競望した為、大内家と少弐家の対立は継続した。又此の頃、少弐政資を支援した大友氏は、少弐氏と不仲になった。 | |
| 1,479 | 大内政弘の命により、筥崎宮(現在の福岡県福岡市東区箱崎)にて釣鐘が造られ、功績が刻まれる。 | |||
| 1,479 | 3 | 6 | 花の御所の再建が開始される。 | |
| 1,479 | 5 | 17 | 土御門内裏の修繕が開始される。 | |
| 1,479 | 8 | 6 | 西陣南帝が、国人等に送られて、越後国から越中国を経由して越前国北ノ庄(現在の福井県福井市)に入る。其の後西陣南帝は、奥州へ下向し自身を「熊沢現覚坊」と称し、身分を秘匿した。 | |
| ≈ | 1,479 | 9 | 北畠政郷が、上意を違えたという理由により、伊勢国守護職を罷免される。此れにより、伊勢国が一色義春の手に戻った。 | |
| ≈ | 1,479 | 12 |
足利義尚が、以下を行い、政務を執り始める。 ①御判始 ②評定始 ③御前沙汰始 しかし、依然として足利義政が実権を握っており、父子間に確執が生じた。 |
|
| 1,480 | 日野富子が、応仁の乱で荒廃した内裏の修造費用を捻出するという名目で、京の七口に新関所を開設し、通行税を徴収を始める。 | |||
| ≈ | 1,480 | 1 | 陶弘護が、筑前国守護代職を、自身の弟右田弘詮に譲る。其の後陶は、周防国へ帰国した。 | |
| 1,480 | 3 | 27 |
大内政弘が、楞厳寺(現在の大分県中津市耶馬溪町大字三尾母)住持の以下の寺領を安堵する。 ①仲津郡立石 ②仲津郡香丸 ③宮市の内の一部 ④内田法橋跡 ⑤上毛郡牧菊丸8町 |
|
| 1,480 | 5 | 8 | 足利義尚が、権大納言に任ぜられる。 | |
| 1,481 | スペインのユダヤ人街が、カテドラル(大聖堂)からサンティアゴ・デ・コンポステーラ大聖堂(現在のスペインのガリシア州ア・コルーニャ県)の門に移設される。 | |||
| 1,481 | 陶弘護が、伊勢神宮を参詣する。 | |||
| 1,481 | 1 | 13 | 大内政弘が、安東俊国に、仲津郡天生田荘(現在の福岡県行橋市)の一部を恩賞として与える。 | |
| 1,481 | 9 | 24 | 足利義尚主催の「着到千首和歌」が、禁裏にて開催される。後土御門天皇等が詠人として参加し、飛鳥井雅親が点者を務めた。 | |
| ≈ | 1,481 | 10 | 陶弘護が、周防国へ帰国する。 | |
| 1,481 | 12 | 11 | 足利義尚主催の「将軍家三十番歌合」が開催される。足利も詠人として参加し、飛鳥井雅親が判者を務めた。 | |
| 1,482 | 2 | 21 | 足利義政が命じた山荘造営が、浄土寺(現在の京都府京都市左京区浄土寺地区)にて着手される。 | |
| ≈ | 1,482 | 4 | 小笠原元長が、大内政弘に拝謁する。其の際陶弘護は「武門にある以上、武芸を極めるのは当然であり、武は弓矢を以って要とする。今日、天下の弓矢の道は小笠原を以って規範とするものである」として、小笠原に師事し、奥義を学んだ。 | |
| ≈ | 1,482 | 4 | 西暦1,475年11月26日に仁保弘名から池永彦次郎に打ち渡された津隈荘40町の内20町が、大内政弘から毛利弘元に預けられる。 | |
| ≈ | 1,482 | 6 | 吉見信頼が、自身の弟の吉見頼興に家督を譲る。此れにより頼興は、第9代石見吉見家当主となった。又此の頃信頼は、大内政弘に拝謁した。 | |
| 1,482 | 6 | 13 | 吉見信頼が、大内館(現在の山口県山口市大殿大路)での宴会にて、陶弘護を吉見家の家宝の短刀である鵜噬を用いて刺殺する。大内義興の家臣で長門国守護代の内藤弘矩は、直様吉見を斬殺した。吉見頼興は、陶家の報復を予見し、吉見家の書物を処分したが、報復は行われなかった。 | |
| 1,482 | 6 | 14 | 大内政弘が、陶弘護が吉見信頼と共に死去した事は残念無念であるとの主旨の書簡を右田弘詮に送る。 | |
| 1,482 | 6 | 25 |
足利義尚主催の「将軍家百番歌合」が開催される。以下の人間等が詠人として参加し、飛鳥井雅親が判者を務めた。 ①足利 ②二条持通 ③近衛政家 |
|
| 1,482 | 7 | 28 | 足利義政が、足利義尚に政務を譲る意思を表明する。 | |
| ≈ | 1,482 | 8 |
足利義尚主催の「十五番歌合」が開催される。以下の人間等が詠人として参加し、飛鳥井雅親が判者を務めた。 ①足利 ②二条持通 ③近衛政家 |
|
| 1,482 | 9 | 23 | 足利義尚主催の「将軍家将軍家千首歌合」が開催される。 | |
| ≈ | 1,483 | クリストファー・コロンブスが第4代アヴィス王朝の王ジョアン2世に、大西洋を西回りしてアジアへと到達する航海計画を願い出るが、審議した数学者委員会が此れを拒否する。 | ||
| 1,483 | 2 | 20 |
足利義尚主催の「将軍家詩歌合」が開催される。詩は近衛政家等が詠み、歌は以下の人間等が詠人として参加した。衆議により判定を行った。 ①後土御門天皇 ②後土御門天皇の第一皇子後柏原天皇 ③足利義尚 ④二条持通 ⑤近衛政家 ⑥中院通秀 |
|
| 1,483 | 4 | 15 | 大内政弘が、伊勢神宮参詣者への餞別を禁止する。 | |
| 1,483 | 5 | 4 |
足利義尚が内裏に参内する。此の日内裏で歌会が開催され、以下の人間が詠んだ歌を含む、神明に奉納する諏訪法楽30首が披露された。 ①後土御門天皇 ②後柏原天皇 ③足利義政 |
|
| 1,483 | 7 | 31 | 足利義政が、完成したばかりの「東山殿常御所」に移り、日野富子と別居する。足利は依然として実権を握り続け、確執は続いた。 | |
| 1,483 | 8 | 1 | 足利義政が、後土御門天皇から東山殿の称号を賜る。 | |
| 1,483 | 11 | 24 |
三条西実隆が、足利義尚が撰定した私撰和歌集「新百人一首」を足利の下で見る。新百人一首は、藤原定家が撰定した小倉百人一首から漏れた歌人の歌を各和歌集から100首撰定したものであった。更に足利は同年、以下の歌人を結集して和歌打聞「撰藻鈔」の編纂に乗り出した。 ①姉小路基綱 ②三条西 ③飛鳥井雅親 ④宗祇 ⑤二階堂政行 ⑥三条西の門人細見宗高 |
|
| 1,484 | 足利義尚が、摂津国の多田院(現在の兵庫県川西市)に「多田院廟前詠五十首和歌」を奉納する。 | |||
| 1,484 | 大内家の干渉を受ける事を嫌った大友政親が、自身の嫡男大友義右に家督を譲る。此れにより義右は、第17代大友家当主に就任した。 | |||
| 1,484 | 9 | 23 | 一色義春が病死する。 | |
| 1,485 |
クリストファー・コロンブスが長男ディエゴ・コロンを連れて、トラスタマラ朝カスティーリャ女王イサベル1世に航海計画の承認を得る為、パロス・デ・ラ・フロンテーラ(現在のスペインのアンダルシア州ウエルバ県)へ到着する。サンタ・マリア・デ・ラ・ラビーダ修道院長の神父フアン・ペレス・デ・マルチェーネと会った。マルチェーネはコロンブスの航海計画に感銘を受けて、セビリア(現在のスペインのアンダルシア州)の神父アントニオ・マルチェーナを紹介した。マルチェーナに会う為にコロンブスはコロンを預けた。更に以下の人間に会う機会を得、コロンブスの航海計画に興味を持った第5代メディナセリ公爵ルイス・デ・ラ・セルダからコロンブスが求めた数隻の船や食料など3,000〜4,000ドゥカート相当の物資を準備する事に合意した。 ①スペイン貴族のメディナ・シドニア家エンリケ・デ・グスマン ②セルダ |
|||
| 1,485 | 大友親綱の六男大聖院宗心が大友政親・大友義右の離間を図り工作していた事や、大内家による干渉が尚も続いた事から、政親は次第に義右を疎ましく感じる様になり、政親・義右が対立する。そして義右は、叔父の大内政弘の下へ逐電した。政親の正室は、大内教弘の娘であった。 | |||
| 1,485 | 5 | 22 |
亀泉集証が、山荘造営の一環として本年完成した「西指庵」に入る。其の後「今日、初めて西指庵に入り、其れを見たが、正に天下の奇観である」と記す。本年は、西指庵の他に、以下も完成した。 ①超然亭 ②浴室 |
|
| 1,485 | 7 | 26 | 足利義政が、臨川寺(現在の京都府京都市右京区嵯峨天龍寺造路町)にて、月翁周鏡を戒師として出家する。剃髪は、第79世相国寺住持横川景三が担った。 | |
| 1,485 | 10 | 29 | 月翁周鏡が、足利義政の命により、第225世南禅寺住持に就任する。 | |
| 1,485 | 12 | 1 | 足利義政が命じた山荘造営の一環で、阿弥陀仏を安置する持仏堂の襖10枚が制作される事が決定される。画題として十牛図が考えられたが、阿弥陀に関する10の機縁はないかという事で、足利義政は、五山文学で一番の碩学である横川景三と相談する様、亀泉集証に命じた。 | |
| 1,485 | 12 | 6 | 足利義政が命じた山荘造営に於ける、阿弥陀仏を安置する持仏堂の襖10枚の制作に関し、阿弥陀の周囲を十僧が囲撓し、各々宝樹下に座す図柄が採用される。狩野正信に1枚描かせる事になり、襖の画面と同じ寸法の紙が狩野に渡された。足利義政は亀泉集証に対し、夏珪・馬遠の筆様か、若しくは其れ以外の筆様でも良いので、1枚描く様指示した。 | |
| 1,485 | 12 | 8 | 狩野正信が、2幅の草案を提出する。其の際狩野は「馬遠様も良いが、既に西指庵の画様が馬遠様なので、李龍眠様が良いのではないか」と意見を述べた。更に足利家所蔵の馬遠・李龍眠の絵を画様の参考に借りたい旨、及び図様の手本として、九品曼荼羅を取り寄せて欲しい旨を要望した。 | |
| 1,485 | 12 | 30 |
狩野正信の下に、足利家の御倉に所蔵されていた以下が届けられる。 ①李龍眠筆の文殊維摩の画本1幅 ②李迪筆の牛の画本2幅 狩野の要望が通った形となった。 |
|
| 1,486 |
足利義尚主催の「殿中十五番歌合」が開催される。以下の人間等が詠人として参加し、飛鳥井雅親が判者を務めた。 ①冷泉為広 ②三条西実隆 |
|||
| 1,486 | 東求堂が完成する。東求堂内の書院は「同仁斎」と名付けられ、茶室の源流となった。 | |||
| 1,486 | 1 | クリストファー・コロンブスが、フアン・ペレス・デ・マルチェーネの計らいで、イサベル1世(カスティーリャ女王)に初めて謁見を許され、大西洋を西回りしてアジアへと到達する航海計画を伝え、3隻の船を与えて欲しいと請願した。計画は特別審査委員会に諮られたが、容易に結論は出なかった。 | ||
| 1,486 | 1 | 6 | 狩野正信が、九品曼荼羅を大慈院(現在の京都府京都市北区紫野大徳寺町)に返却する。 | |
| 1,486 | 1 | 19 | 相阿弥が、草案を作る為の紙を持って亀泉集証の下を訪れる。 | |
| 1,486 | 1 | 20 | 相阿弥が亀泉集証の下に持参した草案用の紙が、狩野正信の下に届けられる。 | |
| 1,486 | 1 | 23 |
以下4名が、十僧の画様に就いて協議する。 ①亀泉集証 ②横川景三 ③相阿弥 ④狩野正信 |
|
| 1,486 | 2 | 2 | 足利義政に対し、十僧の草案が提出される。足利は、幾つか注文を付け、画本として李龍眠の老子青牛図を取り出す様、相阿弥に命じた。 | |
| 1,486 | 2 | 21 | 足利義政が、十僧の草案10幅を狩野正信に返却する。更に足利は、此の襖絵が設置される建設途中の自身の持仏堂「東求堂」を、狩野に見せる様命じた。 | |
| 1,486 | 2 | 24 |
以下2名が、東求堂を拝見する。 ①狩野正信 ②亀泉集証 |
|
| 1,486 | 3 | 4 | 狩野正信が、足利義政に新たな十僧の草案を、西暦1,486年2月21日に足利から返却された草案10幅と併せて提出する。足利は検討に入った。 | |
| 1,486 | 3 | 17 |
狩野正信が、亀泉集証に十楽に就いて相談する。此の時には、十僧だけで無く、十楽の案も浮上していた。亀泉は、同席した以下2名から意見を受けた。 ①横川景三 ②桃源瑞仙 |
|
| 1,486 | 3 | 18 | 足利義政が、十僧の図様が画一的で変化に乏しいと意見する。 | |
| 1,486 | 3 | 19 | 東求堂の襖絵が、十僧に決定される。 | |
| 1,486 | 4 | 20 | 足利義尚主催の「文明十八年殿中千五百番歌合」が開催される。 | |
| 1,486 | 4 | 27 | 大内政弘が、道場寺(現在の福岡県行橋市)領の12町4反余を、造営料として善福寺(現在の山口市道場門前)に寄付する。又、道場寺の前住持暁光は、法門の事を殆ど知らず、俗人と変わらない生活をしているとの理由で、寺領を没収された。 | |
| 1,486 | 4 | 28 | クリストファー・コロンブスが、ルイス・デ・ラ・セルダの紹介でフェルナンド2世(アラゴン王)及びイサベル1世(カスティーリャ女王)に謁見し、航海計画を話す。イサベル1世(カスティーリャ女王)は興味を示したが、フェルナンド2世(アラゴン王)は全く関心が無かった。懺悔聴聞師で神父のエルナンド・デ・タラベラを中心とする、地理や財政の専門家から成る諮問委員会で審議される事となった。 | |
| 1,486 | 4 | 28 | 狩野正信が、完成した十僧10枚を足利義政に提出する。足利は満足し、俸給1,000疋を狩野に支給した。 | |
| 1,486 | 8 | 25 | 上杉定正が、太田道灌を扇谷上杉家の本拠である糟屋館(現在の神奈川県伊勢原市上粕屋)に招く。定正は、太田の功績を妬み、謀反の疑いを掛けて招くに至った。そして、定正の配下曽我兵庫が、太田が入浴後に風呂場の小口から出た無防備な所を襲った。太田は「当方滅亡」と言って絶命した。又、第11代山内上杉家当主上杉顕定は、定正に「太田はお前の首を狙っているぞ」と讒言していた。又太田は、自身の働きが正当に評価されていないと溢し、扇谷上杉家が躍進したのは私のお蔭だとして憚らず、定正の意見を軽んじる始末であった。 | |
| ≈ | 1,486 | 9 | 京極政経が、老臣多賀宗直に命じ、敏満寺城(現在の滋賀県犬上郡多賀町敏満寺)に居る京極高清を攻めさせる。結果、高清は敗北し、敏満寺城を捨て、甲賀郡三雲(現在の滋賀県湖南市)に逃れた。 | |
| ≈ | 1,486 | 9 | 太田道灌の嫡男太田資康が、江戸城に帰還し、家督を継承する。 | |
| ≈ | 1,486 | 10 | クリストファー・コロンブスの航海計画がエルナンド・デ・タラベラを中心とする諮問委員会で審議される。 | |
| 1,486 | 10 | 10 | ジョアン2世がアジアに至る交易路確立の為のアフリカ周回航海の遠征隊長に、バルトロメウ・ディアスを任命する。 | |
| ≈ | 1,486 | 11 | 京極高清が反撃に転じ、多賀宗直が美濃国へ逃亡する。 | |
| 1,487 |
山荘造営の一環として、以下が造営される。 ①東山殿会所 ②弄清亭 |
|||
| ≈ | 1,487 | 初代堀越公方足利政知が、自身の嫡男足利茶々丸を素行不良を理由に廃嫡し、土牢に幽閉する。代わりに自身の参男足利潤童子を後嗣とした。 | ||
| 1,487 |
以下2名が和解する。 ①大友政親 ②大友義右 義右は、大内家から大友家に帰還した。 |
|||
| ≈ | 1,487 | 1 | 上杉定正が、太田資康を江戸城から追放する。定正は江戸城を占拠し、太田は山内上杉家を頼り甲斐国へ逃れ、上杉顕定に付いた。 | |
| 1,487 | 1 | 26 | 足利義稙が、足利義尚の猶子として元服する。 | |
| ≈ | 1,487 | 4 | クリストファー・コロンブスの航海計画がエルナンド・デ・タラベラを中心とする諮問委員会で審議される。否定的な意見が多数を占めたが、航海を実現させたかったタラベラやカトリック修道会であるドミニコ会ディエゴ・デ・デサは結論を引き延ばしていた。 | |
| 1,487 | 5 | 23 | 国友河原(現在の滋賀県長浜市国友町)にて、京極高清が京極政経を攻める。そして高清は、国友城(現在の滋賀県長浜市国友町)主国友兵庫助を攻撃した。此れを受けて政経は、国友の援軍として多賀宗直を国友城に派遣した。其処で高清は、国友城の包囲を解き、国友河原で多賀率いる軍を迎撃した。高清の作戦は成功し、多賀率いる軍は月ヶ瀬(現在の滋賀県長浜市)に逃れたが、多賀は、敵の追撃からは逃れられないと悟り自刃した。 | |
| ≈ | 1,487 | 8 | 奉公衆の一色政具の訴訟案件が幕府に持ち込まれる。此れを切っ掛けに、他の近江国の奉公衆も六角行高に対し訴訟を起こした。 | |
| 1,487 | 8 | 12 | 足利義尚が、六角高頼征伐を正式に決定する。在京・在国の諸将を招集した。 | |
| 1,487 | 8 | 16 |
室町幕府奉行人諏訪貞通等が勧進して集められた歌50首が、諏訪大社上社(現在の長野県諏訪市中洲宮山)の御射山祭にて奉納される。題は、以下を含む10題で其々5首詠まれた。 ①花 ②郭公 ③月 ④恋 ⑤山家 ⑥旅 ⑦祝 詠人は以下の人間等が名を連ねた。 ①足利義尚 ②近衛政家 ③日野富子 ④飛鳥井雅親 ⑤一条冬良 ⑥伊勢貞宗 |
|
| ≈ | 1,487 | 9 | 足利義尚に子供が居ない事を憂えた日野富子の意向により、足利義稙が従五位下・左馬頭に叙位任官される。此の頃、義稙を義尚の猶子とし、長享・延徳の乱で近江国に居た義尚を京都に戻して義稙を近江国に置くという案も有ったが、実行されなかった。 | |
| 1,487 | 9 | 16 | 足利義稙が、日野富子の推挙により、美濃国在国の儘従五位下に叙され、同時に左馬頭に任ぜられる。 | |
| 1,487 | 9 | 27 | 六角高頼方が、近江国南部各地への布陣を終える。 | |
| 1,487 | 9 | 28 |
以下を身に纏った足利義尚が、六角高頼征伐の為、坂本へ向けて出陣する。 ①香の袷 ②白綾の腹巻 ③赤地金襴に桐唐草の模様の直垂 ④重藤弓 ⑤粟田口吉光の太刀 其の際、着飾った足利を一目見ようと見物人が集まった。兵力は391騎・8,000名で、以下の諸将も加わった。 ①京極政経 ②京極高清 ③田中兵衛尉 ④土肥刑部少輔 ⑤大原政重 ⑥大原尚親 ⑦伊勢又六 ⑧吉田源四郎 ⑨岩室弥四郎 坂本に入ってからは、以下の人間等と合流した。 ①細川政元 ②斯波義寛 ③畠山政長 ④山名氏 ⑤一色氏 ⑥富樫政親 ⑦京極氏 ⑧武田国信 此の際加賀国守護代山川高藤は、富樫の命で等持院領加賀粟津保に兵糧200石・人夫100名を命じた。等持院は此れに反発し、山川と繋がりの有る等持院の人間が減免を請うた。結果、15貫200文を納めた他は免除された。 |
|
| 1,487 | 9 | 30 | 六角高頼が、観音寺城を放棄し、甲賀郡へ逃亡する。 | |
| 1,487 | 10 | 6 |
細川政元率いる軍が、琵琶湖を経由して以下に到着する。 ①山田(現在の滋賀県草津市) ②志那(現在の滋賀県草津市) 其の後細川は、坂本から陸路で瀬田(現在の滋賀県大津市)を経由してやって来た足利義尚率いる軍と合流し、六角高頼の指示で山田方面を守備していた山中橘六率いる軍と野洲河原にて交戦した。山中は敗れたものの室町幕府軍に多大な損害を与え、戦功を挙げた甲賀武士53名は、後に甲賀五十三家と呼ばれた。其の中で戦果の目覚ましい21名は、六角から感状を受け、甲賀二十一家と呼ばれた。甲賀五十三家は以下の通り。 ①望月出雲守(筆頭格) ②山中十郎(柏木三家、六角から感状を受けた) ③伴佐京介(柏木三家、六角から感状を受けた) ④美濃部源吾(柏木三家、六角から感状を受けた) ⑤黒川久内(北山九家、六角から感状を受けた) ⑥頓宮利盛(北山九家、六角から感状を受けた) ⑦大野宮内小輔(北山九家、六角から感状を受けた) ⑧岩室大学介(北山九家、六角から感状を受けた) ⑨芥川左京亮(北山九家、六角から感状を受けた) ⑩隠岐右近太夫(北山九家、六角から感状を受けた) ⑪佐治河内守(北山九家、六角から感状を受けた) ⑫神保兵内(北山九家、六角から感状を受けた) ⑬大河原源太(北山九家、六角から感状を受けた) ⑭大原源三郎(南山六家、六角から感状を受けた) ⑮和田伊賀守(南山六家、六角から感状を受けた) ⑯上野主膳正(南山六家、六角から感状を受けた) ⑰高峰蔵人(南山六家、六角から感状を受けた) ⑱池田庄右衛門(南山六家、六角から感状を受けた) ⑲多喜俊兼(南山六家、六角から感状を受けた) ⑳鵜飼源八郎(荘内三家、六角から感状を受けた) ㉑内貴伊賀守(荘内三家、六角から感状を受けた) ㉒服部藤太夫(荘内三家、六角から感状を受けた) ㉓小泉家 ㉔倉治家 ㉕夏見家 ㉖杉谷家 ㉗針家 ㉘小川家 ㉙大久保家 ㉚上田家 ㉛野田家 ㉜岩根家 ㉝新城家 ㉞荻野家 ㉟矢川家 ㊱佐々木家 ㊲藤林家 ㊳鳥居家 ㊴森家 ㊵田中家 ㊶池尻家 ㊷藤川家 ㊸山田家 ㊹中村家 ㊺藤原家 ㊻喜多家 ㊼久野家 ㊽太田家 ㊾東家 ㊿西家 ❶岡本家 ❷村田家 ❸藤堂家 |
|
| 1,487 | 10 | 10 |
以下等の率いる軍が、六角氏の要衝である伊庭氏の拠点である八幡山(現在の滋賀県近江八幡市南津田町)・九里氏の拠点である金剛寺(現在の滋賀県近江八幡市)を攻撃する。 ①細川政元 ②武田国信 ③富樫政親 ④京極高清 ⑤仁木貞長 ⑥細川元治 ⑦伊勢貞陸 ⑧安富氏 ⑨上原氏 ⑩物部氏 伊庭氏・九里氏は逃亡し、室町幕府軍は此れ等を陥落させた。次に室町幕府軍は、観音寺城攻略を目指した。 |
|
| 1,487 | 10 | 10 |
観音寺城に居た六角高頼が、以下を頼り、日野川沿いに三雲に逃れる。 ①甲賀武士 ②山中氏 ③望月氏 ④和田氏 |
|
| 1,487 | 10 | 20 |
足利義尚率いる軍が、六角高頼を追って、坂本から琵琶湖を経由して安養寺(現在の滋賀県栗東市)に布陣する。そして、六角氏の押領地を没収し、側近や寺社に還付した。諸将も分散して布陣し、義尚は、足利義政に以下の歌を贈った。 坂本の浜路を出て浪安く養ふ寺にありと答へよ (坂本の浜辺の道を出て、波を安らかに養う寺に居る、と答えなさい) 此れを受けて義政は、以下の返歌を贈った やかてはや国収りて民安く養ふ寺を立ちぞ帰らん (もう直ぐ国を治めて、民を安らかに養う寺から立って帰ろう) |
|
| ≈ | 1,487 | 11 | 正覚寺(現在の滋賀県草津市上笠)に布陣していた浦上則宗率いる軍が、先陣を切って甲賀郡に侵攻する。しかし、六角高頼は正面切って戦おうとせず、伊勢国に行方を眩ませた。 | |
| 1,487 | 11 | 12 | 足利義尚が、本陣を山徒真宝坊の居館である真宝館(現在の滋賀県栗東市上鈎)に移す。 | |
| 1,488 | ポルトガル人のコヴィリャンがインドのカノナール港に到着する。 | |||
| 1,488 |
クリストファー・コロンブスの弟バルトロメ・デ・ラス・カサスがカスティーリャ王国の援助を受ける事が難しいと考え、以下の2名にコロンブスの航海の援助を依頼する為にフランスへと出発する。 ①初代テューダー朝の王ヘンリー7世 ②第7代ヴァロワ朝の王シャルル8世 結果、何れも援助の取り付けには至らなかったもののシャルル8世の姉アンヌ・ド・ボージューの歓待を得て、バルトロメはフォンテーヌブロー(現在のフランスのセーヌ・エ・マルヌ県)の宮殿に数年間滞在した。 |
|||
| ≈ | 1,488 | 1 | 西暦1,487年9月28日の足利義尚の坂本への出陣に際し、富樫政親が兵粮米・軍費を領国である加賀国の民衆に課し、反富樫の機運が高まった事から、富樫は帰国し、高尾城(現在の石川県金沢市高尾町)に入る。一揆方は、富樫の家老山川高藤を介して和睦を伝えたが、富樫は受け入れなかった。富樫は、高尾城を修築して戦いに備えた。 | |
| 1,488 | 1 | 1 | 六角高頼方の甲賀衆が、伊勢貞誠の陣を放火する。 | |
| 1,488 | 1 | 15 |
六角高頼率いる軍が、甲賀郡の山中から出陣する。又、山内政綱は三上(現在の滋賀県野洲市)に布陣した。そして夜、望月出雲守と以下の甲賀二十一家が、近江国鈎(現在の滋賀県栗東市上鈎付近)の足利義尚の陣所に夜襲を仕掛けた。 ①山中十郎 ②伴佐京介 ③美濃部源吾 ④黒川久内 ⑤頓宮利盛 ⑥大野宮内小輔 ⑦岩室大学介 ⑧芥川左京亮 ⑨隠岐右近太夫 ⑩佐治河内守 ⑪神保兵内 ⑫大河原源太 ⑬大原源三郎 ⑭和田伊賀守 ⑮上野主膳正 ⑯高峰蔵人 ⑰池田庄右衛門 ⑱多喜俊兼 ⑲鵜飼源八郎 ⑳内貴伊賀守 ㉑服部藤太夫 地元の地形を熟知していた甲賀衆は、煙幕を張ったり放火を仕掛けたりして混乱を起こし、足利の本陣に迫った。敵が攻めてくると身を隠し、敵が撤退すれば後ろから攻撃を加える「亀六の法」と呼ばれる戦法によって室町幕府軍は翻弄され、最終的には大損害を被り、足利も深手を負った。 |
|
| 1,488 | 1 | 22 | 甲賀衆が、織田広近の陣を放火する。 | |
| 1,488 | 2 | 25 | 越前国の朝倉孝景に援軍を要請した富樫政親の被官松坂信遠が、2,000騎余で高尾城を出陣し、槻津上野にて越前国の軍勢を待つも、今江兼治率いる加賀国江沼郡の7,000騎余の軍勢に攻められる。松坂は討ち取られた。 | |
| ≈ | 1,488 | 3 |
山川高藤が、越中国からの援軍を迎える為1,500名を率いて高尾城を出陣する。しかし、以下の一揆方の夜襲を受け、高尾城に戻った。 ①馬飼氏 ②浦上氏 |
|
| ≈ | 1,488 | 3 |
上杉顕定が、以下2名と共に1,000騎で鉢形城(現在の埼玉県大里郡寄居町鉢形)から出陣する。 ①太田資康 ②三浦高救 第9代室町幕府越後国守護上杉房定は、自身の嫡男で白井城(現在の群馬県渋川市白井)主の上杉定昌を通じて、顕定を支援していた。 |
|
| 1,488 | 3 | 18 | 上杉顕定率いる軍が、七沢城(現在の神奈川県厚木市七沢)を攻撃する。七沢城を守備していた上杉定正の弟上杉朝昌が応戦するも落城し、朝昌は大庭城(現在の神奈川県藤沢市大庭)へ敗走した。顕定は、糟屋館へと向かった。 | |
| 1,488 | 3 | 18 | 上杉顕定率いる軍が、200騎余で川越城(現在の埼玉県川越市郭町)から駆け付けた上杉定正率いる軍と、実蒔原(現在の神奈川県伊勢原市日向)で交戦する。実蒔原の地形を熟知していた定正率いる軍は、寡兵にも拘らず、激戦の末辛うじて顕定率いる軍を破った。 | |
| 1,488 | 5 | ポルトガルのバルトロメウ・ディアスが喜望峰(南アフリカ西ケープ州ケープタウン)に到達する。 | ||
| 1,488 | 5 | 5 | 上杉定昌が、従者と共に自害する。 | |
| ≈ | 1,488 | 6 | 富樫政親に討たれた、本願寺門徒を味方に付けていた政親の弟富樫幸千代の敵を打つ為に擁立された富樫泰高率いる本願寺門徒を始めとする一揆方が、政親が10,000名余の兵を率いて籠城している高尾城の包囲を開始する。 | |
| ≈ | 1,488 | 7 |
以下2名が、上杉定正の居る川越城を攻める為、2,000名の軍勢を率いて鉢形城から出陣する。 ①上杉顕定 ②顕定の養子上杉憲房 此れを受けて定正は、以下の人間と共に、700騎余を率いて須賀谷原(現在の埼玉県比企郡嵐山町菅谷)付近に布陣した。 ①第2代古河公方足利政氏 ②長尾景春 ③上杉朝昌の弐男で定正の養子の上杉朝良 |
|
| 1,488 | 7 | 2 | 甲賀衆が、浦上則宗の陣を放火する。 | |
| 1,488 | 7 | 5 | 足利義尚が、越前国の朝倉孝景等に富樫政親の下へ援軍を派遣する様命じる。朝倉は応じ、加賀国へ援軍を派遣したが、一揆方が越前国との国境を封鎖して入国を阻んだ。 | |
| 1,488 | 7 | 9 | 一揆方が、大乗寺(現在の石川県金沢市長坂町)に本陣を構え、高尾城の包囲を本格化させる。富樫政親は高尾城から出て、打って出た。しかし、一揆方を破る事は出来なかった。 | |
| 1,488 | 7 | 13 |
富樫政親の救援に向かっていた以下率いる2,000名の軍が、倶利伽羅峠(現在の石川県河北郡津幡町・富山県小矢部市)にて一揆方に敗れる。 ①遊佐氏 ②神保氏 |
|
| 1,488 | 7 | 13 | 畠山義統が富樫政親へ差し向けた援軍が、河北郡黒津船地内(現在の石川県河北郡内灘町宮坂)にて本願寺門徒に敗れる。 | |
| 1,488 | 7 | 13 | 富樫政親方の将本郷春親が、本願寺門徒等の一揆方に高尾城の包囲を解く様促すが、失敗する。其の後、富樫方と一揆方で小競り合いが発生した。 | |
| 1,488 | 7 | 15 |
6時、富樫泰高率いる一揆方が高尾城を攻撃する。富樫政親率いる1,500名の軍は、大手門は松山左近、搦手の額谷口は森宗三郎を其々守将とし、以下の人間等が将兵を指揮した。 ①斎藤八郎 ②安江弥太郎 ③小早川半弥 ④新倉将監 ⑤浅井九八 政親方の本郷春親は、部下を率いて河合藤左衛門の部隊を攻め、河合を討とうとした。しかし河合は先陣には居らず、代わりに伊藤久内が本郷を捕縛した。其処に、春親の息子本郷松千代丸が攻め出て伊藤を斬殺したが、木村八郎九郎と組み打ち、木村に捕縛された。政親方の小川隼人成定は、寺井豊後の部隊を攻撃し、寺井の息子を斬殺した後丘に登って休憩していた所、矢の雨を浴び、斬首された。昼に休戦したが、政親の軍は以下の人間を始めとする200名余の戦死者を出した。 ①本郷春親 ②額景春 ③額親家 ④林正蔵坊 ⑤正蔵坊の弟林六郎二郎 ⑥高尾若狭守 ⑦槻橋弥次郎 ⑧斎藤彦八郎 ⑨安江 ⑩安江三郎 ⑪宇佐美八郎左衛門 ⑫山田弥五郎 ⑬広瀬源左衛門 ⑭広瀬又七 ⑮徳光次郎 ⑯松本新五郎 ⑰阿曽孫六 ⑱霜田伊豆坊 ⑲奈良与八郎 ⑳松原彦四郎 ㉑多田源六 ㉒石田帯刀 ㉓和田次郎三郎 ㉔越前国の溝口兄弟 ㉕越前国の一木兄弟 ㉖松千代丸 ㉗板倉喜内 ㉘森勝介 ㉙岡豊後守 ㉚佐々木志摩助 ㉛柏原与市 ㉜古沢勘七 ㉝同朋衆の知阿弥 政親の家臣57名や城兵達は、高尾城からの脱出を始めた。山川高藤は、政親の正室巴を一揆方の光徳寺(現在の石川県金沢市玉川町)と申し合わせて、高尾城から脱出させた。此れは、山川の妹おわんが、一揆方の安吉城(現在の石川県白山市安吉町)主大窪家長に嫁いでいた事から実現した。又山川自身も、政親を裏切り高尾城から脱出した。 |
|
| 1,488 | 7 | 16 | 山内上杉方が、扇谷上杉方の防衛拠点の1つである武蔵松山城(現在の埼玉県比企郡吉見町北吉見)を攻撃する。又、須賀谷原(現在の埼玉県比企郡嵐山町菅谷)でも小規模な戦いが発生した。 | |
| 1,488 | 7 | 17 |
富樫政親が、自身の嫡男富樫家延と共に自害し、高尾城が落城する。又山川高藤は、一揆方の将三池掃部率いる軍に捕縛され、祇陀寺(現在の石川県白山市吉野付近)に幽閉された。其の後山川は、夕闇に紛れて脱出し、越前国大野(現在の福井県)へ向かった。更に、政親の後を追って、以下の人間も自害した。 ①宮永八郎三郎 ②勝見与四郎 ③福光弥三郎 ④那波氏 ⑤吉田氏 ⑥小河氏 ⑦白河氏 ⑧進藤氏 ⑨黒川氏 ⑩興津屋五郎 ⑪谷屋入道 ⑫徳光西坊林 ⑬金子氏 ⑭田上入道 ⑮八屋藤左衛門入道 ⑯立入加賀入道 ⑰長田三郎左衛門 ⑱宮永左京進 ⑲沢奈井彦八郎 ⑳安江和泉守 ㉑神戸七郎 ㉒御園筑前守 ㉓御園五郎 ㉔槻橋豊前守 ㉕槻橋近江守 ㉖槻橋三郎左衛門 ㉗槻橋式部丞 ㉘槻橋弥六 ㉙槻橋弥次郎 ㉚槻橋三位坊 ㉛山川又次郎 ㉜本郷春興坊 ㉝本郷駿河守 政親の自害を聞いた足利義尚は激怒し、蓮如に本願寺門徒等の破門を迫った。政親の首級は、富樫泰高によって灰の中から探し出され、大乗寺に葬られた。 |
|
| 1,488 | 7 | 26 | 朝、山内上杉軍と扇谷上杉軍が須賀谷原にて交戦する。扇谷上杉軍は、上杉朝良が先陣を切ったが、台地の低部で、平澤寺(現在の埼玉県比企郡嵐山町平澤)に布陣していた山内上杉軍に逆落としに攻撃を掛けられ崩されるも、長尾景春率いる部隊が横槍を入れた事で山内上杉軍が浮き足立ち、其処を上杉定正が、高台から味方に指図して突き崩させた。更に長尾率いる部隊は、山内上杉軍の藤田三郎勢を破り、扇谷上杉軍が勝利した。此の戦での戦死者は700名余、馬も数百頭が犠牲になった。 | |
| 1,488 | 8 | 11 | 蓮如が、一向宗門徒の行動を非難・叱責する。 | |
| ≈ | 1,488 | 10 | 足利義尚が陣中に打たせていた60本の刀が完成する。足利は、二階堂政行経由で陰陽博士土御門有宣から、60名の刀鍛冶に60本の刀を打たせれば敵を誅滅出来ると聞き、刀を作らせていた。 | |
| ≈ | 1,488 | 10 | 足利義尚が陣中に打たせていた60本の刀が完成した翌日、足利が病に倒れる。日野富子が看病に駆け付けた。足利は元々体が弱く、軍営での激務と共に、京都から訪れる公家・高僧の接遇を自ら行い、酒量も増えていた。足利は其の後一旦回復し、日野は京都に戻った。 | |
| 1,488 | 12 | 17 |
上杉定正が、以下2名に援軍を求め、2,000騎で山内上杉軍を攻撃する為に進軍する。 ①足利政氏 ②長尾景春 此れを知った山内上杉軍は、上杉房定に援軍を求め、鉢形城から程近い高見原(現在の埼玉県大里郡寄居町今市)に3,000名余で布陣した。夕方、高見原にて、山内上杉軍と扇谷上杉軍が交戦した。此れを不安に思った長尾は、上杉定正に相談した。上杉は、鉢形城から出張って来た山内上杉軍の旗指物が動かなくなり、休息を取り始めた時に攻撃する様指示した。夜、長尾が上杉の指示通りに攻撃し、風上である事も手伝って、兵力が山内上杉軍よりも劣っていたにも拘らず撃破した。山内上杉軍は鉢形城に敗走した。其の後も山内上杉軍は、後方の支援を受けて、鉢形城を保持し続けた。軈て、三度山内上杉軍を破った上杉は驕り始め、太田道灌を暗殺した事を部下から疑問視されていた事も有り、離反する武将が出始めた。家臣が、言動を慎み各方面との和解に努める様促す書簡を上杉に送る程であった。 |
|
| 1,489 | フランチェスコ・デ・タシス1世がマクシミリアン1世(神聖ローマ皇帝)の郵便物の無料配達を請け負う。 | |||
| 1,489 | 大友政親の異母弟である日田親胤が、肥後国にて謀反を起こす。此の時政親は上洛中であった。此れは、大友親繁の五男大友親治によって鎮圧され、親治は、政親・大友義右を助けた。間も無くして、大聖院宗心が義右の下にやって来て「日田殿の謀反は政親殿の差し金である」と讒言した。此れを信じた義右は激怒し、政親と再び対立した。 | |||
| 1,489 | 1 | 7 |
第28代北野天満宮松梅院院主禅予が、以下の主旨の内容を記し、飯尾為規・清元定の捺印が為される。 壬生家の掘削の件に関し、西京の散所は掘削すべきであるとの御奉書が出された。其処で現地に百姓が派遣されたが難渋した。其の為、年貢の浪費や煩いにはならないと説得し、早く掘削する様下知の仰せが出されたので、此の通り伝達する。 |
|
| 1,489 | 4 | 2 | 山荘造営の一環である「東山殿(現在の京都府京都市左京区銀閣寺町)」が上棟される。 | |
| 1,489 | 4 | 16 | 足利義尚の病が重篤な状態となる。 | |
| 1,489 | 4 | 26 |
10時、足利義尚が、近江国鈎の陣中にて死去する。水と酒しか受け付けない状態であった。義尚は臨終に際し、足利義政に対し以下の辞世の句を詠んだ。 ①ながらへば人の心も見るべきに露の命ぞはかなかりけり (もし長く生きる事が出来れば、他人の心も良く見極められる様になるだろうに、露のような命は儚いものだ) ②もしほ草あまの袖師の裏波にやどすも心あり明の月 (藻塩草が海人の袖を濡らす裏波に宿るように、心にも有明の月のような明るさがある) ③出づる日の余の国までも鏡山と思ひしこともいたづらの身や (昇る日の向こうの遠い国々までも、鏡山の様に美しいと思っていた事も、結局は無駄な身の上だった) 遺体は以下2名に譲られ、凱旋将軍の様な隊列で以って京都に帰還した。 ①細川政元 ②日野富子 其の後日野は、足利義視が出家する事を条件に、足利義稙を次期征夷大将軍に決定した。 |
|
| 1,489 | 5 | 10 | 足利義尚の葬儀が執り行われる。葬儀に際して、遺体の腐臭を防ぐ目的で、口・目・鼻に水銀が注入された。日野富子は、此の葬儀に於いて莫大な資金提供を行い、足利との最後の別れの際、裳階の中で、声を惜しまず咽び泣いた。周囲の者も涙した。其の後足利は等持院に葬られた。義尚の後継として、足利義政が政務に復帰した。 | |
| 1,489 | 5 | 12 | カスティーリャ王国が、クリストファー・コロンブスが王室に謁見する際、宿泊費を王国側で負担する通達を出す。 | |
| 1,489 | 5 | 13 |
以下4名が上洛する。 ①足利義視 ②足利義稙 ③土岐成頼 ④斎藤妙純 元々は足利義尚の葬儀に参列する予定であったが、細川政元の反対に遭い、葬儀後の上洛となった。其の後、義視の娘の居る通玄寺(現在の京都府京都市中京区曇華院前町)に入った。 |
|
| 1,489 | 5 | 19 | 足利義視が、日野富子の住む小川殿に移る。 | |
| 1,489 | 5 | 27 | 足利義視が、通玄寺にて出家する。 | |
| 1,489 | 8 | 12 | 横川景三の勧めで、如意ヶ嶽(現在の京都府京都市左京区鹿ケ谷菖蒲谷町)の山の斜面に白布を持って大文字を作らせ、東求堂から見て字の形を決めて斜面に掘らせた75ヶ所の火床に積み上げた松の割木に一斉に点火し、足利義尚の精霊を送る。此れは五山送り火の始まりとなった。 | |
| ≈ | 1,489 | 9 | 足利義政が、中風を再発させて倒れ、左半身不随となる。 | |
| 1,489 | 11 | 14 |
以下2名が足利義政と対面する。 ①足利義視 ②足利義稙 |
|
| 1,490 | クリストファー・コロンブスの航海計画がエルナンド・デ・タラベラを中心とする諮問委員会で否決される。其の後更にコロンブスは審議を願い出たが、1ヶ月も経たぬ内に否決された。 | |||
| 1,490 | ヴェネツィアで飛脚問屋を営んでいたフランチェスコ・デ・タシス1世がマクシミリアン1世(神聖ローマ皇帝)から命じられ郵便契約を結び、郵便制度を設立し郵便馬車を走らせる。 | |||
| 1,490 | フランチェスコ・デ・タシス1世とフランチェスコの兄ヤネット・デ・タシス、フランチェスコの甥ジョヴァンニ・バッティスタがマクシミリアン1世(神聖ローマ皇帝)から郵便主任を命じられる。さらにマクシミリアン1世(神聖ローマ皇帝)の長男であるフェリペ1世(カスティーリャ王)が、フランチェスコに対しブルゴーニュ(現在のフランスのマルヌ県)とネーデルラント(現在のベルギー、オランダ、ルクセンブルク)物資輸送の機構改革を命じた。 | |||
| 1,490 | 1 | 27 | 足利義政が病死する。足利義視は、其の後の法事の席で「兄弟の仲は元々良かったが、人の言動で疎遠になった。美濃国で私は或る僧を出世させる様要望したが、周囲の僧達に反対された。しかし義政殿が『義視の言う事だから』と反対を押し切った。私は此れを聞いて頷き、一笑した」という主旨の発言をした。義政の遺言により、遺骨は西指庵に納められた。此の時点で東山殿は、内外を黒漆で塗り終えた状態であった。 | |
| ≈ | 1,490 | 3 | 東山殿が完成する。東山山荘全体を寺とし「慈照院」と名付けられた。 | |
| ≈ | 1,490 | 4 | 足利義政の菩提を弔う為に、東山殿を「慈照寺」として禅寺に改められ、相国寺の末寺として創始される。 | |
| 1,490 | 5 | 16 | 日野富子が、小川殿を足利義稙の従兄弟の足利義澄に与える事を決定する。此れにより、日野が細川政元と内談して義澄を征夷大将軍に擁立しようとしているという噂が立った。 | |
| 1,490 | 6 | 6 | 足利義視が小川殿を、日野富子の居室を除き、全て破却する。又足利は、日野の所領も奪った。 | |
| 1,490 | 7 | 22 | 足利義稙が、第10代室町幕府征夷大将軍に就任する。足利義視は准后宣下を受け、政務を担った。其の後義稙は、六角氏が押領していた寺社本所領の返還を条件として六角高頼を赦免し、第27代室町幕府近江国守護として復職させた。 | |
| ≈ | 1,490 | 11 | 六角氏の内衆・国人衆が、寺社本所領の返還を拒否する。此れにより、足利義稙の権威は損なわれた。 | |
| 1,490 | 11 | 19 | 日野良子が死去する。 | |
| ≈ | 1,490 | 12 | 足利義視が腫物を患う。 | |
| 1,490 | 12 | 18 |
以下の人間が文庫の屋根の南側を葺く。 ①静円房 ②三郎五郎 ③七郎三郎 翌日は北側を葺く予定であるとした。 |
|
| 1,490 | 12 | 19 | 文庫の屋根が葺かれる。 | |
| 1,490 | 12 | 21 |
文庫の屋根に、前日に明静房が受け取りに行って持って来た粟田口(現在の京都府京都市東山区・左京区)から買い入れた瓦が載せられる。又、文庫内の棚等を修繕し、番匠が作業に来て、河原者は壁土を塗った。更に、南側の廂等の外側に在った竹垣等が破損していた為、此の日から茂加利を結び始めた。東側は元々茂加利であったが、結び直した。北側の棚も、柱や壁に垂木を入れて補強する為、棚を破却した。櫃も同様に破損していた為、此の日修理が為された。其の後、土が崩れ落ちていたので、土を補充した。文庫の南東や南廂の竹垣が朽ちて壊れ、櫃を十数個取り出した所、文書は湿って損傷していた。又同年、以下2名等の尽力により、葺と板戸の修繕が行われた。 ①宗祇 ②細川政元 |
|
| 1,491 | 1 | 21 | 畠山義就が死去する。 | |
| 1,491 | 2 | 15 |
足利義視が、通玄寺にて死去する。此れにより足利義稙は、後ろ盾を失った。以降以下2名は、足利義澄を征夷大将軍に擁立すべく動き始めた。 ①足利義教の四男足利政知 ②細川政元 |
|
| 1,491 | 5 | 11 | 足利政知が病死する。足利茶々丸は、其のどさくさに紛れ、土牢から脱出した。 | |
| 1,491 | 5 | 29 | 足利義稙が、六角高頼征伐を宣言する。 | |
| 1,491 | 8 | クリストファー・コロンブスがサンタ・マリア・デ・ラ・ラビーダ修道院を訪れ、フアン・ペレス・デ・マルチェーネから、預けていたディエゴ・コロンを引き取り「シャルル8世の援助を取り付けに行く」とマルチェーネに告げる。マルチェーネは考え直す様説得し、イサベル1世に再度請願する様勧めた。又マルチェーネはイサベル1世の側近セバスチャン・ロドリゲス経由で、王室に再検討を促した。イサベル1世はマルチェーネに対し、コロンブスを慰留する事を求めた。更に2週間後、コロンブスの元に王室から「旅金を添えて出頭する様勧告する」主旨の書簡が届いた。航海計画の検討はカスティーリャ枢機院に移管された。 | ||
| 1,491 | 8 | 6 |
足利茶々丸が以下2名を殺害する。 ①足利政知の側室円満院 ②足利潤童子 茶々丸は正室の子であったが、政知の弐男足利義澄と潤童子は円満院の子であった。茶々丸は武力で家督を奪い、第2代堀越公方を宣言した。 |
|
| 1,491 | 9 | 26 | 六角高頼が、観音寺城を捨て、甲賀郡に逃亡する。 | |
| 1,491 | 9 | 30 | 足利義稙が、六角高頼征伐の為、光浄院(現在の滋賀県大津市園城寺町)に布陣する。 | |
| ≈ | 1,491 | 11 | 浦上則宗が、佐々木荘(現在の滋賀県近江八幡市安土町)に着陣する。 | |
| 1,491 | 11 | 2 | 細川政元の家宰安富元家が、金剛寺に入る。 | |
| 1,491 | 12 | 4 | 山内政綱が、六角高頼を裏切り、足利義稙方に寝返る。 | |
| 1,491 | 12 | 19 |
足利義稙が、以下2名に山内政綱征伐を命じる。 ①赤松政則 ②織田敏定 以下2名は大津の浜道場(現在の滋賀県大津市札の辻付近)にて山内を挟撃した。 ①浦上則宗 ③織田 そして山内は降伏した。しかし、足利は此れを許さず、赤松伯耆守によって首を討たれた。 |
|
| 1,492 | 1 | 2 | イベリア半島最後のムスリムの拠点グラナダが、フェルナンド2世(アラゴン王)とイサベル1世(カスティーリャ女王)により陥落される。 | |
| ≈ | 1,492 | 2 | クリストファー・コロンブスがエルナンド・デ・タラベラを中心とする諮問委員会に対し航海計画の再審議を願い出る。しかし1ヶ月も経たぬ内に否決され、其の事実をフェルナンド2世とイサベル1世により知らされ、アラゴン王国へ向けてグラナダを出発した。 | |
| ≈ | 1,492 | 2 | アラゴン王国の財務大臣ルイス・ド・サンタンヘルがイサベル1世と面会し、サンタンヘルは「此の航海計画の援助費用は、此の航海で得られるであろうものに比べると少なく、費用は自分が都合する」と言った。其の後イサベル1世は考えを変え、フェルナンド2世の同意を得て、コロンブスの提案を実施する事を決定した。イサベル1世は急使を送り、1,000,000マラベティを援助するので、コロンブスを呼び戻す様命じた。 | |
| 1,492 | 2 | 25 | 細川政元が、畠山義豊の使者と接触する。 | |
| 1,492 | 3 | フェルナンド2世(アラゴン王)とイサベル1世(カスティーリャ女王)がユダヤ人追放令を出す。少なくとも100,000名のユダヤ人がポルトガルに逃れた。しかし、ポルトガル王ジョアン2世は、僅かな例外を除き、8ヶ月の滞在しか許さず、それを超えて滞在する者は奴隷の身分に落とした。また、フランドル(旧フランドル伯領を中心とする、オランダ南部、ベルギー西部、フランス北部)や地中海沿岸にも散っていった。オスマン帝国はセファルディム(スペイン、ポルトガルに定住していた離散したユダヤ人)の商人たちを歓迎し、積極的に受容した結果、首都イスタンブルやガリラヤ湖畔のサフェドなどにセファルディムの大規模な共同体が形成され、在地のユダヤ人集団を凌駕するようになる。しかも、こうした商人たちは「スルタンの臣民」としてイタリア諸都市にも到来し、地中海商業に大きな役割を果たすようになった。 | ||
| ≈ | 1,492 | 4 |
安富元家が六角高頼方の牢人衆による奇襲を受け、敗走する。此れを受けて足利義稙は、以下の人間に援軍を命じた。 ①赤松政則 ②武田元信 ③斯波義寛 更に、以下の人間が安富の下に派遣された。 ①浦上則宗 ②織田敏定 ③逸見弾正 |
|
| ≈ | 1,492 | 4 | 前年から豊前国にて悪銭が流布している事を背景に、取り締まりを強化する旨のお触れ書きが出される。更に、此れを知らないと申す者が在れば、其処の給主・地下役人の落ち度である為、給地・役職を没収せよと、郡代・段銭奉行に命じ、請書を提出させた。 | |
| 1,492 | 4 | 17 |
クリストファー・コロンブスが、フェルナンド2世及びイサベル1世とサンタ・フェ(現在のスペインのアンダルシア州グラナダ県)にて以下の協約を結び、コロンブスの航海計画が承認され、イサベル1世(カスティーリャ女王)がバックアップする事となった。 ①コロンブスは発見された土地の終身提督となり、此の地位は相続される。 ②コロンブスは発見された土地の副王及び総督の任に就く。 ③各地の統治者は3名の候補をコロンブスが推挙し、此の中から選ばれる。 ④提督領から得られた全ての純利益の内10%はコロンブスの取り分とする。 ⑤提督領から得られた物品の交易に於いて生じた紛争は、コロンブスが裁判権を持つ。 ⑥コロンブスが今後行う航海に於いて費用の1/8をコロンブスが負担する場合、利益の1/8をコロンブスの取り分とする。 そしてルイス・デ・サンタンヘルが中心となってイサベル1世が戴冠用宝玉を担保に供出する事を防ぎつつ資金調達された結果、以下の内訳で航海の為の資金が集まった。 ①サンタンヘル:1,140,000マラベディ ②警察組織サンタ・エルマンダーの経理担当:フランチェスコ・ピネリ:260,000マラベディ ③アラゴン王国:350,000マラベディ ④コロンブス:250,000マラベディ(ルイス・デ・ラ・セルダやセビリアの銀行家ベラルディ等から借金) |
|
| 1,492 | 4 | 25 |
約4,000名の六角氏の牢人衆と以下4名率いる室町幕府軍が、梁瀬河原(現在の滋賀県東近江市五個荘簗瀬町付近)にて交戦する。 ①浦上則宗 ②織田敏定 ③安富元家 ④逸見弾正 室町幕府軍は、7,800名の軍勢で戦った。逸見は武田元信の命で加勢したが、山上に陣取ったまま見物していた。安富は、浦上・織田を凌ぐ活躍を見せた。六角高頼は、飯道寺(現在の滋賀県甲賀市水口町三大寺)へ敗走した。其の後六角は、京極氏館(現在の滋賀県米原市上平寺)を本拠とする京極高清と手を結び、室町幕府軍を撹乱させようとした。 |
|
| 1,492 | 5 | 10 | 今小路が伊勢神宮を参拝する。 | |
| ≈ | 1,492 | 6 |
以下2名が、守山(現在の滋賀県)に着陣する。 ①斯波義寛 ②山名豊時 |
|
| ≈ | 1,492 | 6 | 武田元信が、小南(現在の滋賀県野洲市)に着陣する。 | |
| 1,492 | 8 | 3 |
クリストファー・コロンブス一行87名が、イサベル1世(カスティーリャ女王)の資金提供を受け、以下の3隻の船でパロス・デ・ラ・フロンテーラを出港する。 ①サンタ・マリア号 ②ニーニャ号 ③ピンタ号 |
|
| ≈ | 1,492 | 9 | 26 |
草津にて、武田元信の軍の陣中で以下2名が争う。 ①青地長綱 ②逸見弾正 逸見は討たれかけたが、助けられ、負傷しただけで済んだ。 |
| ≈ | 1,492 | 10 |
京極高清が、以下2ヶ所に出陣する。 ①市原谷(現在の滋賀県甲賀市甲南町市原) ②八風峠口(現在の滋賀県東近江市・三重県三重郡菰野町) |
|
| ≈ | 1,492 | 10 | 赤松政則が、芝原(現在の滋賀県東近江市)に到着する。其の後赤松は、京極高清勢を破り、甲津畑(現在の滋賀県東近江市)へ進軍した。京極勢は北方に退却した。 | |
| 1,492 | 10 | 12 | 未明、クリストファー・コロンブス一行がヨーロッパから大西洋を横断し、サン・サルバドル島(現在のバハマ)に到達する。 | |
| 1,492 | 10 | 26 | クリストファー・コロンブス一行がキューバに上陸する。 | |
| ≈ | 1,492 | 11 | 足利義稙が、三井寺から金剛寺へ向けて進軍する。 | |
| ≈ | 1,492 | 11 | 六角高頼が伊勢国へ逃亡する。しかし其の後、坂下(現在の三重県亀山市関町)にて、北畠材親率いる軍に敗れた。 | |
| 1,492 | 12 | 6 | クリストファー・コロンブス一行が、モール・サン・ニコラ(現在のハイチの北西県)に上陸する。コロンブスは、此の島を「スペインのように美しい」という理由で「イスパニョーラ島」と名付ける。一行は停泊する所々で、先住民タイノ族から歓迎を受けた。 | |
| 1,492 | 12 | 25 | サンタ・マリア号がカパイシャン(現在のハイチの北県)で座礁する。先住民であるマリアン王国のガカナガリック酋長の助けを借りて、サンタ・マリア号を解体し、使える木材と載せていた大砲を使って小さな砦を築き、クリスマスの日にちなんでナヴィダード(誕生)と名付けた。 | |
| 1,493 | 使者が周防国の大内館に派遣される。使者は、文庫等が破損した件に就いて、大内義興に修繕費用の援助を依頼した。 | |||
| 1,493 | 1 | クリストファー・コロンブスが、スペイン王室に航海の報告をする為に、39名のスペイン人を植民として其の砦に残し、インディオを6名連れて、酋長ガカナガリックから受け取った金銭と其の他お土産を持って、ニーニャ号に乗船してスペインへ向けて出発する。 | ||
| 1,493 | 1 | 1 | 足利義稙が、金剛寺の陣を払い、京都へ向けて出発する。 | |
| ≈ | 1,493 | 2 | 畠山政長が、自身の敵対する第17代室町幕府河内国守護畠山義豊の征伐を足利義稙に依頼する。政長は、畠山義就の死を河内国奪回の機会と捉えていた。 | |
| ≈ | 1,493 | 2 | 此の時点で神保長誠は、中風を患い、越中国にて療養を強いられていた。 | |
| 1,493 | 3 | 3 |
足利義稙が、畠山義豊配下の以下2名が寺社本所領を侵略しているとの理由により、畠山義豊征伐の為出陣する。 ①越智家栄 ②古市澄胤 以下の人間等も参陣した。 ①畠山政長(先陣、牧(現在の京都府久世郡久御山町御牧地区)に布陣) ②畠山政長の嫡男畠山尚順 ③畠山政近 ④斯波義寛(後陣、薪(現在の京都府京田辺市薪地区)に布陣) ⑤赤松政則(山崎に布陣) ⑥大内政弘 ⑦大内義興 ⑧武田元信(薪に布陣) ⑨土岐成頼 ⑩葉室光忠(先陣) ⑪細川義春(後陣) ⑫根来寺(現在の和歌山県岩出市根来)衆 義稙は此の日、八幡(現在の京都府)まで進軍し、善法律寺(現在の京都府八幡市八幡馬場)に布陣した。細川政元は、義豊は、畠山義就と異なり、室町幕府に対して表立って敵対的な行動は取っていなかったとして反対し、出陣しなかった。しかし、出陣前の祝宴では義稙を饗応した。伊勢貞宗も反対に回った。同日筒井は、郡山城(現在の奈良県大和郡山市城内町)を落城させた。又、義稙に呼応して福住から筒井党を率いて挙兵した筒井の後見人の成身院順盛は、越智・古市方の小城を次々と落城させた。更に、京都に亡命していた十市遠清も義稙に呼応し、矢田(現在の奈良県大和郡山市)から長安寺(現在の奈良県大和郡山市)に進軍し、十市郷(現在の奈良県橿原市)まで攻勢を掛け矢木市(現在の奈良県橿原市)を焼き払った。対立する大友政親・大友義右に於いては、政親が足利義澄を支持し、義右は義稙を支持した。 |
|
| 1,493 | 3 | 12 | 足利義稙率いる軍が、正覚寺城(現在の大阪府大阪市平野区加美正覚寺)に布陣する。 | |
| 1,493 | 3 | 13 | クリストファー・コロンブス一行がリスボン(ポルトガル)に到着する。 | |
| 1,493 | 3 | 14 | 足利義稙方の斎藤氏が、畠山義豊方との合戦の末、藤井寺に打ち入る。 | |
| 1,493 | 3 | 15 | クリストファー・コロンブス一行がパロス・デ・ラ・フロンテーラに到着する。フェルナンド2世(アラゴン王)とイサベル1世(カスティーリャ女王)に航海の報告を行い、両王は直ちに2度目の航海を促した。 | |
| ≈ | 1,493 | 3 | 17 | 十市遠清が、越智家栄方の反撃に遭い、宇陀(現在の奈良県)に敗走する。 |
| ≈ | 1,493 | 4 | 伊勢貞陸が、第31代室町幕府山城国守護に就任する。 | |
| ≈ | 1,493 | 4 | 1 |
足利義稙率いる軍が、以下を征圧する。 ①野崎城(現在の大阪府大東市野崎) ②犬田城(現在の大阪府枚方市印田町) |
| 1,493 | 4 | 6 | 細川政元の密使が、越智家栄の下を訪れる。細川のクーデター計画を知った越智・古市澄胤は喜んだ。 | |
| 1,493 | 4 | 9 | 葉室光忠が藤井寺に出陣する。 | |
| ≈ | 1,493 | 4 | 9 | 足利義稙方が、雪宮城(現在の大阪府羽曳野市軽里付近)を落城させる。城衆4名を殺害した。 |
| 1,493 | 4 | 12 |
足利義稙方と畠山義豊方の合戦が発生し、以下の畠山方の拠点が焼ける。 ①誉田城 ②道明寺(現在の大阪府藤井寺市) 畠山は、自身の軍勢を高屋城(現在の大阪府羽曳野市古市)に引き入れた。 |
|
| ≈ | 1,493 | 4 | 15 | 足利義稙率いる軍が、畠山義豊の居城である高屋城を包囲し、攻撃を開始する。 |
| 1,493 | 4 | 16 |
此の日の時点で、足利義稙率いる軍の配置は以下であった。 ①足利義稙(正覚寺) ②畠山政長(行基の宮(現在の大阪府羽曳野市古市の白鳥神社付近)) ③畠山尚順(大田若林(現在の大阪府羽曳野市)・野遠(現在の大阪府堺市北区)・野々瀬(現在の大阪府松原市北新町の布忍神社付近)、越中国・安芸国・石見国の衆を率いた) ④遊佐長直(藤井寺) ⑤斎藤・紀伊国の衆(藤井寺の西の野) ⑥斯波義寛(国府(現在の大阪府藤井寺市)) ⑦大内政弘(丹下(現在の大阪府大阪市平野区長吉長原付近)) ⑧赤松政則(南庄(現在の大阪府堺市堺区)) ⑨武田元信(八尾) |
|
| 1,493 | 5 | 7 |
夜、細川政元が、遊初軒(現在の京都府京都市上京区)に足利義澄を迎え入れて保護した上で、挙兵する。更に細川は、以下2点を発表した。 ①足利を征夷大将軍として擁立する ②畠山政長の河内国守護職を罷免する |
|
| 1,493 | 5 | 8 |
細川政元率いる軍が、足利義稙の屋敷や寺院を襲撃する。以下等が破壊された。 ①三宝院 ②曇花院(現在の京都府京都市右京区嵯峨北堀町) ③慈照寺 又、日野富子は細川支持を表明し、義稙に付いていた諸将は、足利義澄に従う様記した伊勢貞宗の密書を受け取った。 |
|
| 1,493 | 5 | 10 |
以下3名率いる軍が堺に入り、細川政元に付く。 ①斯波義寛 ②武田元信 ③細川尚春 |
|
| 1,493 | 5 | 13 | 足利義澄が還俗する。 | |
| 1,493 | 5 | 13 |
以下2名が誉田城に入り、細川政元に付く。 ①赤松政則 ②細川義春 |
|
| ≈ | 1,493 | 5 | 16 |
細川政元が、以下3名を足利義稙・畠山政長征伐の為、河内国に派遣する。 ①細川元治 ②丹波国守護代上原元秀 ③安富元家 |
| 1,493 | 5 | 21 | 畠山政長方の籠城していた廿山城(現在の大阪府富田林市)が落城する。 | |
| ≈ | 1,493 | 5 | 21 |
大和国の畠山政長方の国人である以下が、相次いで自焼没落する。 ①筒井氏:筒井城(現在の奈良県大和郡山市筒井町)を自焼し、東山内(現在の奈良県山辺郡山添村・宇陀郡曽爾村・宇陀郡御杖村・宇陀市・奈良市柳生町・生駒市東山町・桜井市)へ没落 ②十市氏:十市城(現在の奈良県橿原市十市町)を自焼し、東山内へ没落 ③箸尾氏:箸尾城(現在の奈良県北葛城郡広陵町弁財天)を自焼し、多武峰へ没落 |
| 1,493 | 5 | 21 |
此の日から2日間、藤井寺にて、足利義稙方と細川政元方の間で戦闘となる。結果、以下2名は畠山尚順を破った。 ①上原元秀 ②安富元家 尚順は、正覚寺城へ退却し、以下の人間等と合流した。 ①足利義稙 ②畠山政長 ③遊佐長直 |
|
| 1,493 | 6 | 3 | 根来寺衆を率いる足利義稙方の斎藤氏が、正覚寺城に到着する。正覚寺城南口に構えていた安富元家方の誉田氏は、直様斎藤氏の下へ向かった。 | |
| 1,493 | 6 | 5 | 赤松政則率いる軍が、堺付近にて根来寺衆を破る。 | |
| ≈ | 1,493 | 6 | 5 | 上原元秀率いる軍が、天王寺から正覚寺城の西に進軍し、足利義稙方と合戦する。其の後上原は、天王寺木村邊に戻り、逗留した。 |
| 1,493 | 6 | 6 |
細川政元が派遣した以下2名率いる40,000名の軍勢が、畠山政長等が籠城する足利義稙の本陣である正覚寺城を包囲する。 ①畠山義豊 ②赤松政則 |
|
| 1,493 | 6 | 6 | 上原元秀が、畠山義豊から河内国17ヶ所を拝領する。 | |
| 1,493 | 6 | 8 |
夕方、以下2名率いる軍が、正覚寺城に総攻撃を仕掛ける。 ①畠山義豊 ②赤松政則 |
|
| 1,493 | 6 | 9 |
正覚寺城が落城する。畠山政長は、畠山尚順を紀伊国へ逃した上で切腹した。政長の部下の越中衆も後に続いた。尚順は虎口を脱出し、紀伊国で再挙を図る事となった。遊佐長直は討ち取られ、以下2名は捕縛され、上原元秀に降伏した。 ①足利義稙 ②葉室光忠 越中国の神保家・椎名家は、此の政変により打撃を受けた。 |
|
| 1,493 | 6 | 13 | 上原元秀が、細川政元の命により、葉室光忠を処刑する。 | |
| 1,493 | 6 | 15 | 上原元秀が、足利義稙を伴い京都へ帰還する。此の際足利は、古い板輿に乗せられ、6名の近臣を付ける事しか許されなかった。そして足利は、多数の見物人の居る中で、龍安寺(現在の京都府京都市右京区龍安寺御陵ノ下町)に幽閉された。 | |
| 1,493 | 6 | 19 | 夜、足利義稙の夕食に毒が盛られる。毒を盛らせたのは日野富子であった。食した足利は、苦悶の末、薬によって一命を取り留めた。 | |
| ≈ | 1,493 | 7 |
足利義澄が、以下2名の敵討ちとして、足利茶々丸の近くに城を持つ北条早雲に対し、茶々丸征伐を命じる。 ①円満院 ②足利潤童子 北条は下調べを行い、茶々丸が横暴を振るい、足利政知の時からの堀越公方の重臣達と上手くいっておらず、領民が疲弊している事や、堀越御所(現在の静岡県伊豆の国市四日町字御所ノ内)の内情を掴み、内部工作を行なった。 |
|
| ≈ | 1,493 | 7 | 越智家栄が、細川政元方に味方した功により伊賀守に任じられる。 | |
| 1,493 | 7 | 1 | 足利義稙の身柄が、龍安寺から上原元秀の屋敷に移される。 | |
| ≈ | 1,493 | 7 | 2 |
畠山義豊が、以下の人間を始めとする2,000名余を率いて上洛する。 ①遊佐就家 ②誉田正康 ③甲斐庄氏 |
| 1,493 | 7 | 4 | 畠山義豊が室町幕府に出仕し、第17代室町幕府河内国守護に就任する。同時に、越智氏も1,000名余を率いて上洛し、室町幕府に出仕した。 | |
| 1,493 | 7 | 24 | 細川政元等により、足利義稙の小豆島への配流が決定される。 | |
| 1,493 | 8 | 11 | 夜、嵐の中、数名の近臣を連れた足利義稙が、神保長誠の配下の手配により、上原元秀の屋敷から脱走し、京都を脱出する。其の後足利は、近江国を経由して越中国へ下向し、放生津(現在の富山県射水市)にて神保長誠に迎えられた。神保は、同地の正光寺を改装し、将軍の御座所とした。斯うして足利が樹立した政権は「越中公方」と呼ばれた。以降神保は、細川政元方の畠山基家の越中国侵攻を何度も撃退し、軍事力を誇示する一方、金や献上品を京都に送り、足利の征夷大将軍復帰に尽力した。 | |
| 1,493 | 9 | 25 | クリストファー・コロンブスが17隻1,500名でイスパニョーラ島を植民地にする為に、カディス(現在のスペインのアンダルシア州)を出港する。今回はコロンブスの父ペドロ・デ・ラス・カサス、バルトロメ・デ・ラス・カサスも同行した。 | |
| ≈ | 1,493 | 10 | クリストファー・コロンブス一行が小アンティル諸島中の一島に上陸し「ドミニカ島」と命名する。 | |
| ≈ | 1,493 | 10 |
北条早雲が、自身の居城である興国寺城(現在の静岡県沼津市根古屋)にて足利茶々丸征伐の作戦を練る。そして、以下からの援軍を得て、足利潤童子を支持していた伊豆国人を味方に付け、500名の軍勢で出陣した。 ①今川氏親 ②葛山氏 ③上杉定正 |
|
| ≈ | 1,493 | 10 | 11 | 越中国の足利義稙勢が、細川政元の派遣した軍勢を破る。此れにより足利は、越中国全域を掌握し、周辺の諸将からの支持を集め、九州の大友政親等の遠方の大名も支持した。 |
| 1,493 | 10 | 17 |
伊勢貞陸によって、古市澄胤が以下2ヶ所の守護代に任じられる。 ①綴喜郡 ②相楽郡 此れによって古市は、山城国を攻撃する大義名分を得た。 |
|
| 1,493 | 10 | 21 | 古市澄胤が、山城国への侵攻を開始する。越智氏と古市氏の不和により、古市氏の単独侵攻となった。 | |
| 1,493 | 10 | 27 | 古市澄胤が、惣国の解体と守護による統治に反対する山城国人衆の籠城する稲八妻城(現在の京都府相楽郡精華町北稲八間城山付近)を陥落させる。 | |
| 1,493 | 11 | クリストファー・コロンブス一行がイスパニョーラ島に上陸する。其の後、金の採掘の為にタイノ族を酷使し、抵抗する者を虐殺した。数十万から百万名程いた同島のタイノ族は50年後には数百名に減少し、後に絶滅した。 | ||
| 1,493 | 11 | クリストファー・コロンブス一行が前回の航海での植民39名が全滅していた為、モンテ・クリスティ(現在のドミニカ)の近くに植民地を再建し「イサベラ」と名付ける。其の後金鉱とアジアへの経路の探索を開始した。 | ||
| ≈ | 1,493 | 11 | 19 | 北条早雲率いる軍が、伊豆国の兵が手薄になるタイミングを計って堀越御所を夜襲する。足利茶々丸は、上杉顕定や上杉を支持する伊豆国人等と共に応戦した。北条は戦いを優位に進め、足利は堀越御所を捨て、守山(現在の静岡県伊豆の国市中條付近)方面に逃亡した。北条は、韮山城(現在の静岡県伊豆の国市韮山)を居城に定めた。 |
| 1,493 | 12 | 22 | 大友親繁が死去する。 | |
| 1,494 | 越智家栄が修理大夫に任じられる。 | |||
| 1,494 | 3 | 5 |
官務壬生晴富が以下の主旨の内容を記す。 文庫の修繕を行うに当たり、従来は諸国からの段銭・棟別銭或いは御倉からの納銭・御物の寄付等によって、毎回厳重な対応が為されて来ました。しかし近年、其の様な措置が十分に行われず、土壁が崩れ落ち、庫内の柱が腐って朽ち、外からも内からも透けて見える状態となり、文書は日を追う毎に朽ちて損傷していました。西暦1,494年2月20日に強風が吹き、仮屋が倒れてしまった為、風雨により益々漏湿が酷くなり、言葉に尽くせない程の惨状です。諸家の文籍は全て紛失し、文庫に残された物は天下の明鏡として備えておくべき物であったにも拘らず、此の様な事態に至って滅失してしまうのは、誠に嘆かわしい限りです。 |
|
| 1,494 | 6 | 金鉱とアジアへの経路を探索していたクリストファー・コロンブス一行が、成果を上げる事が出来ず引き返す。 | ||
| ≈ | 1,494 | 6 | 大友政親派の重臣で筑後国詰郡代の田原親宗が、府内(現在の大分県大分市)に侵攻する。大友義右を追放するのが狙いであった。しかし義右は此れを撃破し、田原は敗走した。 | |
| ≈ | 1,494 | 9 | 30 | クリストファー・コロンブス一行がイサベラに上陸する。しかし植民同士が仲違いしていた。 |
| ≈ | 1,494 | 10 | 大内政弘が、中風の悪化により、大内義興に家督を譲り隠居する。 | |
| 1,494 | 10 | 20 |
足利義稙が、放生津城(現在の富山県射水市中新湊)に移り挙兵する。以下2名の打倒を宣言し、全国の諸将に檄を飛ばした。 ①足利義澄 ②細川政元 そして、以下の人間が呼応した。 ①畠山義統 ②朝倉貞景 ③上杉房定 ④富樫稙泰 ⑤大友政親 |
|
| ≈ | 1,494 | 11 | 細川義春が、山城国人衆を味方に付け、伊勢貞陸を山城国守護職から追い落とそうとする。細川政元は此れを認めなかったが、古市氏による南山城支配が揺らぎ始めた。 | |
| 1,494 | 11 | 2 | 上杉定正が、荒川を渡河しようとした際に落馬して死去する。 | |
| 1,494 | 12 | 25 | 細川政元に山城国守護職就任を阻まれ怒った細川義春が、阿波国に向けて京都を出発する。 | |
| 1,495 | 1 | 16 | 足利義澄の元服の儀が執り行われる予定であったが、加冠役の細川政元が烏帽子を被る事を嫌がった為、足利は花の御所で1日中待たされ、西暦1,495年1月23日に延期となった。 | |
| 1,495 | 1 | 17 | 細川義春が病死する。 | |
| 1,495 | 1 | 23 | 大内氏から3,000疋が、相国寺大智院競秀軒に届けられる。 | |
| 1,495 | 1 | 23 | 5時、足利義澄の元服の儀が執り行われ、朝廷からの将軍宣下により、足利が第11代室町幕府征夷大将軍に就任する。細川政元は第29代管領に就任し、政所執事の伊勢貞宗と共に、若年である足利に代わり政務を担った。 | |
| 1,495 | 2 | 10 | 台風により、文庫の仮屋が破損する。其の為、文書を雨や露から守る為の修繕が行われた。 | |
| 1,495 | 3 | 24 | 大内義興が、内藤弘矩を大内政弘の屋敷にて殺害する。又同日、弘矩の嫡男の内藤弘和も、義興の差し向けた兵により殺害された。弘矩・弘和勢力の拡大を恐れた陶弘護の嫡男陶武護が「弘矩が大内高弘の擁立を画策している」と義興に讒言していた。後に義興は真相を暴き、武護を誅殺した。 | |
| ≈ | 1,495 | 4 | 畠山義豊が紀伊国に進軍する。此れに呼応して、畠山に与する以下が挙兵し、田辺(現在の和歌山県)に乱入した。此れにより、鬪雞神社(現在の和歌山県田辺市東陽)の社壇が破壊された。 | |
| 1,495 | 7 | 1 | 畠山尚順方の奥郡(紀伊国の熊野)小守護代野辺六郎右衛門率いる軍が、田辺に進軍する。愛洲構(現在の和歌山県田辺市中三栖の衣笠城)を攻略した。 | |
| 1,495 | 7 | 4 | 野辺六郎右衛門率いる軍が、愛洲構(現在の和歌山県田辺市中三栖の衣笠城)を攻略する。 | |
| 1,495 | 8 | 8 | 相国寺大智院競秀軒の人間が、細川政元の命により、近日中に周防国へ向かう事となる。此の機会に競秀軒の書簡が文主座に送る事となった。大内在京雑掌が関与していた。 | |
| 1,495 | 10 | 25 | マヌエル1世がポルトガル王に即位する。すぐにユダヤ人を奴隷身分から解放した。 | |
| ≈ | 1,495 | 12 | 畠山義豊の家臣である遊佐弥六が、山城国守護を名乗り南山城に進駐する。第20世大乗院門主尋尊は、此の遊佐の行動を、古市氏を援護する為ではないかと推測した。 | |
| 1,496 | マヌエル1世が、イサベル1世(カスティーリャ女王)の娘のイザベル・デ・アラゴン・イ・カスティーリャを妃に迎えるに当たり、スペイン側はポルトガル領内でのユダヤ教徒追放を求め、マヌエル1世がこれに応じる。結果、ポルトガルでキリスト教以外の宗教儀式は違法となり、ユダヤ人に対しては追放令が出される。 | |||
| 1,496 |
以下2名の不和が再び表面化する。 ①大友政親 ②大友義右 原因としては、少弐家対大内家の争いや、足利義稙の催促に如何に対応するか、といった点での意見の対立であったが、此れは以下の人間の工作によって引き起こされた。 ①大聖院宗心 ②市河親清 ③内宮内助 ④田北七郎兵衛 ⑤田原中務丞 ⑥小原新四郎 |
|||
| 1,496 | 3 | クリストファー・コロンブスがバルトロメ・デ・ラス・カサスを副総督としてイスパニョーラ島に残し、コロンブス一行225名がインディオ30名を連れて、帰国の為出港する。 | ||
| ≈ | 1,493 | 3 | 此の頃、大友義右は軍船の建造を進めていた。 | |
| ≈ | 1,496 | 5 |
壬生晴富が以下の内容を記す。 文庫の破損と修理の件に就いて、近年資金不足の為、修繕を行う事が出来ず、日を追う毎に朽ちて損傷が進んでいます。此の為、後土御門天皇が足利義澄殿に勅命を出し、足利殿も費用の徴収を命じましたが、捻出する事は出来ませんでした。又、文庫の仮屋は先日の大風雨で破損した後、まだ修繕されていない為、漏湿が酷く、言葉に尽くせない程の惨状です。 |
|
| ≈ | 1,496 | 5 |
壬生晴富が、文庫の破損と修理の件に就いて記した翌日、文庫の屋根の葺き替えに就いて申し付ける。 ①清元定 ②波々伯部氏 |
|
| ≈ | 1,496 | 5 | 大友義右が病を発症する。 | |
| ≈ | 1,496 | 6 | 此の時点でまだ文庫の修繕が為されておらず、風雨による漏湿が酷い状態であった。 | |
| 1,496 | 6 | 13 | 大友政親が、筑前国へ逐電する。 | |
| 1,496 | 6 | 23 | 大友政親が、北九州の大内領侵攻の為挙兵し、立花山城(現在の福岡県福岡市東区下原)を目指し、豊後国臼杵から出航する。しかし、船は遭難し、赤間関に流され、大内義興の家臣杉信濃守に捕えられて舟木地蔵院(現在の山口県宇部市船木)に幽閉された。 | |
| 1,496 | 7 | 7 | 大友義右が、後継者の居ない儘病死する。此の際、大友政親が義右を毒殺したとの噂が流れた。 | |
| ≈ | 1,496 | 7 | 大内義興が、大友政親が大友義右を毒殺したとの話を聞いて激怒し、政親征伐の兵を差し向ける。 | |
| 1,496 | 7 | 20 | 大友政親が、舟木地蔵院にて切腹に追い込まれる。伴衆18名も後を追って自害した。 | |
| 1,496 | 8 |
大友親治率いる軍が、大友氏館(現在の大分県大分市顕徳町)にて、大内義興が大聖院宗心を大友家当主に擁立しようとする動きに加担した以下の重臣等を鎮圧する。 ①市川親清 ②朽網繁貞 此の戦いで両軍合わせて約500名が戦死した。此れにより大友は、大聖院の家督継承を阻止し、第18代大友家当主に就任した。 |
||
| 1,496 | 9 |
細川政元が、赤沢朝経を南山城へ派遣する。以下に対して圧力を掛けた。 ①畠山氏 ②古市氏 |
||
| 1,496 | 9 | 18 | 文庫の仮屋の葺き替えを行い、適切に取り計らう様指示が出る。 | |
| 1,496 | 9 | 20 | 文庫の仮屋の葺き替えに関し、上葺が完了する。雨の中でも作業を行い、3日間で完了した。 | |
| 1,496 | 10 | 6 | 壬生晴富が町広光に対し、文庫の漏湿に関し報告する。 | |
| ≈ | 1,496 | 11 |
以下が南山城から撤退する。 ①畠山氏 ②古市氏 |
|
| 1,496 | 12 | 26 |
少弐政資が、以下2名の援軍を伴い、筑前国へ侵攻する。 ①大友政親 ②大友親治 大内家の領地を攻撃し、旧領回復を狙った。第72代宗像大宮司氏佐の下に在った重代の宝物を強奪し、肥前国青山城(現在の佐賀県唐津市山本)主留守氏を追放した。更に少弐率いる軍は、以下等で防戦する河津氏等の筑前国人衆を攻撃した。 ①飯盛山城(現在の福岡県福津市内殿) ②高鳥居城(現在の福岡県糟屋郡篠栗町若杉) |
|
| 1,497 | ヴェネツィア共和国が、元老院令により、マラーノ(イベリア半島で止む無くキリスト教に改宗したユダヤ人の蔑称)に対し2ヶ月以内の退去とその間の商業取引の禁止を規定し、マラーノと取引したヴェネツィア商人に対し、罰則規定を設ける。 | |||
| 1,497 | 初代テューダー朝王ヘンリー7世公認の下、ジョン・カボット、セバスチャン・カボット親子が、ブリストル港の商人の資金によってアジアへの航路探検に出発する。 | |||
| ≈ | 1,497 | 1 | 大内義興が、室町幕府から少弐家の征伐を命じられる。 | |
| 1,497 | 1 | 16 |
大内義興が、以下の人間を始めとする20,000騎余を率いて、九州へ向けて出陣する。 ①陶興房(大将) ②吉見頼興 ③熊谷膳直 ④小早川弘平 ⑤仁保護郷 ⑥杉弘依 ⑦内藤氏 |
|
| 1,497 | 3 | 19 | マヌエル1世が、ポルトガル国内に在住する全ユダヤ教徒に対し、形式的なキリスト教への強制改宗を行い、内心での信仰の調査は20年間猶予する事となった(後に延長され、マヌエル1世の治世下では調査は行われていない)。商業、金融業で主要な役割を果たし、また医師などの知的専門職や職人となっている者も多いユダヤ人を追放する事は、ポルトガルの経済的損失である為彼らを国内に引き留める為に行った。しかし、マラーノと呼ばれ差別を受ける事となり、14歳未満の子は親許から引き離され、キリスト教徒の家庭に里子に出す事が義務付けられた。 | |
| ≈ | 1,497 | 4 | 三条西実隆が、文庫の破損に就いて後土御門天皇に奏聞する。後土御門天皇は、修繕の詳細や方法に就いて尋ねる様指示した。三条西は、内々に押小路師富経由で申し付けた。 | |
| ≈ | 1,497 | 4 | 大内義興率いる軍が、筑前国へ侵攻する。 | |
| 1,497 | 4 | 15 |
少弐政資の息子少弐高経が、大内義興率いる軍が博多に到着して陣を固めようとした隙を突いて奇襲し、先鋒の杉興正を討ち取る。しかし直ぐに、二陣の陶興房・熊谷膳直等が入れ替わり、聖福寺(現在の福岡県福岡市博多区御供所町)にて、以下3名率いる軍と大内率いる軍の間で戦闘となった。 ①少弐政資 ②大友政親 ③大友親治 大内側は、陶が先鋒となり、圧倒的な兵力で攻勢を掛け、少弐・大友父子率いる軍を撃破した。少弐・大友父子率いる軍は、太宰府方面へ敗走した。 |
|
| 1,497 | 4 | 17 |
退却中であった以下3名率いる軍が、追撃して来た大内義興率いる軍と、筑紫村(現在の福岡県筑紫野市)にて戦闘となる。 ①少弐政資 ②大友政親 ③大友親治 大内率いる軍は、2日前と同じく少弐・大友父子率いる軍を破り、少弐方国人・河津氏等が守備する高鳥居城を落城させた。少弐・大友父子率いる軍は、肥前国へ逃亡した。大内の軍勢は50,000騎余まで膨れ上がり、勢いに乗って筥崎宮(現在の福岡県福岡市東区箱崎)付近まで進軍した。 |
|
| ≈ | 1,497 | 4 | 18 |
以下2名が、相談の上、軍を二手に分ける。 ①少弐政資(岩門城(現在の福岡県那珂川市山田)) ②少弐高経(勝尾城(現在の佐賀県鳥栖市牛原町)) 政資は岩門城に籠城し、高経も勝尾城に入って大内義興勢を待ち構えた。 |
| ≈ | 1,497 | 4 | 19 |
大内義興が、太宰府を本陣とし、以下の軍を差し向ける。 ①陶弾正忠(岩門城、兵20,000名) ②陶興房・右田弘詮(勝尾城、兵20,000名) |
| ≈ | 1,497 | 4 | 20 | 陶弾正忠率いる軍が、岩門城を攻撃する。少弐家10名余が討死し、雑兵も大半が討たれ、落城した。少弐政資は密かに岩門城から出て、千葉胤資の居る晴気城(現在の佐賀県小城市小城町畑田)へ逃亡した。 |
| ≈ | 1,497 | 4 | 23 |
以下2名率いる軍が、勝尾城を攻撃する。 ①陶興房 ②右田弘詮 守備していた城兵は討ち負け、少弐高経は勢福寺城(現在の佐賀県神埼市神埼町城原)へ落ち延びた。 |
| 1,497 | 4 | 25 | 大内義興率いる軍が、朝日山城(現在の佐賀県鳥栖市村田町)を攻撃し、此れを攻略する。 | |
| ≈ | 1,497 | 5 | 5 |
第13代江上家当主で勢福寺城主の江上興種が、大内義興方と内通する。少弐高経は此れを把握すると、江上を勢福寺城から追放した。此の江上の裏切りにより、勢福寺城は、以下2名率いる軍によって容易く落とされた。 ①陶興房 ②右田弘詮 高経は、少弐政資の居る晴気城へ向かった。 |
| ≈ | 1,497 | 5 | 10 | 少弐高経が、晴気城へ入り、少弐政資と合流する。 |
| 1,497 | 5 | 15 | 千葉興常勢等の大内義興方が、晴気城を攻撃する。千葉胤資は防ぎ切れないと考え、少弐政資に、政資の側室の父である、梶峰城(現在の佐賀県多久市多久町)主多久宗時を頼る様申し出た。 | |
| 1,497 | 5 | 16 | 大内義興率いる軍が、少弐政資の居城である小城城を包囲する。 | |
| 1,497 | 5 | 18 |
一旦山口に戻っていた大内義興が、以下の周防国の一宮から五宮の神社に参詣して、戦勝祈願する。 ①一宮:玉祖神社(現在の山口県防府市切畑) ②二宮:出雲神社(現在の山口県山口市徳地堀) ③三宮:仁壁神社(現在の山口県山口市三の宮) ④四宮:赤田神社(現在の山口県山口市吉敷) ⑤五宮:朝田神社(現在の山口県山口市矢原) 神馬の寄進も行い、其の後小城城を包囲している自軍へ帰還した。 |
|
| 1,497 | 5 | 20 |
夜、千葉胤資が、以下3名を晴気城から逃す。 ①少弐政資 ②政資の嫡男少弐頼隆 ③少弐高経 |
|
| 1,497 | 5 | 20 | 小城城が落城する。 | |
| 1,497 | 5 | 21 | 少弐頼隆が、千葉興常勢に討たれる。 | |
| 1,497 | 5 | 21 | 千葉胤資が、晴気城から打って出るも、討死する。其の後晴気城は落城した。 | |
| 1,497 | 5 | 21 | 少弐政資が、梶峰城に到着する。少弐は、多久宗時に匿って欲しい旨を伝えた。大内義興方の追撃を恐れた多久は此れを拒否し、自害を勧めた。そして少弐は、専称寺(現在の佐賀県多久市多久町)境内で切腹した。 | |
| 1,497 | 5 | 23 | 落ち延びる途上で追手に市の川(現在の佐賀県小城市牛津町地区)で追い付かれた少弐高経が、最早逃れ得ぬと考え、市の川の山中にて切腹する。 | |
| ≈ | 1,497 | 5 | 大内義興が、千葉興常を肥前国守護代に任じる。 | |
| ≈ | 1,497 | 5 |
以下2名等が、大内義興に降伏する。 ①筑紫満門 ②東尚盛 |
|
| ≈ | 1,497 | 5 |
大内義興が、以下3名に対し処置を行い、山口に帰陣する。 ①筑紫満門(三根郡(現在の佐賀県三養基郡上峰町・みやき町)と神埼郡(現在の佐賀県佐賀市・神埼市・神埼郡吉野ヶ里町)の守備を命じる) ②東尚盛(佐賀郡(現在の佐賀県佐賀市)を与える) ③陶弾正忠(博多に配置) |
|
| ≈ | 1,497 | 5 | 大内義興が、朝廷から太宰少弐に任じられる。 | |
| 1,497 | 5 | 30 | フェルナンド2世(アラゴン王)がルイス・デ・サンタンヘルを保護する。サンタンヘルがキリスト教に改宗したユダヤ人の孫であった為、スペイン異端審問によりサンタンヘルを排斥する動きがあった。 | |
| 1,497 | 7 | 8 | マヌエル1世の命により、ヴァスコ・ダ・ガマが、大勢の観衆が見守る中、聖母修道院の修道士が執り行うミサの後、サン・ガブリエル号という船で、リスボンを出港する。 | |
| ≈ | 1,497 | 7 | 29 |
以下2名の間で和平交渉が開始される。 ①足利義稙 ②細川政元 足利側は、神保長誠を中心に交渉を進め、神保の家臣倉川兵庫助が上洛して、工作費として、数千貫を各方面に散蒔いた。 |
| ≈ | 1,497 | 8 |
畠山義豊の家臣団である以下に内紛が発生する。 ①遊佐氏 ②誉田氏 畠山尚順は此れに乗じ、河内国に進軍し、筒井党の以下2名も尚順に呼応して、大和国に帰還した後に挙兵した。 ①成身院順盛 ②筒井順賢 |
|
| 1,497 | 8 | 12 | 倉川兵庫助が、細川政元の屋敷を訪れる。工作の甲斐有って倉川は、細川との和平交渉に漕ぎ着けた。其の後吉見義隆も、足利義稙方として交渉に当たった。しかし最終的に、細川政賢の反対に遭い、交渉は決裂した。 | |
| ≈ | 1,497 | 10 |
畠山尚順が、河内国奪回の為挙兵する。畠山は、以下が対立しているのを好機と捉え挙兵に踏み切った。 ①遊佐氏 ②誉田氏 此れを受けて細川政元は、赤沢朝経を南山城に派遣し、古市澄胤に代わる守護代とした。 |
|
| 1,497 | 11 | ヴァスコ・ダ・ガマがアフリカ大陸南端の喜望峰を超える。 | ||
| ≈ | 1,497 | 11 |
各地で合戦に及んでいた以下が敗退する。 ①筒井党 ②古市氏 ③越智氏 今市(現在の奈良県奈良市)の越智氏代官や堤氏は敗走し、以下の越智党の主要国人達も自焼没落した。 ①小泉氏 ②竜田氏 此れにより筒井氏は、西暦1,477年に畠山義就によって奪われた大和国の本領を奪還した。 |
|
| 1,497 | 11 | 2 |
畠山尚順が、高屋城(現在の大阪府羽曳野市古市)を落城させる。此れにより尚順は、河内国の大半を奪回した。此れを受けて畠山義豊は山城国へ逃亡し、足利義澄は、以下の奉公衆に対して、尚順を攻撃する様御内書を発した。 ①湯河氏 ②玉置氏 ③山本氏 しかし湯河氏は、畠山方であった為御内書を無視した。 |
|
| 1,497 | 11 | 2 |
成身院順盛が、越智郷(現在の奈良県高市郡高取町)に侵攻する。以下2名は壷阪寺(現在の奈良県高市郡高取町壷阪)に逃れ、越智郷は戦火に包まれた。 ①越智家栄 ②家栄の嫡男越智家令 |
|
| ≈ | 1,497 | 12 |
十市遠治が壷阪寺を攻撃する。以下は此れに応戦し、退けた。 ①越智家栄 ②越智家令 十市は以下2名に援軍を要請した。 ①成身院順盛 ②畠山尚順 畠山は此の要請に応じ、河内国から万歳平城(現在の奈良県大和高田市市場)に入った。此れを受けて家栄・家令は吉野に逃亡した。万歳氏の所領を奪取した畠山は、其れを自身の馬廻衆に恩賞として与えた。大和国の荘園が他国の衆に与えられたのは此れが初めてで、興福寺は大変な衝撃を受けた。 |
|
| 1,497 | 12 | 7 |
古市澄胤が、300名余の兵を率いて白毫寺(現在の奈良県奈良市白毫寺町)付近に布陣し、以下の大和国人を率いる1,000名の筒井氏率いる軍を迎撃する。 ①超昇寺(現在の奈良県奈良市山陵町) ②秋篠(現在の奈良県奈良市) ③宝来(現在の奈良県奈良市) 結果、筒井氏は大勝し、古市は伊賀国へ逃亡した。斯うして、西暦1,477年以降続いた越智氏・古市氏と筒井党の力関係は逆転した。 |
|
| ≈ | 1,498 | 3 | 興福寺の学侶・六方衆の集会が開かれ、畠山尚順が自身の馬廻衆に万歳氏から奪った所領を与えた件に就いて議題に挙がる。尋尊は「神国大和に武家の家臣が領地を持つなど前代未聞だ」と怒りを込めて記した。 | |
| ≈ | 1,498 | 3 |
吉見義隆が活動を活発化させる。以下2名の下に赴き、双方に対して和平交渉を重ねた。 ①細川政元 ②畠山尚順 公家達は、足利義稙が京都に戻ると予測し、吉見に贈り物を送り、接近した。一方、足利方の和平反対派の種村視久は、家臣の杉川平左衛門を派遣して尋尊に足利の意向を伝え、交渉を妨害する工作を展開した。 |
|
| 1,498 | 5 | 20 | ヴァスコ・ダ・ガマがポルトガルの援助を受けて、インドのコーリコードに到着。 | |
| 1,498 | 5 | 30 | クリストファー・コロンブス一行がサンルーカル・デ・バラメーダ(現在のスペインのアンダルシア州カディス県)を出港する。 | |
| ≈ | 1,498 | 7 | クリストファー・コロンブス一行が現在のベネズエラのデルタアマクロ州のオリノコ川の河口に上陸する。 | |
| ≈ | 1,498 | 7 | 吉見義隆が和平を実現する事が出来ない儘、越中国へ帰国する。双方共に反対派の声を無視出来ず、細川政元側は、細川政賢が再び強く反対した。 | |
| 1,498 | 7 | 30 | クリストファー・コロンブス一行が小アンティル諸島最南端の島を発見し「トリニダ」と名付ける。 | |
| 1,498 | 9 | 11 | 南海トラフを震源とする明応地震が発生する。被害は会津から京都まで広範囲に及び、推定マグニチュードは8.2〜8.4であった。特に東海道一帯で甚大な被害を出し、5,000名以上が死亡した。大半は津波による犠牲者であった。北条早雲は救済の為、駿河国清水から西伊豆へ向かった。 | |
| ≈ | 1,498 | 9 | 北条早雲が下田を攻撃する。足利茶々丸は、身柄を武田方から北条方に引き渡された上で、深根城(現在の静岡県下田市堀之内)にて切腹した。 | |
| ≈ | 1,498 | 9 | 足利義稙が改名を行う。 | |
| 1,498 | 9 | 12 | 六角氏が、芦浦観音寺(現在の滋賀県草津市芦浦町)に毎月の代参と坂本への御用を命じるに当たり、諸関奉行・志那渡(現在の滋賀県草津市志那町付近)宛の過所を発給する。 | |
| ≈ | 1,498 | 10 | 足利義稙が、軍事協力の得られない越中国に見切りを付け、越前国の朝倉貞景を頼り、一乗谷に入る。此れにより、越中公方は事実上崩壊した。 | |
| 1,498 | 11 | 9 | 吉見義隆が、越中国にて切腹する。足利義稙が、吉見が細川政元方と過度な接触を行なっていた事を理由に内通を疑い、切腹に追い込まれた。 | |
| 1,499 | ヴァスコ・ダ・ガマが香辛料をポルトガルに持ち帰る。 | |||
| 1,499 | 3 | 4 | 山名政豊が死去する。 | |
| 1,499 | 3 | 11 | 畠山基家が、河内国17ヶ所付近で畠山尚順方に攻撃され、戦死する。 | |
| 1,499 | 5 | 5 | 蓮如が入滅する。 | |
| 1,499 | 10 | 9 |
以下2名率いる軍が、山城国飯岡(現在の京都府京田辺市)に着陣する。 ①足利義稙 ②畠山尚順 |
|
| ≈ | 1,499 | 10 | 10 | 薬師寺元一が、細川政元の命を受け、誉田城主畠山義英の救援の為出陣する。 |
| 1,499 | 10 | 14 | 畠山尚順率いる軍が、誉田城を孤立させる事を意図し、木幡(現在の京都府宇治市)まで進軍する。此の軍は、畠山が動員した、河内国から筒井氏や十市氏等の大和国人衆で構成されていた。畠山は、河内国を征圧して上洛するという算段を立てていた。そして畠山率いる軍は、赤沢朝経率いる軍と交戦した。赤沢勢が優位に戦いを進めた。 | |
| 1,499 | 10 | 30 | 赤沢朝経率いる軍が、西一口城(現在の京都府久世郡久御山町西一口)を焼き払う。 | |
| 1,499 | 10 | 31 | 赤沢朝経率いる軍が、真木島氏の居城である槇島城(現在の京都府宇治市槇島町薗場)を落城させ、複数名の首級を挙げる。京都府城陽市水主北垣内 | |
| 1,499 | 11 | 1 | 赤沢朝経率いる軍が、水主城(現在の京都府城陽市水主北垣内)を落城させる。此れにより赤沢は、南山城一帯の征圧を完了した。此れにより畠山義英は、誉田城を守り、総州家を存続させた。 | |
| ≈ | 1,499 | 12 | 西陣南帝が、伊豆国三島に流れ着く。北条早雲は、西陣南帝を諌めて相模国に向かわせた。 | |
| ≈ | 1,499 | 12 | 足利義稙が、越前国府中(現在の福井県越前市国府)から出陣する。其の後足利は、坂本に布陣した。南方からの畠山尚順の軍と連携して、京都の細川政元・足利義澄方を挟撃し、上洛を狙う算段を立てていた。 | |
| 1,499 | 12 | 24 | 六角高頼が、坂本にて、足利義稙率いる軍に奇襲攻撃を仕掛ける。足利は敗れ、比叡山に逃れた。 | |
| 1,500 |
ジョアン2世が、以下3名の成功を受けて、ペドロ・アルヴァレス・カブラルをインド航海の遠征隊隊長に任命する。 ①クリストファー・コロンブス ②ヴァスコ・ダ・ガマ ③バルトロメウ・ディアス |
|||
| 1,500 | 1 | 20 | 畠山尚順が、紀伊国へ退却する。 | |
| 1,500 | 1 | 30 | 足利義稙が、楊井津(現在の山口県柳井市)に下向する。 | |
| 1,500 | 2 | 1 | 足利義稙が、乗福寺(現在の山口県山口市大内御堀)に入る。 | |
| 1,500 | 3 | 9 |
ペドロ・アルヴァレス・カブラルが、13隻の船と1,500名の隊員と共に、タホ川下流のリスボンから出発する。南米を目指して西へ向かい、喜望峰を回ってインドへ向かうルートを採った。以下2名も乗船した。 ①ヴァスコ・ダ・ガマ ②バルトロメウ・ディアス ガマは航海のコースに必要な指示を与えた。 |
|
| ≈ | 1,500 | 4 | 足利義稙が、大内氏館(現在の山口県山口市大殿大路)に招かれる。 | |
| 1,500 | 4 | 3 |
大内義興が、大内氏館(現在の山口県山口市大殿大路)にて、足利義稙を以下の32膳(25献+2供御+4御台+御菓子)で饗応する。 御立物 式御肴三献 御手懸 御肴次第 ①初献 ❶きそく ❷雑煮 ❸五種盛り ②弐献 ❶刺身鯉子付 ❷菱喰皮入り ❸海老舟盛 ③参献 ❶縮み鮑 ❷鯉の煮物 ❸蛸 ④供御 ❶鯛の焼物 ❷塩引 ❸背腸 ❹鮒膾 ⑤供御 ❶塩 ❷数の子 ❸干鯛 ❹子鱁鮧 ⑥弐御台 ❶鳥の焼物 ❷鮭の焼物 ❸鯉 ❹刺身鯛 ❺御汁 ❻鱧 ❼この桶 ❽鯛 ⑦参御台 ❶大蒲鉾 ❷雁の皮入り ❸貝鮑 ❹御湯土器重 ❺蛸味噌焼 ❻わけの供御 ⑧四御台 ❶氷羹 ❷白魚 ❸雁の焼物 ❹御汁 ❺水母 ❻冷製海鞘 ⑨五御台 ❶鮒焼浸 ❷御汁海豚 ❸太煮 ⑩御菓子 ❶まつき ❷削栗 ❸昆布 ❹蜜柑 ❺ところ ❻飴 ❼串柿 ❽胡桃 ❾海苔 ⑪四献 ❶小蒲鉾 ❷鮒丸煎め入 ❸栄螺盛こぼし ⑫五献 ❶角又 ❷三方尖 ❸御添物鵠生鳥 ⑬六献 ❶刺身鱸 ❷醤煎 ❸鮑 ⑭七献 ❶とっさか ❷饅頭 ❸御添物蝤蛑甲盛 ⑮八献 ❶小串刺し鯛 ❷腹子の煎物 ❸雲丹 ⑯九献 ❶茹で西貝 ❷鶴煎物 ❸数の子 ⑰拾献 ❶大根 ❷蒸し麦 ❸御添物羽敷鶉 ⑱拾壱献 ❶刺身鰤 ❷鮎の煎物 ❸蛤 ⑲拾弐献 ❶岩茸 ❷うんぜんかり ❸御添物牡蠣 ⑳拾参献 ❶つべた貝 ❷やまぶき煎 ❸くるくる ㉑拾四献 ❶雉の足 ❷海老羹 ❸御添物鰤子 ㉒拾五献 ❶さし水母 ❷鱏の煎物 ❸馬刀貝 ㉓拾六献 ❶蓮根 ❷羽羊羹 ❸海鞘 ㉔拾七献 ❶小串刺し雁 ❷鱈の煎物 ❸唐墨 ㉕拾八献 ❶刺身鯒 ❷のりからみ ❸飯蛸 ㉖拾九献 ❶焦がし海老 ❷つま重ね ❸羽ふし和え ㉗廿献 ❶ほろふ ❷寸金羹 ❸御添物凝煮鮒 ㉘廿壱献 ❶刺身鰤 ❷鴨の煎物 ❸鱈子 ㉙廿弐献 ❶鰆せんばん焼 ❷赤鮋煎物 ❸橘焼 ㉚廿参献 ❶貽貝 ❷鰤の煎物 ❸削り塩引 ㉛廿四献 ❶揉み栄螺 ❷鶫煎物 ㉜廿五献 ❶刺身名吉 ❷𩸽煎物 ❸しとと焼 |
|
| 1,500 | 4 | 22 | ペドロ・アルヴァレス・カブラル一行が山を発見する。「モンテ・パスコアル(現在のブラジルのバイーア州)」と名付けた。 | |
| 1,500 | 4 | 23 | ペドロ・アルヴァレス・カブラルがブラジルの海岸に上陸する。 | |
| 1,500 | 4 | 25 | ペドロ・アルヴァレス・カブラルの全艦隊がポルト・セグーロ(現在のブラジルのバイーア州)に入る。カブラル達は、上陸した土地は島であると考え「真の十字架の島(ベラクルス島)」と名付けた。此の土地には赤色染料の原料となるパウ・ブラジルが豊富に存在していた為、ポルトガルの商人達は「テッラ・ド・ブラジル(ブラジルの地)」と呼んだ。此れは後の国名「ブラジル」の由来となった。 | |
| 1,500 | 5 | 3 | ペドロ・アルヴァレス・カブラルが、当初の目的である喜望峰経由でのインドへの航海を再開する。 | |
| 1,500 | 5 | 24 | ペドロ・アルヴァレス・カブラル一行が、喜望峰付近で激しい嵐に遭い、バルトロメウ・ディアスの船を含む4隻が失われる。 | |
| 1,500 | 7 | 16 | ペドロ・アルヴァレス・カブラル一行がソファラ(現在のモザンビーク)に到着する。 | |
| 1,500 | 7 | 20 | ペドロ・アルヴァレス・カブラル一行がモザンビーク島(現在のモザンビークのナンプーラ州)に到着する。 | |
| 1,500 | 8 | 2 | ペドロ・アルヴァレス・カブラル一行がメリンデ(現在のケニアのキリフィ県)に到着する。インドへ向かう為の水先案内人を雇った。 | |
| 1,500 | 8 | 10 | ディオゴ・ディアスが指揮する船の内1隻が、悪天候により集団から離れる。そして、後に「マダガスカル」と呼ばれる島を発見した。 | |
| 1,500 | 9 | 13 | ペドロ・アルヴァレス・カブラルが、カリカット(現在のインドのケララ州コーリコード)に到着する。カブラルは、香辛料の交易を行なった。 | |
| 1,500 | 10 | 22 | 後土御門天皇が、清涼殿の黒戸御所(現在の京都府京都市上京区京都御苑)にて崩御する。 | |
| 1,500 | 11 | 16 | 後柏原天皇が、第104代天皇として践祚する。 | |
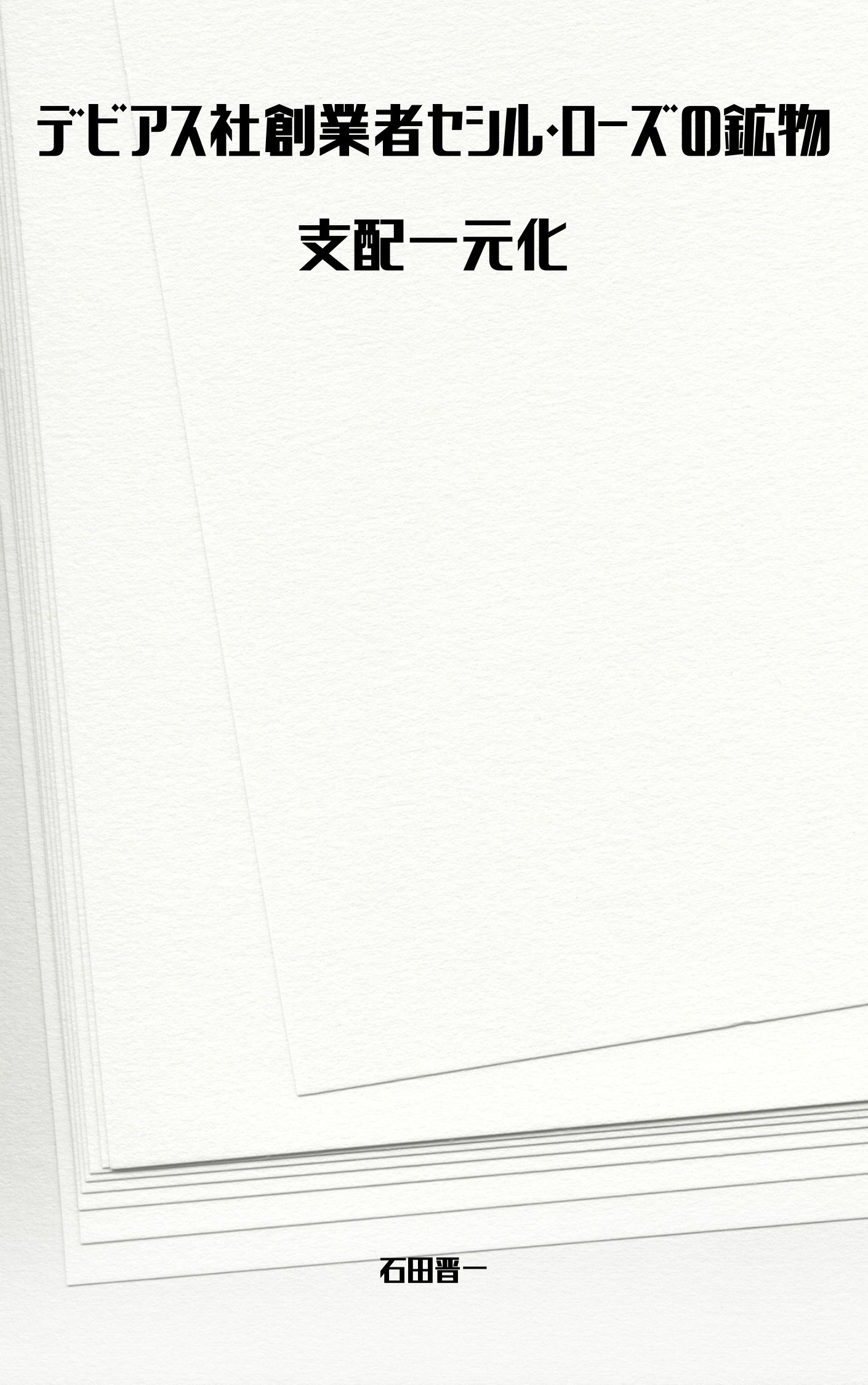
|
ンデベレ王を騙し鉱物を奪取。
|
|
